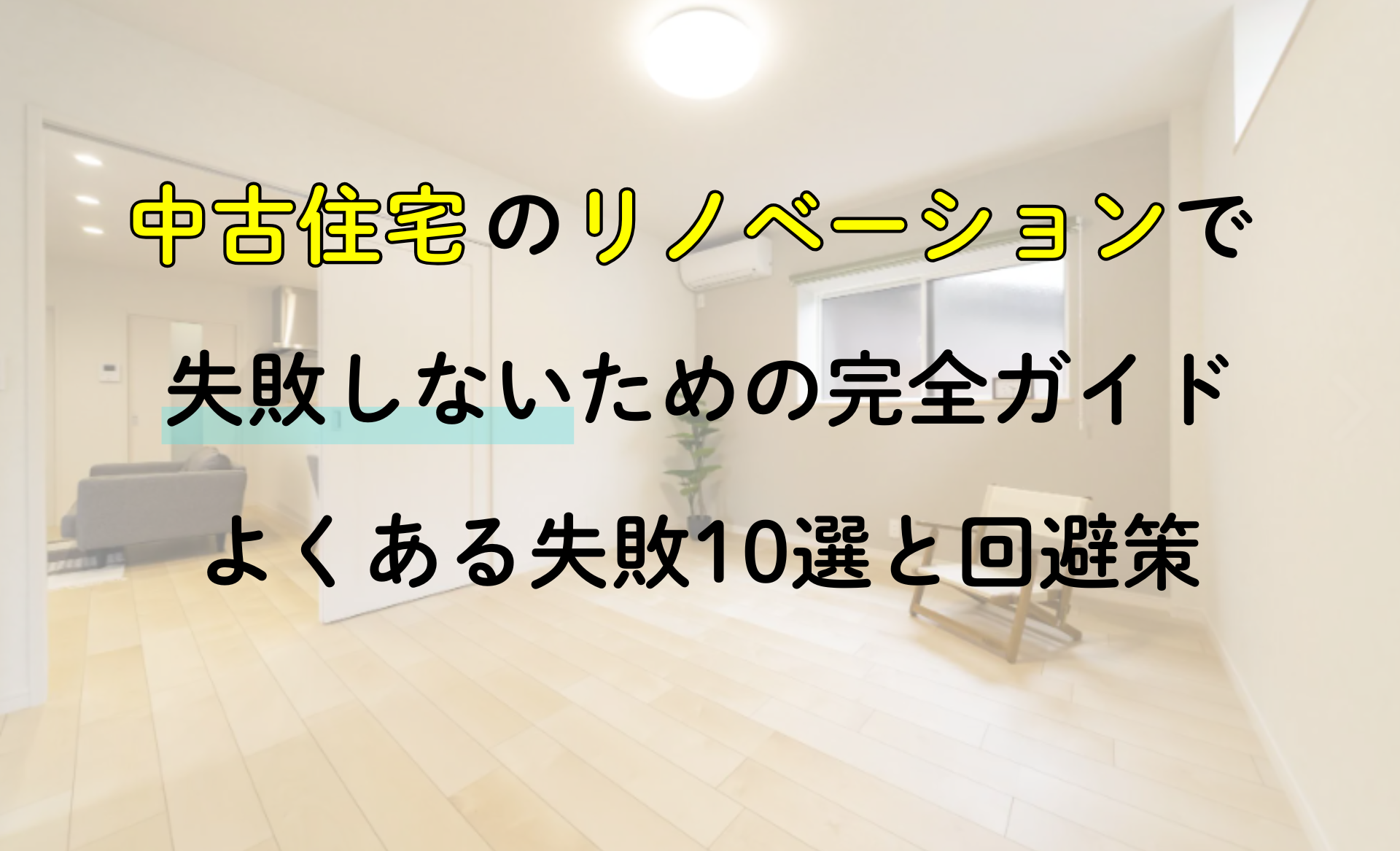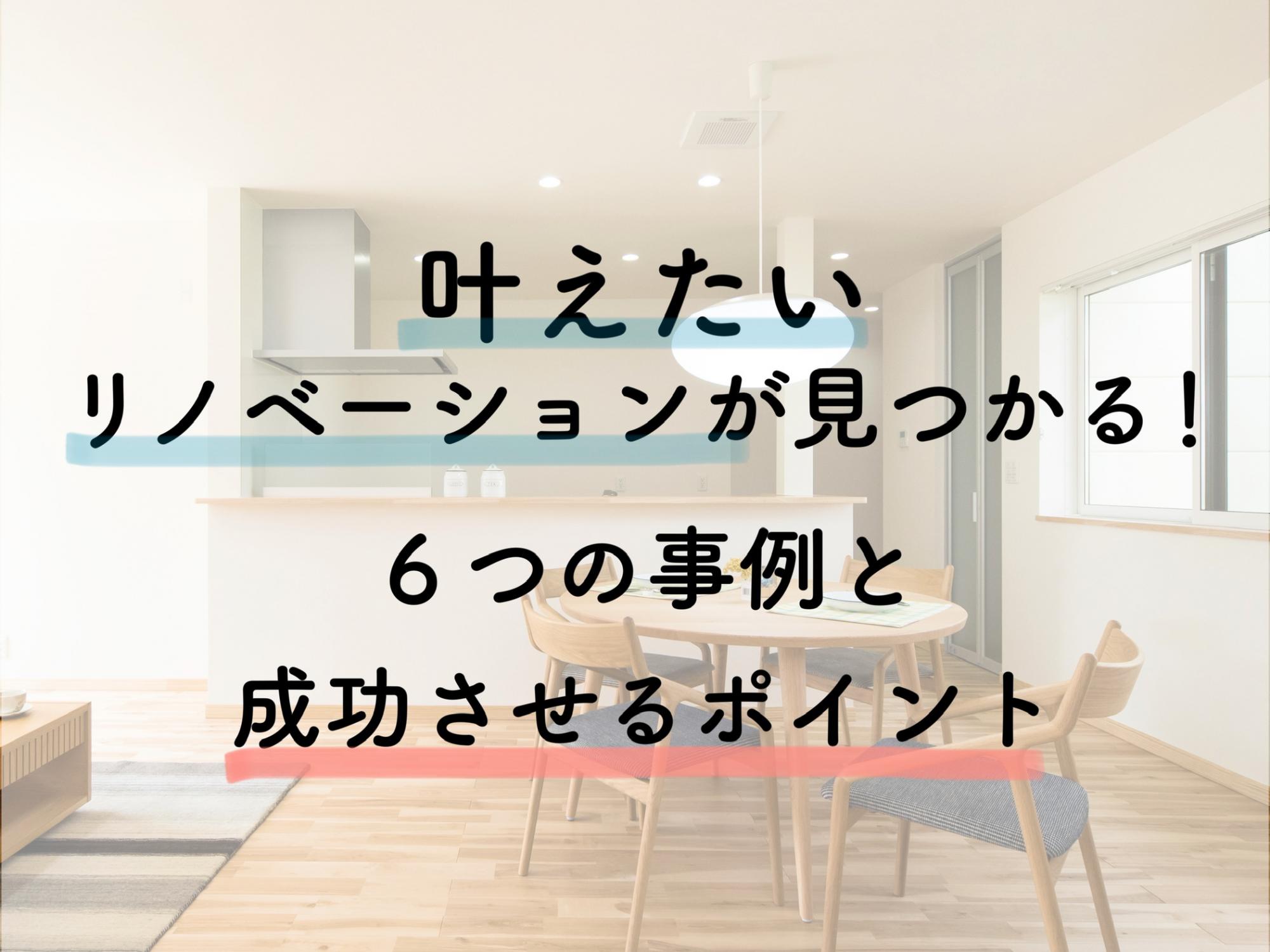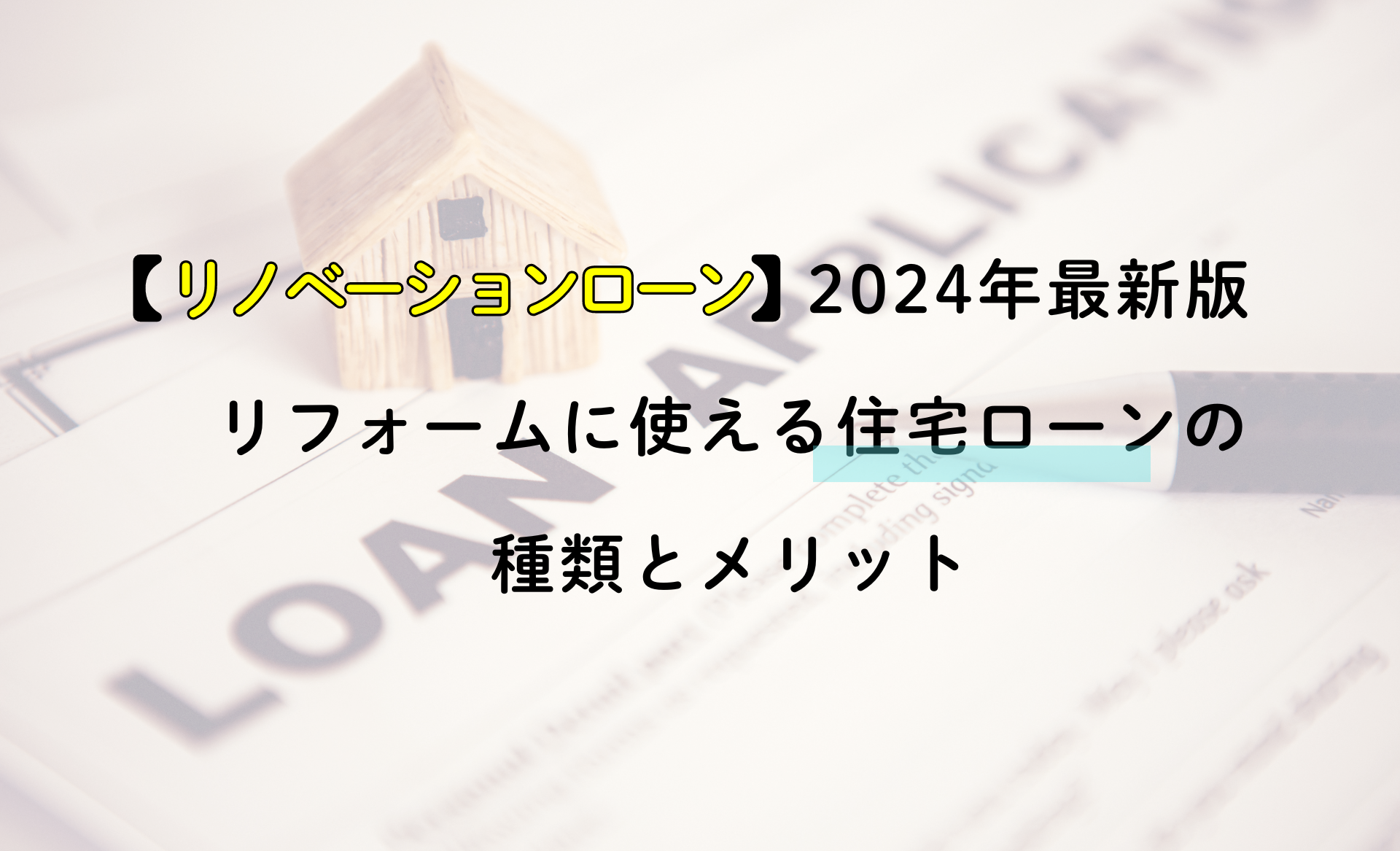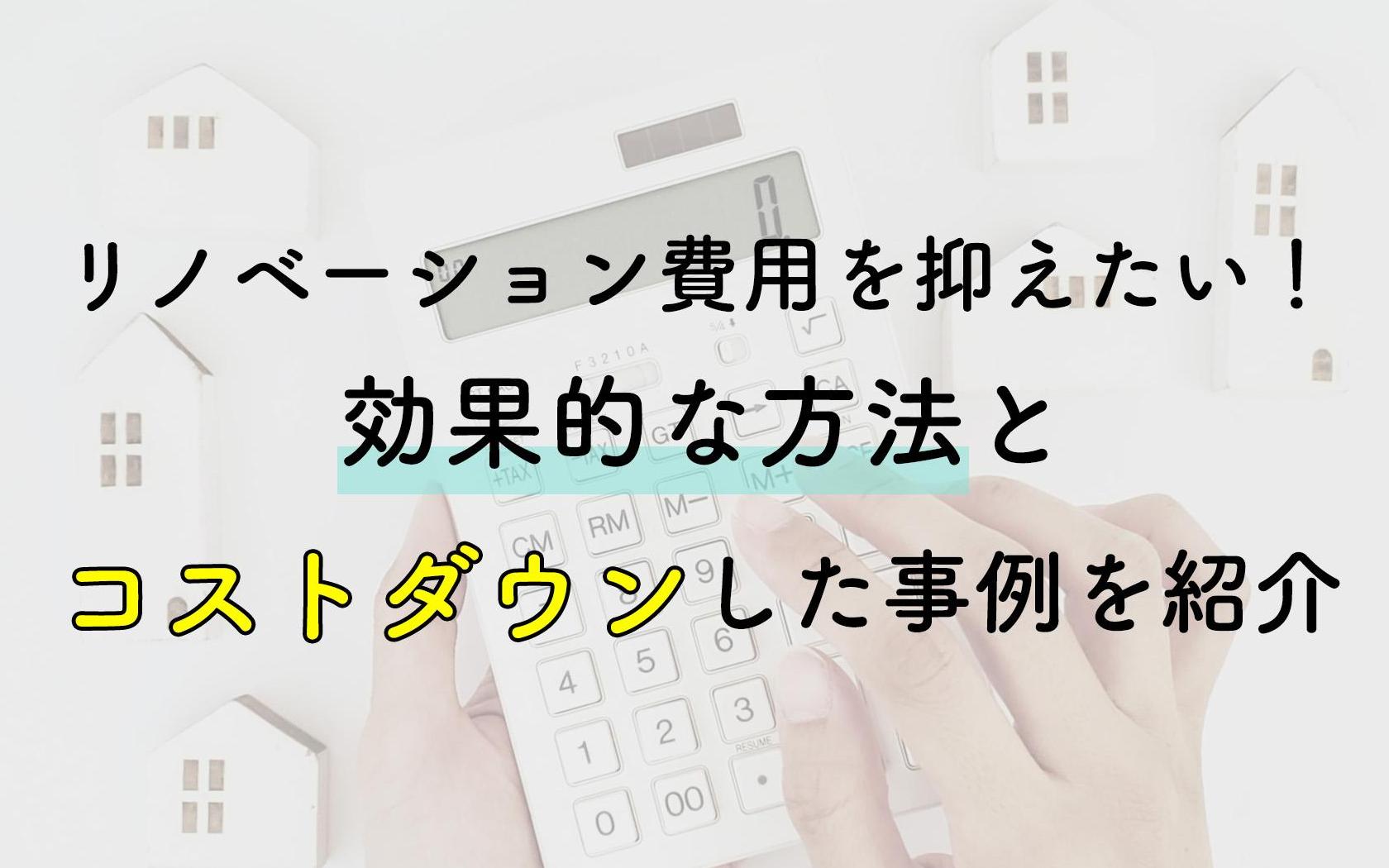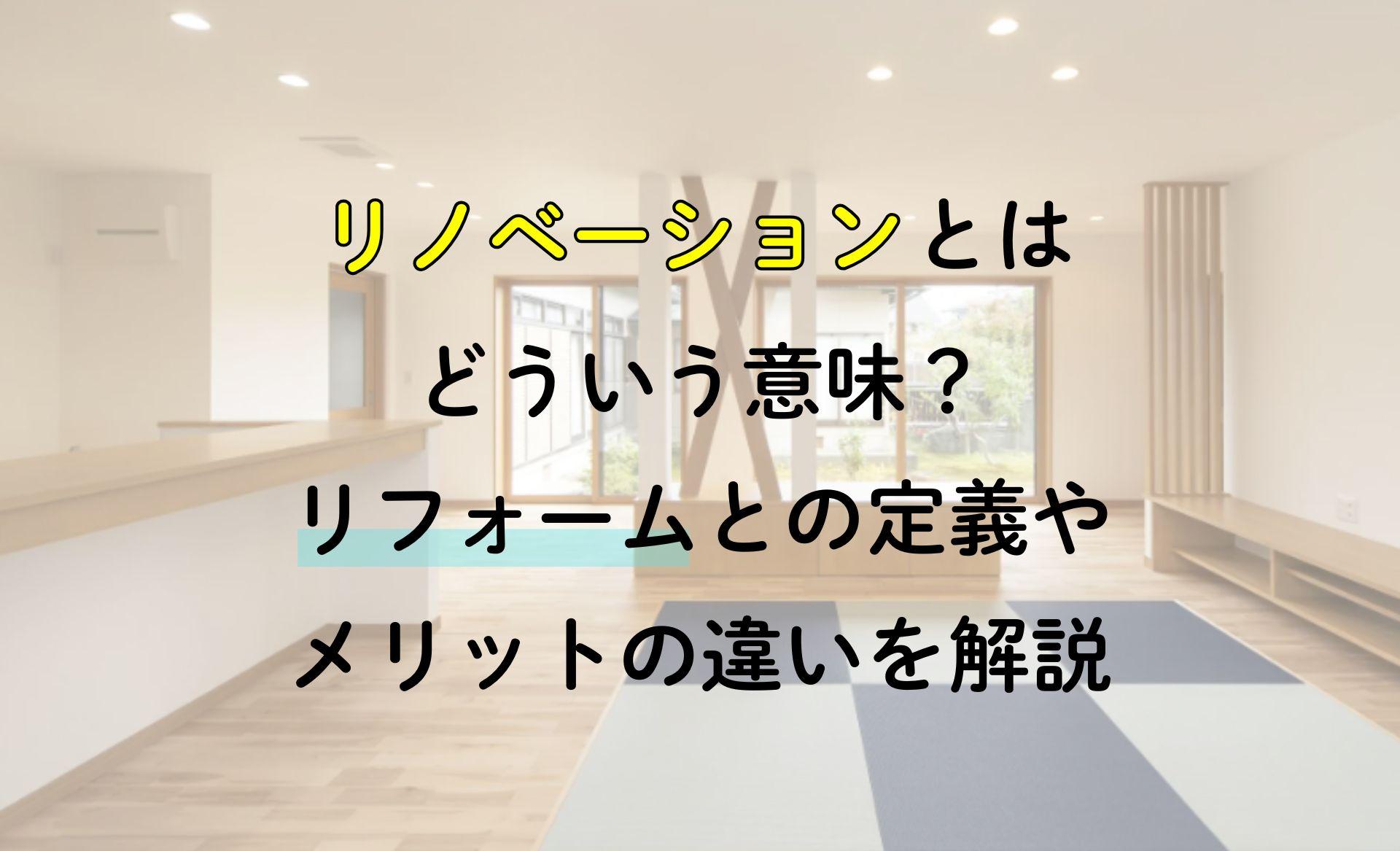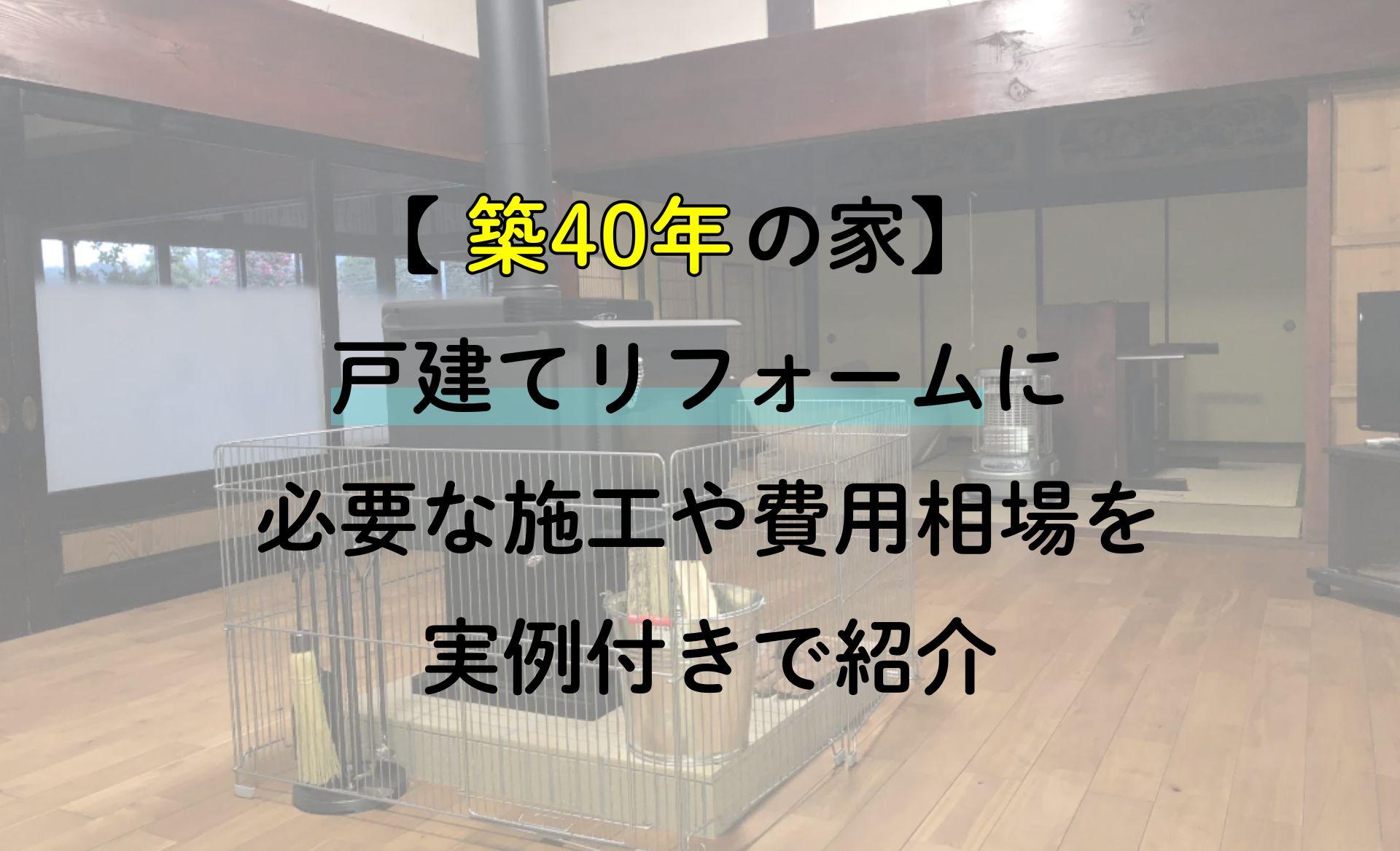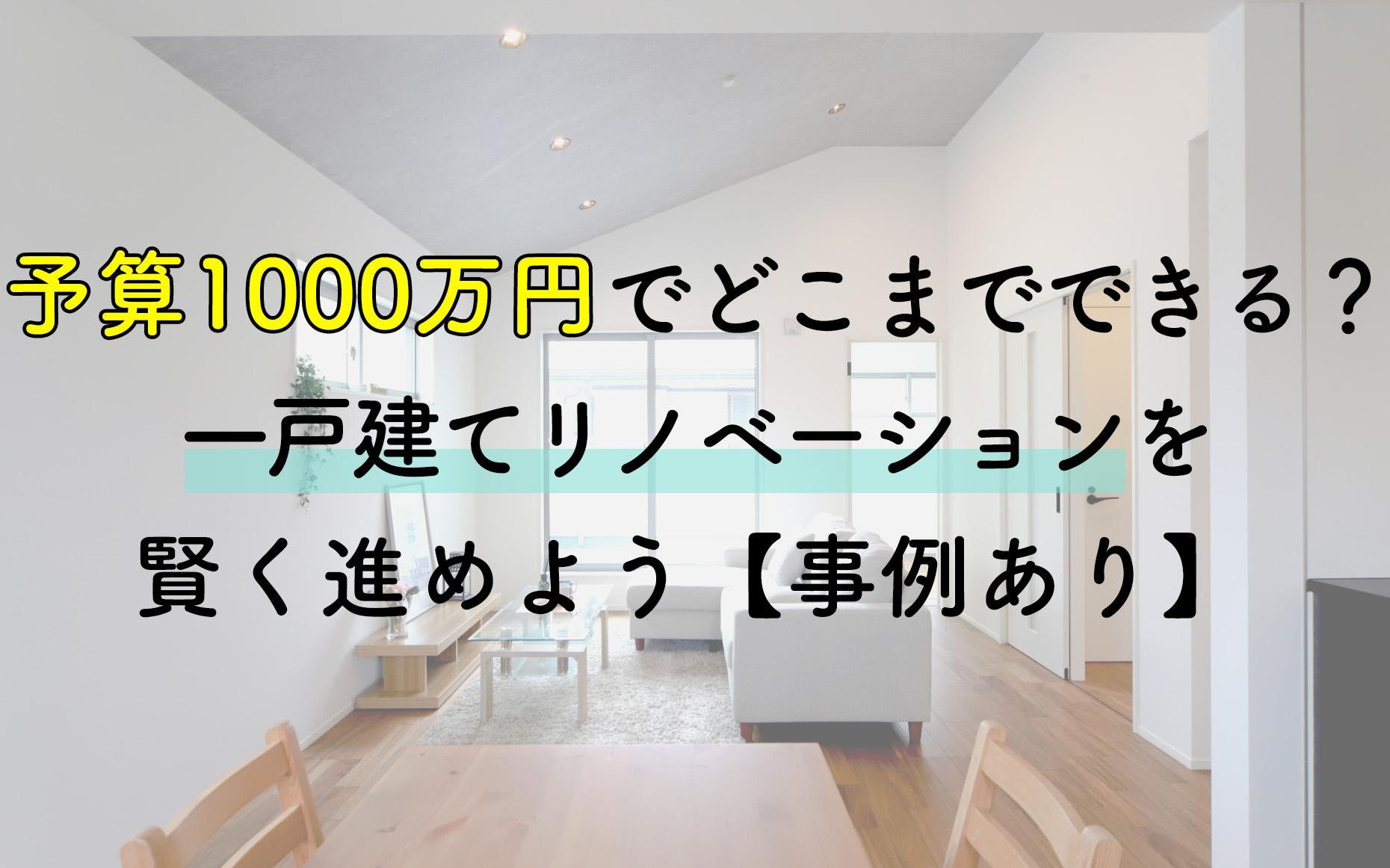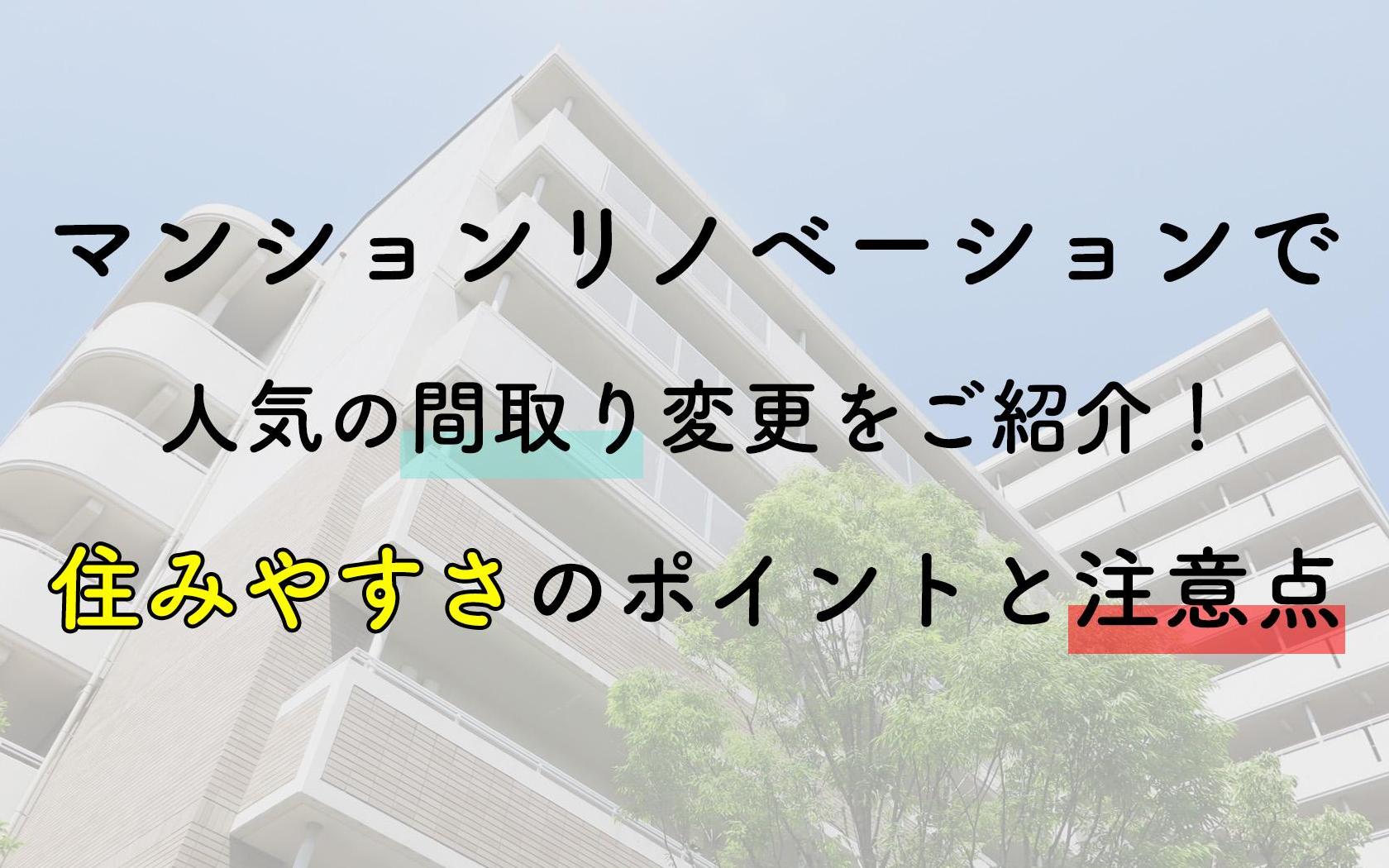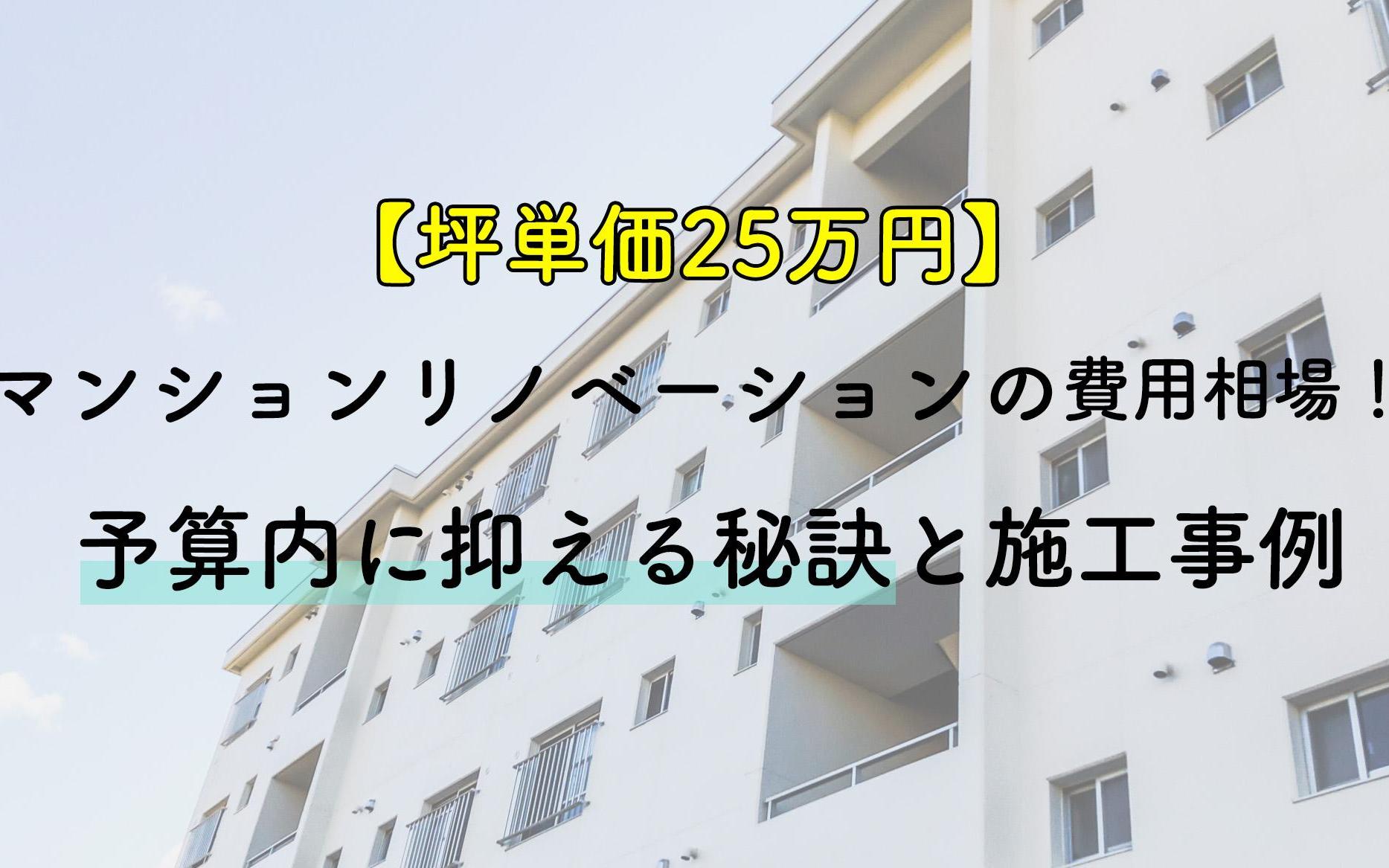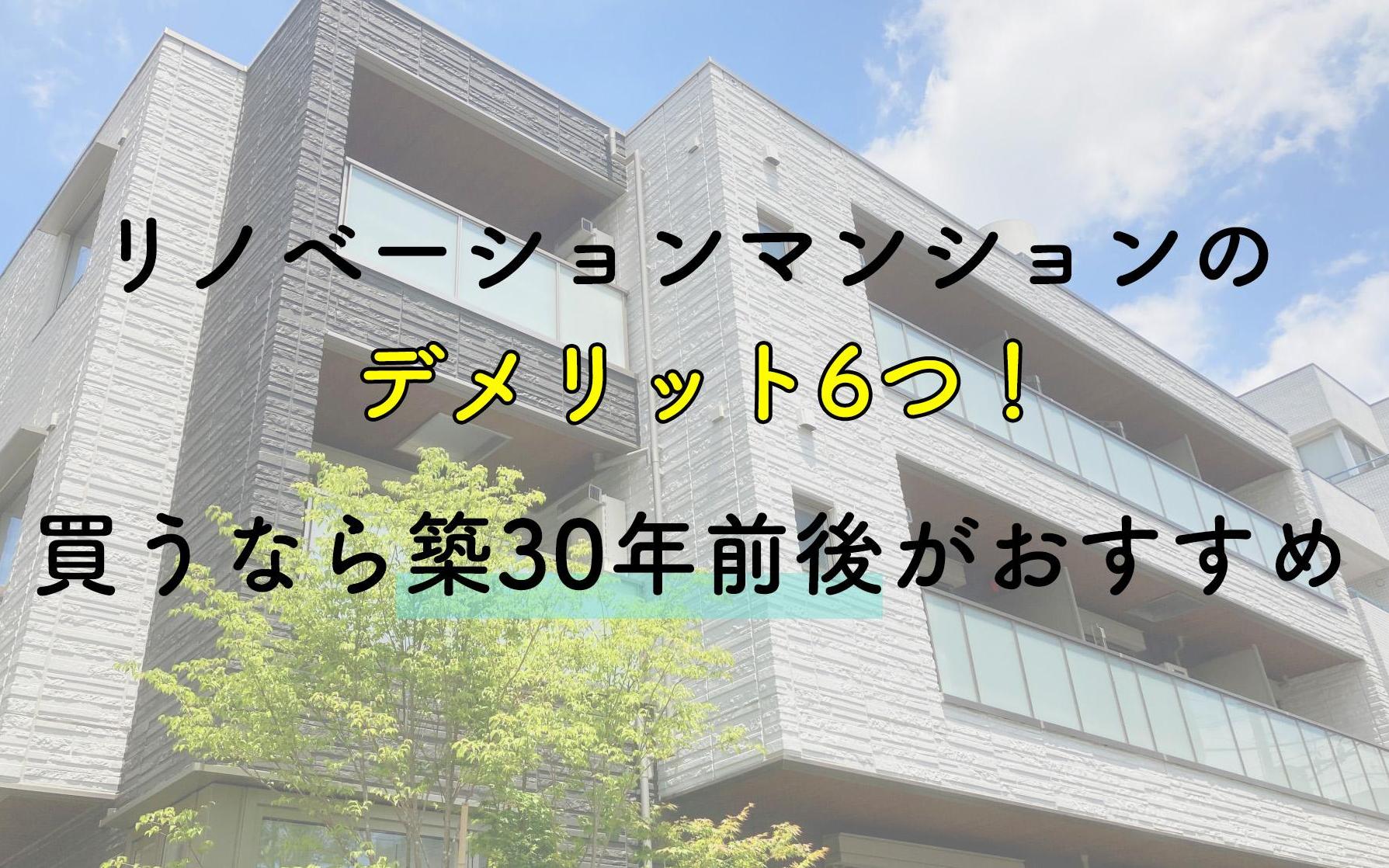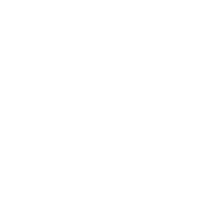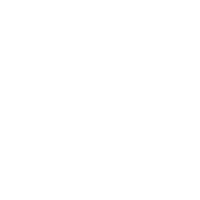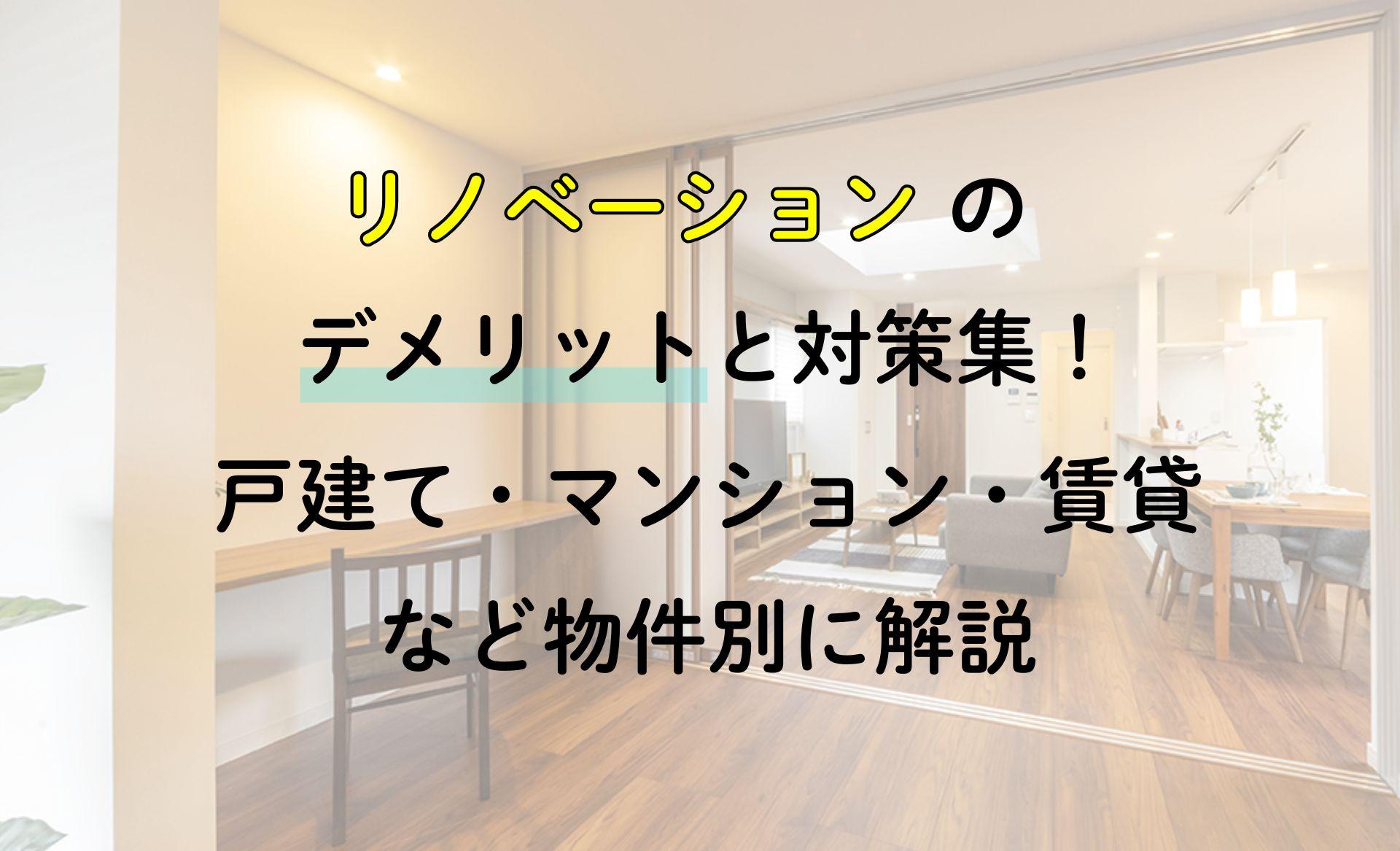
リノベーションにおけるデメリットと対策集!30年以上のノウハウを持つユニテが、プロの視点から詳しく解説していきます。戸建て・マンション・リノベ済み物件それぞれのケースを紹介しますので、「リノベーションに失敗したくない」という方は必見です。
目次
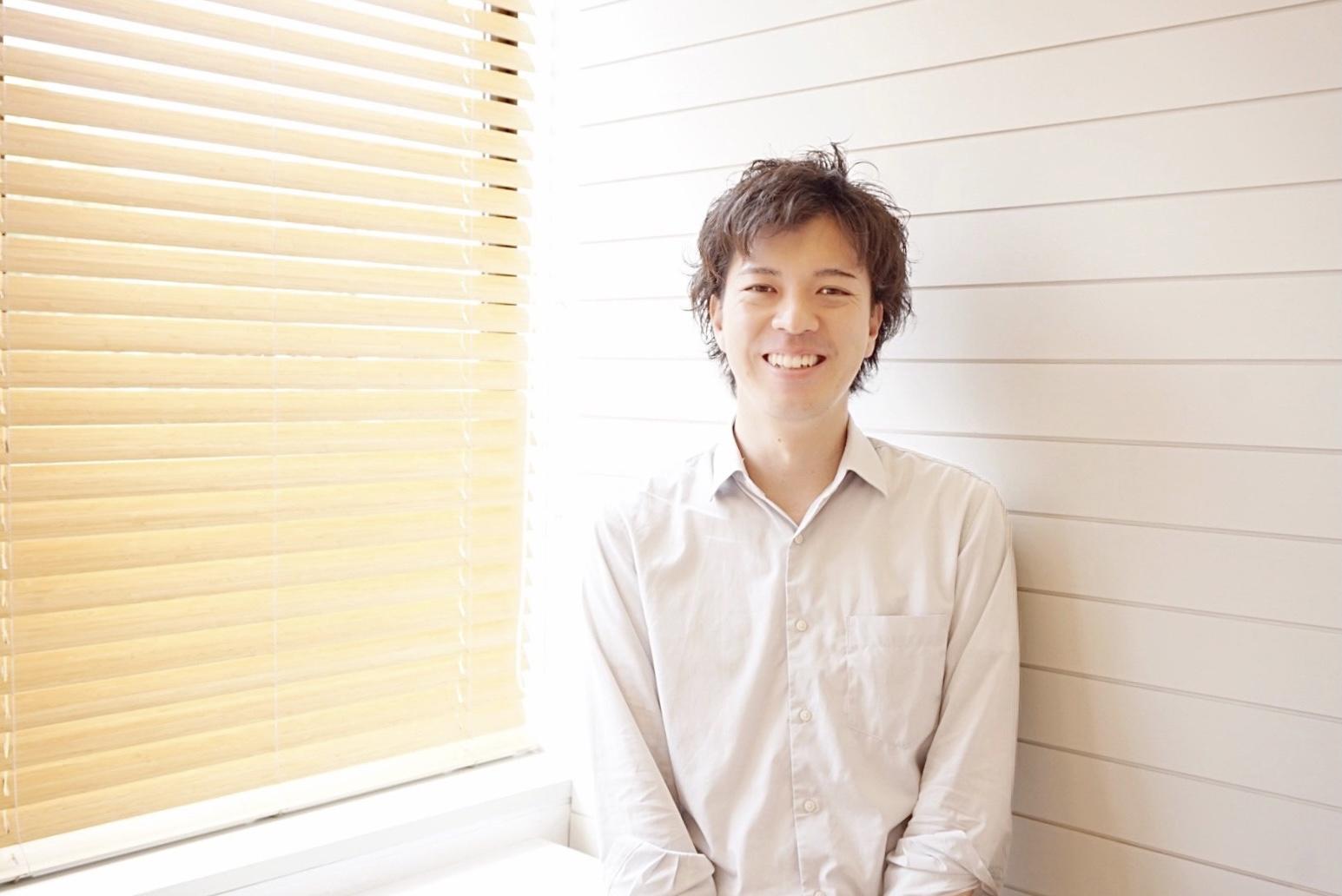
株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
リノベーションに失敗しないために、「どんなデメリットがあるのか知っておきたい」と思っている方は多いのではないでしょうか。
リノベーションのデメリットとしては、具体的には以下が挙げられます。
- 新築よりも高額になることもある
- 窓の交換ができない
- 近隣住民からクレームが入ることがある
- 築40年以上のお家は耐震性に不安が残る
- 間取りの自由が制限されることもある
- 仮住まいが必要になる
- リフォームローンは、借入金額が低くローン金利が高くなる
また、これらのデメリットが気になってしまいリノベーションをするか迷ってしまうという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、リノベーションに携わって30年以上の実績を持つ弊社ユニテが、リノベーションのデメリットと失敗しないための対策を詳しく紹介していきます。
リノベーションはデメリットもありますが、しっかりとポイントを押さえて対策をしていれば、理想の家を低価格で実現することも可能です。
最高の家を手にする一歩を踏み出すお手伝いをいたしますので、この記事をぜひ参考にしてみてください!
【共通】リノベーションの7つのデメリットと対処法
まずは、リノベーション全体におけるデメリットを7つご紹介していきます。
【リノベーションに共通する7つのデメリットと対処法】
| デメリット | 対処法 |
|---|---|
| 新築よりも高額になるケースがある | しっかり費用の計画を立てる (リノベーション費用+物件購入費+将来必要になる修繕費 など) |
| 光熱費がかかる | 断熱工事をおこなう |
| 築40年以上のお家は耐震性に注意 | 耐震診断や耐震補強工事をおこなう |
| 定期的なメンテナンスが必要 | アフターサービスが充実した業者を選ぶ |
| 間取りの自由が制限されることもある | 物件を決める前にプラン設計を明確にする |
| リフォームローンだと不利になる | リノベーションは住宅ローンに組み込む |
| 売りにくくなる・貸しにくくなる | 市場の需要とバランスを考慮する |
それぞれデメリットの詳しい内容と、対処法について解説していきますので、リノベーションを検討している方はぜひ知っておいてください。
新築よりも高額になるケースがある

リノベーションをした物件は、その後も定期的なメンテナンスやリフォームが不可欠です。結果として、新築を建てるよりもトータルコストが高くなることがあります。特に、中古物件は築20〜30年以上のものが多く、すでに一定の経年劣化が進んでいるのが現状です。
たとえば、築30年の物件を購入してリノベーションしたとします。あと40年前後住むことを想定すると、その間に屋根や外壁の修繕、水回り設備の交換などが必要になり、追加のコストが発生するのです。
対処法:トータルコストを見据えた費用の計画を立てる
リノベーションを検討する際は、施工費用だけでなく将来の修繕費用などのその他費用についても考慮する必要があります。中古物件を購入する場合はその購入費用、自宅をリノベーションする場合は引っ越し費用も年頭に置かなければなりません。
光熱費がかかる

築古物件や中古住宅は、最新の住宅に比べると断熱性能が劣っていることが多く、冬は寒く夏は暑い状態に陥りやすい傾向です。そのため、快適に過ごそうとするとエアコンやヒーターの使用頻度が増え、光熱費が高くなりやすいというデメリットがあります。
また、古い建物では電気容量が不足しているケースも多く、現代の生活スタイルに合った家電を使用するには、電気設備の改修が必要になるケースもあるのです。家族が多い場合は、部屋ごとに温度調整が必要になるため、さらに光熱費がかさむことも考えられます。
対処法:断熱リフォームを検討する
光熱費を抑えるためには、断熱リフォームを検討することが有効です。具体的には、以下の対策を講じることで、冷暖房効率を新築同様まで向上できます。
- 壁や天井、床に断熱材を入れる
- 窓を二重窓にする
リノベーションの際は、耐震補強や間取り変更と合わせて断熱リフォームをおこなうと効率的です。見た目のリフォームだけでなく、機能面の改善にも目を向けることで、長期的に快適でコストを抑えた住まいを実現できるでしょう。
築40年以上のお家は耐震性に注意

1981年以前に建てられた建物は、現在の耐震基準を満たしておらず、耐震性に不安が残ります。そのため、築40年以上のお家は、耐震性に注意した上でリノベーションをおこなわなければなりません。
1981年6月1日に建築基準法が大きく改正され、それ以前の基準は「旧耐震基準」、それ以降の基準は「新耐震基準」と改められました。
|
旧耐震基準:中規模地震(震度5強程度)で建物がほとんど損傷しない構造基準 新耐震基準:大規模地震(震度6強~7)でも建物が倒壊しない構造基準 |
旧耐震基準によって建てられた築40年以上の建物は、震度5強程度にまでしか耐えられないので、やはり耐震性に不安が残ります。
対処法:耐震診断や耐震補強工事をおこなう
築40年以上のお家をリノベーションする際は、耐震診断や耐震補強工事をおこなうことが大切です。新耐震基準で建てられた建物でも、劣化などが懸念される場合は耐震診断をされることをおすすめします。
また、耐震補強のリノベーションに対しては補助金制度があるため、そちらを利用して耐震補強をされるとより安心です。
築40年以上の物件におけるリノベーションのコツは、以下の記事もご覧ください。
「【築40年の家】戸建てリノベーションのコツ!必要なリフォーム内容や費用相場を実例付きで紹介」
定期的なメンテナンスが必要
先述した通り、一度リノベーションをした物件でも、定期的なメンテナンスは必要です。10〜20年住むと必ずどこかの修繕が発生するため、計画的なメンテナンス費用の確保が重要になります。
- 外壁塗装
- クロスの張り替え
- 防水工事
- 水回り設備の交換
- シロアリ駆除 など
劣化を放置すると大規模な修繕が必要となり、余計な費用がかかるため、計画的に修繕費用を積み立てることが望ましいでしょう。
対処法:アフターサービスが充実した業者を選ぶ
メンテナンス費用を抑えるためには、アフターサービスが充実したリノベーション会社を選ぶことが大切です。リノベーション会社によっては、以下のサービスを一貫して対応する「ワンストップ型リノベーション」を提供しているところもあります。
- 資金計画
- 物件探し
- 施工
- アフターサービス など
また、メーカー保証や工事保証がある会社を選ぶと、突発的な修繕費用も軽減できます。定期的な点検を行い、劣化を早めに発見して修繕コストを抑える工夫も必要です。
間取りの自由が制限されることもある

リノベーションのおこなう際に注意すべき点としては、間取りの自由が制限されることも挙げられるでしょう。
たとえば戸建ての場合だと、木造の「2×4(ツーバイフォー)工法」や「軽量鉄骨造」などのいわゆる「壁構造」に注意が必要です。この構造の住宅は建物を「面」で構成しており、必要な壁を取り払うことが難しいため、間取りの制限が大きくなってしまいます。
また、マンションやアパートでは、一部が下がり天井になっていることがありますが、この構造がネックになるケースが多いです。鉄筋コンクリート造のマンションは、建物全体を支える構造部材として柱同士をつなぐ梁があり、この梁が下がり天井の原因になっています。
また、管理規約によるリノベーションの制限が生じたり、水回りの移動が難しかったりする可能性も考えられるでしょう。
対処法:物件を決める前にプラン設計を明確に
「リノベーションで希望の間取りができなかった」という後悔をしないためには、まず物件を決める前にプラン設計を明確にしておく必要があります。プロの意見を聞きながら、どの程度間取り変更ができるかを確認し、リノベーション可能な物件を選ぶことが大切です。
また、マンション・アパートの場合は、管理規約をしっかり確認しましょう。管理規約は物件ごとに異なりますので、購入前に自分のやりたいプランが実現できるか確認しておけると安心です。管理組合や不動産会社に聞いてみるのがいいでしょう。
さらに、リノベーション会社が開催する相談会やイベントに参加することで、成功事例を参考にしながら計画を進めることもできます。事前の準備をしっかり行い、理想の住まいを実現しましょう。
リフォームローンだと不利になる

リフォームローンは通常無担保であり、借入金額の上限が1,000万円となっています。また、「リフォームローンは金利が高い」というイメージを持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に住宅ローンとリフォームローンを比較してみると、リフォームローンは住宅ローンに比べて借入金額が少なく、金利も高いということが分かります。
| 住宅ローン | リフォームローン | |
| 借入限度額 | 100万円~2億円 | 10万円~1000万円 |
| 借入年数 | 2~40年 | 1~15年 |
| 金利 |
変動金利:0.975% 固定金利:0.6~1.3% |
変動金利:4.15% 固定金利:5.2% |
| 担保 | 必要 | 不要 |
(富山県のある地方銀行の例)
対処法:リノベーションの場合は住宅ローンに組み込める
リノベーションの場合、お家全体の改装になることが多いため、そういった場合はリノベーションのローンを住宅ローンに組み込むことができます。
自分の場合は当てはまるのか、など分からないことも多いと思います。その場合は、一度リフォーム会社に相談してみましょう。弊社ユニテでは、お客様と一緒にローンや資金計画等について考えていきますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。
リノベーションローンに関しては以下の記事もご覧ください!
「【リノベーションローン】2024年最新版|リフォームに使える住宅ローンの種類とメリット」
売りにくくなる・貸しにくくなる

リノベーション物件は、手放す際に売りにくくなったり、貸しにくくなったりするデメリットがあります。
リノベーションは、自分の好みやライフスタイルに合わせて独特のデザインや間取りに変更できるのがメリットです。しかし、個性的な内装や奇抜なデザインは市場の需要と合わないケースも多く、売却時や賃貸時に買い手・借り手が見つかりにくくなるリスクもあります。
多くの購入者は、時代に左右されないシンプルで普遍的なデザインを好む傾向があるため、特定のテイストに偏った物件は敬遠されやすくなってしまうでしょう。
対処法:市場の需要とバランスを考慮してリノベーションする
手放す際のことを検討している場合は、流行に左右されにくいデザインや間取りを意識してリノベーションすることが重要です。たとえば、ナチュラルテイストやモダンなシンプルデザインを取り入れると、幅広い層に受け入れられやすくなります。
また、将来的な売却や賃貸を見据え、内装の変更がしやすい仕様にすることも有効です。市場の需要を考慮しながら、バランスの取れたリノベーションを計画しましょう。
戸建て住宅のリノベーションにおけるデメリットと対策

ここからは、戸建てリノベーションのデメリットとその対策についてご紹介していきます。
- 新築よりも高額になりやすい
- 家の性能に不安がある(断熱性・耐震性)
- 定期的なメンテナンスが必要
- 引っ越し費用や仮住まい費用がかかる など
先ほど紹介したリノベーション全体のデメリットの中でも、一戸建てに顕著なのは「リノベーションにかかる費用」でしょう。戸建てのリノベーションが高くなりすぎてしまうのは、主に以下の3つのケースです。
- 施工範囲が広い場合(施工面積)
- 施工規模が大きい場合(スケルトンリフォームなど)
- こだわりを詰込み過ぎている場合
家を全面的に新しくしたい、とことんディティールにこだわりたいという気持ちが強い方もいらっしゃると思います。ですが、フルリノベーションをしたりデザイン性を追求しすぎたりすると、その分費用も高くなってしまうでしょう。
また、リノベーションの規模によっては自宅に住み続けられないので、工事が終わるまでの仮住まい費用も必要です。
対策1.こだわりたい優先順位を決める

リノベーションをおこなう面積が広いほど費用が高くなるため、面積によっては新築の費用を超えてしまいます。リノベーション会社によって一坪あたりの費用目安があり、ユニテの場合は40万〜50万/坪です。
また、デザインや素材を追求し、金額の高い設備ばかりを選んでいくと結果的に新築よりも高くなることがあります。たとえば、バスルームリノベーションで浴槽を取り替える際も、5万円程度のものから100万円を超えるものまで、さまざまな金額のものがあるのです。
そのため、戸建てのリノベーションで大切なのは、優先順位を考えて「絶対に譲れない部分」を決めておくことです。
- キッチンだけは自分の思うようなデザインにしたい
- お風呂を広々とした落ち着く空間にしたい
- お気に入りの部屋は雰囲気をそのままにしたい
など、人それぞれ譲れないこだわりがあるはずです。そういった部分に力を入れて、他の部分は少し妥協するということも考えてみてはいかがでしょうか。
対策2.ホームインスペクションをする
「現在の家の性能が気になる」「傷んでいるところを重点的に新しくしたいが、どこを新しくすればいいのか分からない」といった方は、「ホームインスペクション」をおこなうのがおすすめです。
建築士がお家の傷み具合や新しくしたほうがよい箇所などを確認し、お家の状態を診断することをインスペクションと呼びます。リノベーション前にホームインスペクションをおこなうことで、事前にお家の現状が把握できるのがメリットです。
これを上手く利用してリノベーションすることにより、家をより長持ちさせることができます。
対策3.長期的な視点でかかる費用を考える
戸建てリノベーションをおこなう際は、初期費用だけでなく長期的な維持費も考慮することが重要です。リノベーション後の住宅は、新築に比べて外壁塗装・水回り設備の交換・防水工事などの定期的なメンテナンスが必要になります。
築年数が経過した物件では修繕費がかさむ可能性もあるため、計画的な資金管理をおこない、将来を見据えたリノベーションを検討しましょう。
たとえば、リノベーション時に耐久性の高い建材や設備を選ぶことで、メンテナンス費用を抑えられます。将来的に発生する大規模な修繕リスクを軽減するために、定期的な点検で劣化を早期発見することも重要です。
また、リノベーション費用がかさんでしまったとしても、長期的に見ると新築よりも経済的な選択肢となる場合もあります。築年数が経った物件は固定資産税が減額されるため、長く住み続けるのであれば初期投資として検討するのもいいでしょう。
「リノベーションをできるだけ安くおこないたい!」という方は、以下の記事もご覧ください。
「【リノベーションローン】2024年最新版|リフォームに使える住宅ローンの種類とメリット」
対策4.今の家に住みながらできるプランを検討する
ご自宅をリノベーションするとなると、一時的に別のお家を借りなければならないケースもあります。リノベーション費用に加えて引っ越しの費用や、仮住まいの賃料などを考えると少し気が重くなってしまいますよね。
「仮住まいの費用をかけたくない」という方は、今の家に住みながら、荷物をその都度別の部屋に移動しながら工事を進めていく方法もあります。賃料や引っ越し代がかからないため、その分の費用をリノベーションの予算に回すこともできるでしょう。
ただし、今の家に住みながらリノベーションをおこなうよりも、「一時的に別のお部屋を借りて生活をするほうが楽」ということは念頭に置いておく必要があります。
マンション・賃貸のリノベーションにおけるデメリットと対策

ここからは、マンション・賃貸におけるリノベーションのデメリットをご紹介します。
- 古い設備のリスク
- 間取りや施工内容に制限がある
- 水回り設備の老朽化
- 共用部分はリノベーションできない
- 光熱費や断熱性への懸念
- 近隣トラブルへの懸念
マンションや賃貸物件のリノベーションでは、建物のうちの1部を所有することになるため、施工範囲が限られてしまいます。たとえば、購入した部屋の大部分は占有部分に該当しますが、窓やバルコニーは共有部分の扱いです。
また、建物の構造やマンションの管理規約によっては、理想通りのリノベーションが叶わない可能性もあります。
対策1.購入前に現地で直接建物の状態を見る
すでに住んでいる物件でなく、これから中古物件を購入してリノベーションしようと検討している場合は、必ず購入前に現地で物件の状態を確認しましょう。可能であればリノベーションを依頼する業者など、専門家と一緒に内見に行くことをおすすめします。
- 築年数(老朽化のチェック)
- 躯体の状態(改修必須の場所はあるか)
- 間取り(理想のリノベーションができるか)
- 再利用可能な部分(そのまま使える部分はあるか)
- 立地
- 瑕疵担保期間
- マンションの管理規約 など
また、上記だけだとわからないことも多いため、ホームインスペクターや一級建築士に依頼し、住宅診断を受けることも大切です。住宅診断を受けることで、目に見えない部分の問題点を事前に把握でき、リノベーションの施工に反映できるメリットがあります。
中古物件の選び方のコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。
対策2.建物内の住民にあいさつ回りをする
マンションやアパートの場合、工事の音が他の部屋へ響きやすいことから、隣や上下階のお部屋の住人とのトラブルが起こってしまう可能性があります。
工事期間が予定よりも延びてしまったり、建物の構造上壁が薄かったりする場合は、クレームが入る可能性が高くなってしまうでしょう。
隣人トラブルを防ぐには、工事が始まる1週間前には挨拶回りを済ませておくのがベターです。リノベーションの工事期間や工事を行う時間帯、工事内容などを事前に伝えておくとなおよいでしょう。
またこのご時世、対面でのお話が難しい場合もあると思います。そういった場合はお手紙を投函するなどの対応をするのがよいでしょう。
対策3.インナーサッシを取り付ける

築年数が経っているマンションやアパートにお住まいの方は、冬の冷気や結露が気になることもあるのではないでしょうか。暖房をつけてもなかなかお部屋が暖まらないと感じるのは、窓から熱が逃げてしまっていることが原因です。
しかし、窓は共有部分になるため、取り替えたり塞いだりすることはできません。そのため、インナーサッシを取り付けることで対策する必要があります。
インナーサッシは、元々ある窓の内側にもう1つ窓サッシを取り付ける方法です。インナーサッシを採用することで、二重の窓の間に空気の層ができ、室内の熱は逃げづらく、室外からの冷気は入りづらくなります。インナーサッシのメリットはそれだけではありません。
- 断熱性向上
- 結露対策
- 防音対策
結露は、暖かく湿った空気が冷やされ、空気中の水蒸気が水に変わることで発生し、放っておくとカビやダニ、シミの原因になります。窓を二重にすることで熱を伝えにくい空気の層が生まれるので、結露が起こりにくくなるのです。
また、二重窓にすることで防音対策にもなりますので、ペットを飼われている方や楽器が趣味の方など、近隣への音漏れが気になっている方にもおすすめです。
さらに、インナーサッシを取り付けることで鍵も二重になるため、防犯性も高まります。1階や2階のお部屋にお住まいの場合は、防犯対策も兼ねて二重窓を取り入れてみてはいかがでしょうか。
リノベ済み物件のリノベーションにおけるデメリットと対策

リノベーション済みの中古物件の購入を検討している方は、以下のデメリットに留意した上で物件選びをすることが大切です。
- 物件の販売価格が割高
- 見えない部分の施工状態がわからない
- 好みの物件がない場合がある
- 立地を選べない
価格が適正か判断するためには、同じエリアの類似物件と比較し、リノベーションの内容やコストパフォーマンスを確認することが大切です。単に「高い」「安い」ではなく、リノベーションの質と価格のバランスを考慮しましょう。
また、耐震補強や断熱性能の向上など、見えない部分の工事がしっかりおこわれているかもチェックすると、適正価格かどうか判断しやすくなります。事前に市場価格を把握し、コストに見合った価値があるか慎重に見極めましょう。
対策1.販売価格が適切かリサーチする
リノベ済み物件を購入する際は、販売価格が適切かをリサーチすることが重要です。リノベ済み物件は、リノベーション費用が上乗せされているため、新築よりは安価でも中古物件と比べると割高に設定されています。
対策2.施工範囲とかかった費用を確認する
リノベ済み物件は見た目が新しく整えられていますが、建物の躯体や配管・配線など、目に見えない部分の老朽化が残っている可能性もあります。これらの部分がリノベーションの対象外だった場合、購入後に追加で補修費用がかかることがあるため注意が必要です。
そのためリノベ済み物件を購入する際は、施工範囲とかかった費用を事前に確認することが大切になります。どこまで施工がおこなわれたのか、費用の内訳をしっかり確認しましょう。
また、耐震補強や配管・配線の交換が実施されているかをチェックし、不安がある場合は専門家に相談すると安心です。見た目だけで判断せず、物件全体の品質を総合的に評価することを心掛けてください。
対策3.住宅瑕疵保険に着目する
リノベーション物件では、購入後に隠れた不具合が見つかる可能性があります。特に、構造部分や設備の不具合が発生した場合、修繕費が高額になることもあるため注意しましょう。
そのため、リノベ済み物件を購入する際は、万が一に備えてリフォーム瑕疵保険に加入しているかを確認することが重要です。住宅瑕疵保険は、リノベーションをおこなった業者が加入するものなので、物件の販売会社から確認できます。
保険に加入している物件であれば、購入後に不具合が発生しても補修費用がカバーされるので、安心して住み続けられるのがメリットです。そのため、気になる物件があれば、瑕疵保険の有無を必ずチェックしましょう。
リノベーションのデメリットを解消したおしゃれな施工例

ここからは、弊社ユニテが担当したリノベーションの中から、デメリットを解消しつつおしゃれに仕上げた施工事例を3つ紹介していきます。どのように工夫すべきか悩む方は、ぜひ参考にしてみてください。
構造上の制限を活かしたリノベーション事例

こちらの事例の左側にある壁は、構造上取り壊せなかったものです。この壁の陰に収納棚を設置したり荷物を置いたりすることで、リビングからの目隠しとして活用できます。
また、壁と仕切りの間にデスクを設置することにより、読書や書き物ができるスペースとしても活用できるようになりました。

また、こちらは構造上取り外すことのできない壁の間にテレビボードを設置した事例です。壁のデザインとテレビボードに親和性を持たせることで、壁を邪魔に感じることなく、むしろデザイン性が高まって見えます。両脇にスピーカーを置いてもいいですね。
このように、取り壊せないことをマイナスにとらえるのではなく、生かすことができないかと考えてみるのはいかがでしょうか。リフォーム・リノベーション会社は、間取りを考えるプロです。
弊社ユニテでは、お客様のお悩みをヒアリングし、ご満足いただける間取りをご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
マンションの管理規約に配慮したリノベーション事例

Before

After
上記は、築年数23年のマンションをリノベーションした事例です。21坪のお部屋を費用680万円でフルリノベーションしています。
間取りはそのままに、LDK横にあった和室を洋室に変え、ご夫婦の寝室として使用するなど、お部屋ごとの用途を変えました。全体的にナチュラルカラーで統一することで広い空間を演出し、明るく過ごしやすいお部屋になりました。
マンションの管理規約により窓の取替えができないため、LDKや娘さんのお部屋などにはインナーサッシを取り付けて二重窓にしています。

Before

After
部分的にこだわりを出したリノベーション事例


こちらは、キッチンと寝室にのみこだわりを詰め込んだ事例です。特にキッチンにこだわりを持ってらっしゃる施主様でしたので、その想いを反映したおしゃれなカフェ風のキッチン・ダイニングに仕上げました。
一方、寝室や玄関などは現存のまま利用して少し手を入れるだけにしています。こだわりたい部分と、そうでない部分を明確にしているからこそ、満足のいくリノベーションに仕上がりました。
富山県のリノベーションにお悩みならユニテにお任せください

全面的なリノベーションが予算的に難しい場合に、他のお部屋は少し妥協したとしても「ここだけは特に力を入れてリノベーションしたい」という部分がある方は、リノベーションすべきだと考えます。
毎日のお料理が楽しくなるようなキッチン、秘密基地のような自分だけの書斎スペースなど、特にこだわった部分はより愛着が湧くはずです。
弊社ユニテは、リフォーム・リノベーションに30年以上携わっており、豊富なノウハウと実績がございます。一戸建てはもちろん、マンションのリノベーション実績も豊富なので、お客様の要望や予算に合わせた適切なプランを提案可能です。
無料相談なども定期開催していますので、些細なことでもどうぞご気軽にご相談ください。家に帰るのが楽しみになるようなリノベーションを一緒に考えていきましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせはコチラ】
まとめ
新築とリノベーションやリフォームを比較して考えると、一番の大きな違いは間取りの自由度です。
構造上取り払うことのできない柱や壁があったり、水回りの移動ができないという規制の中で、それを受け入れることができる人、間取りの制限を生かしたアイデアを楽しむことができる人はリノベーションに向いています。
メリットだけでなくデメリットを知ることで、リノベーションについてより深く知ることができるでしょう。また、どんなデメリットにも、解決策や未然に防ぐ方法があると思います。
まだ抱えている不安が解消されていないという方は、ぜひ弊社ユニテまでお気軽にご相談ください!