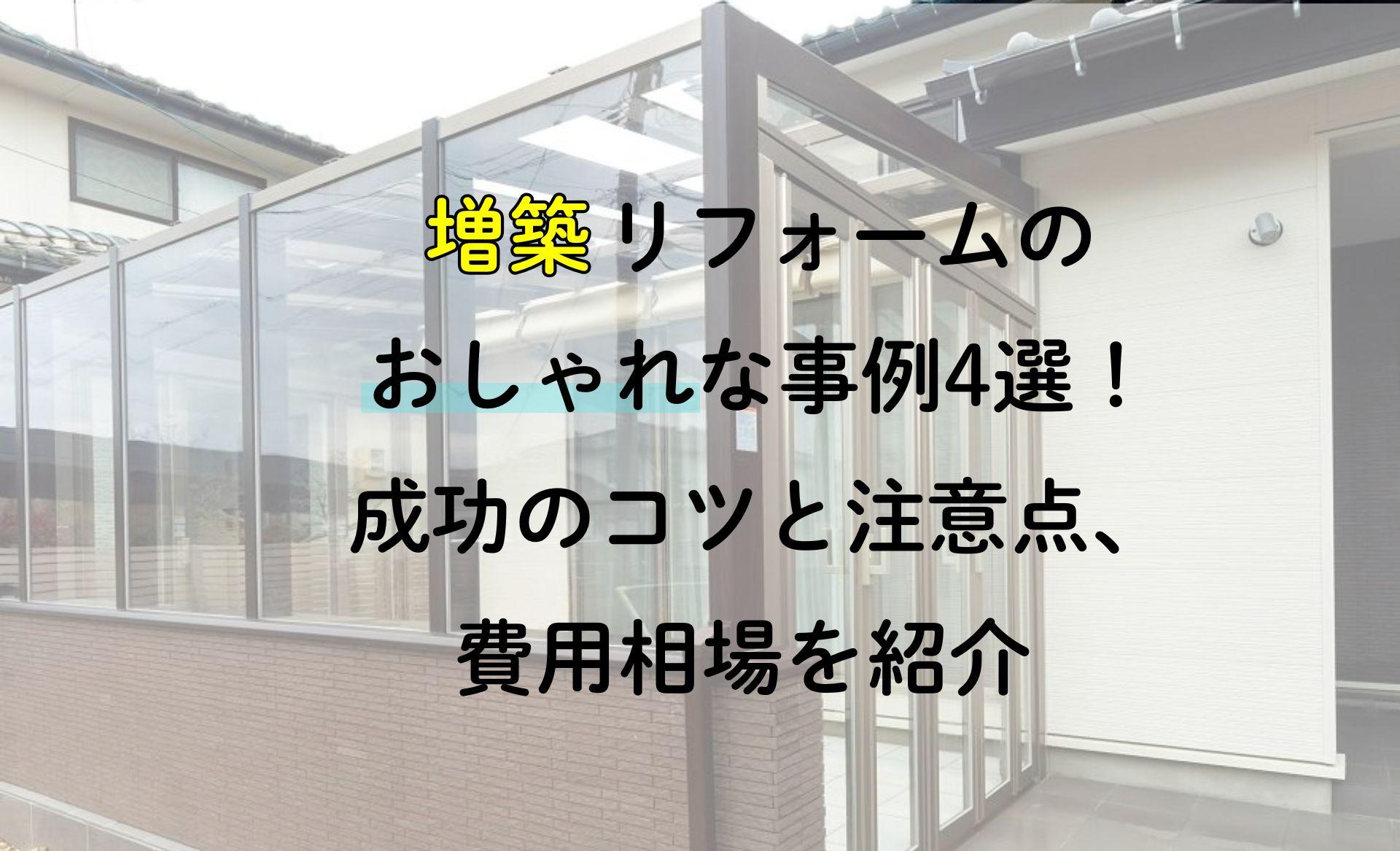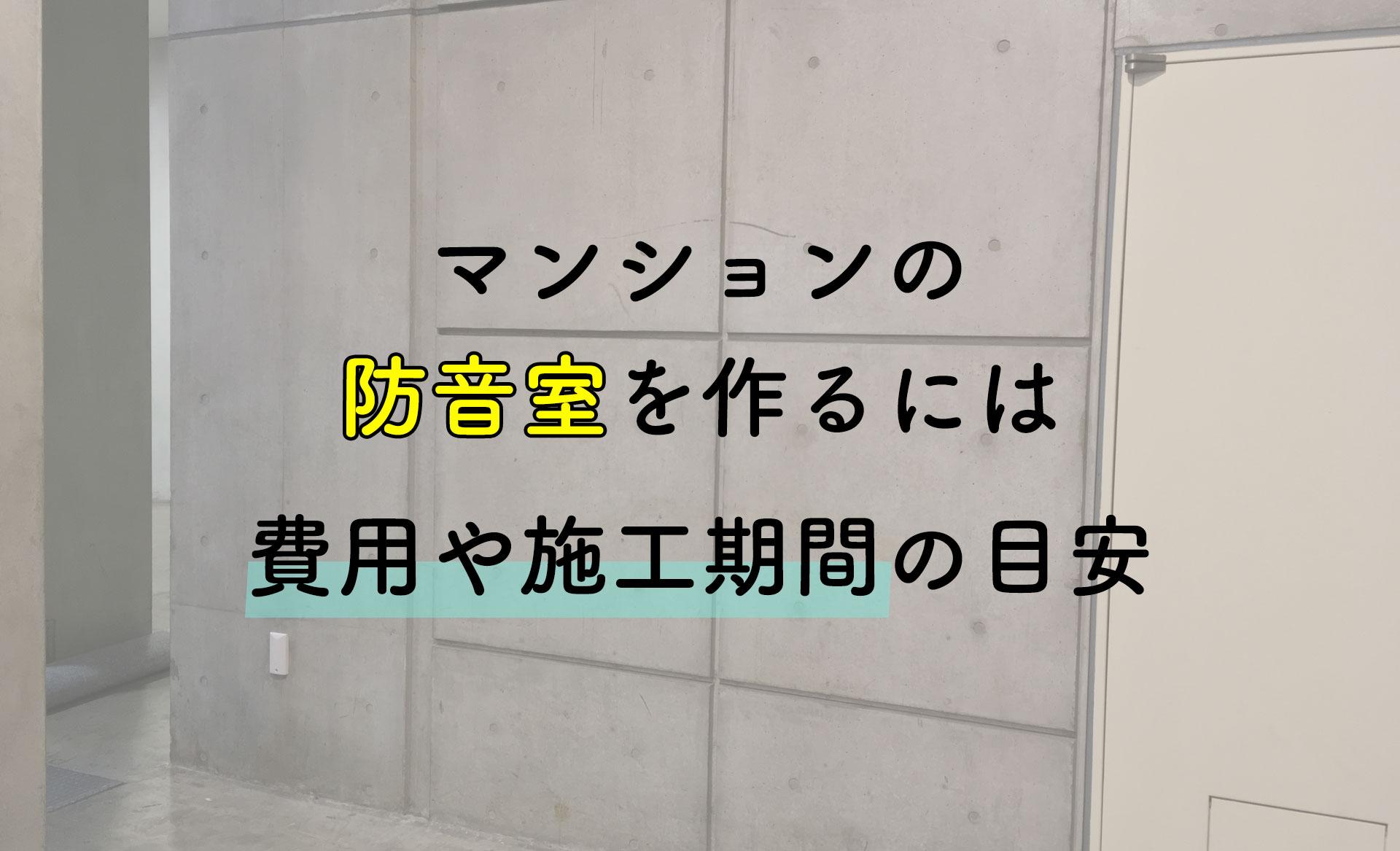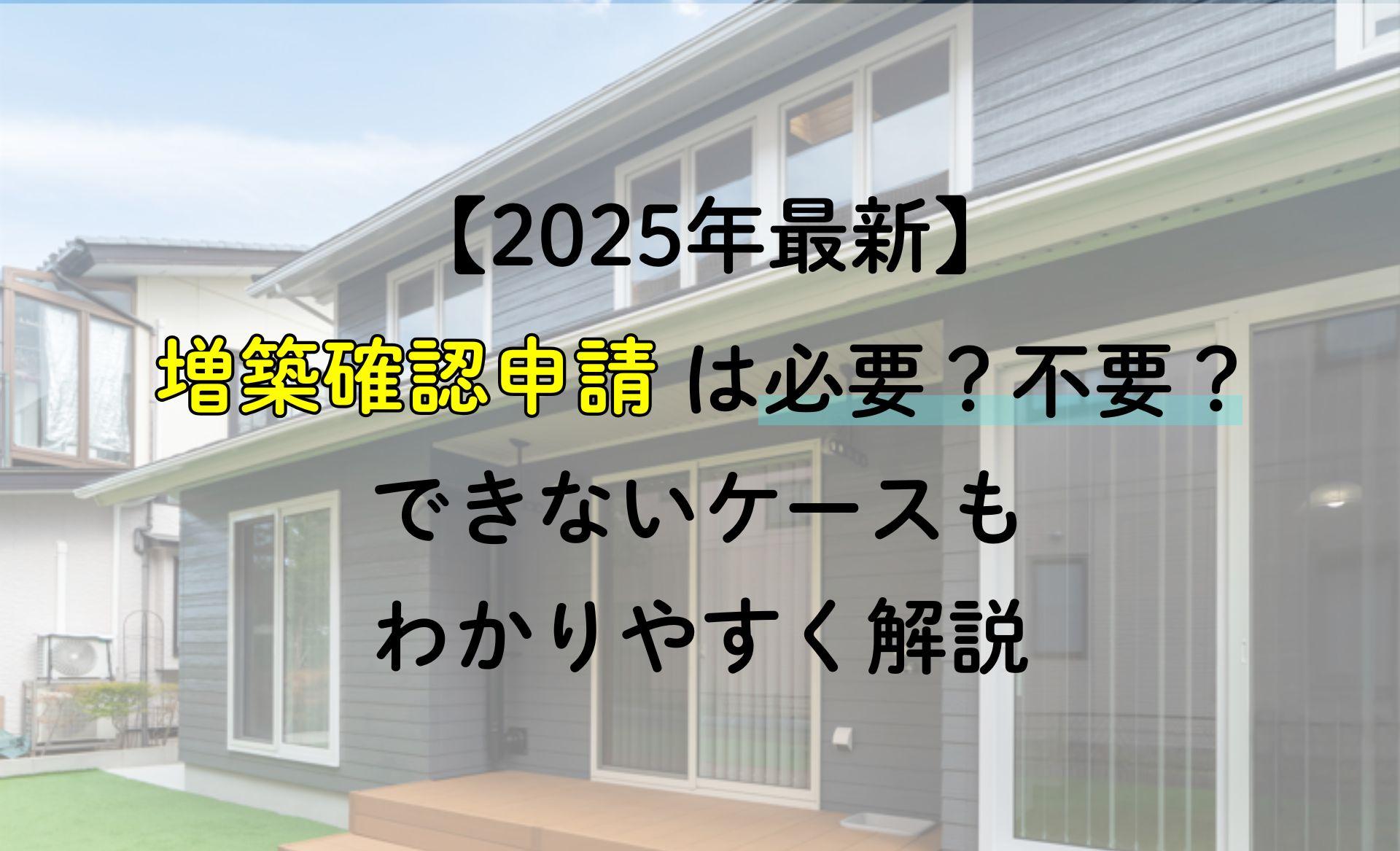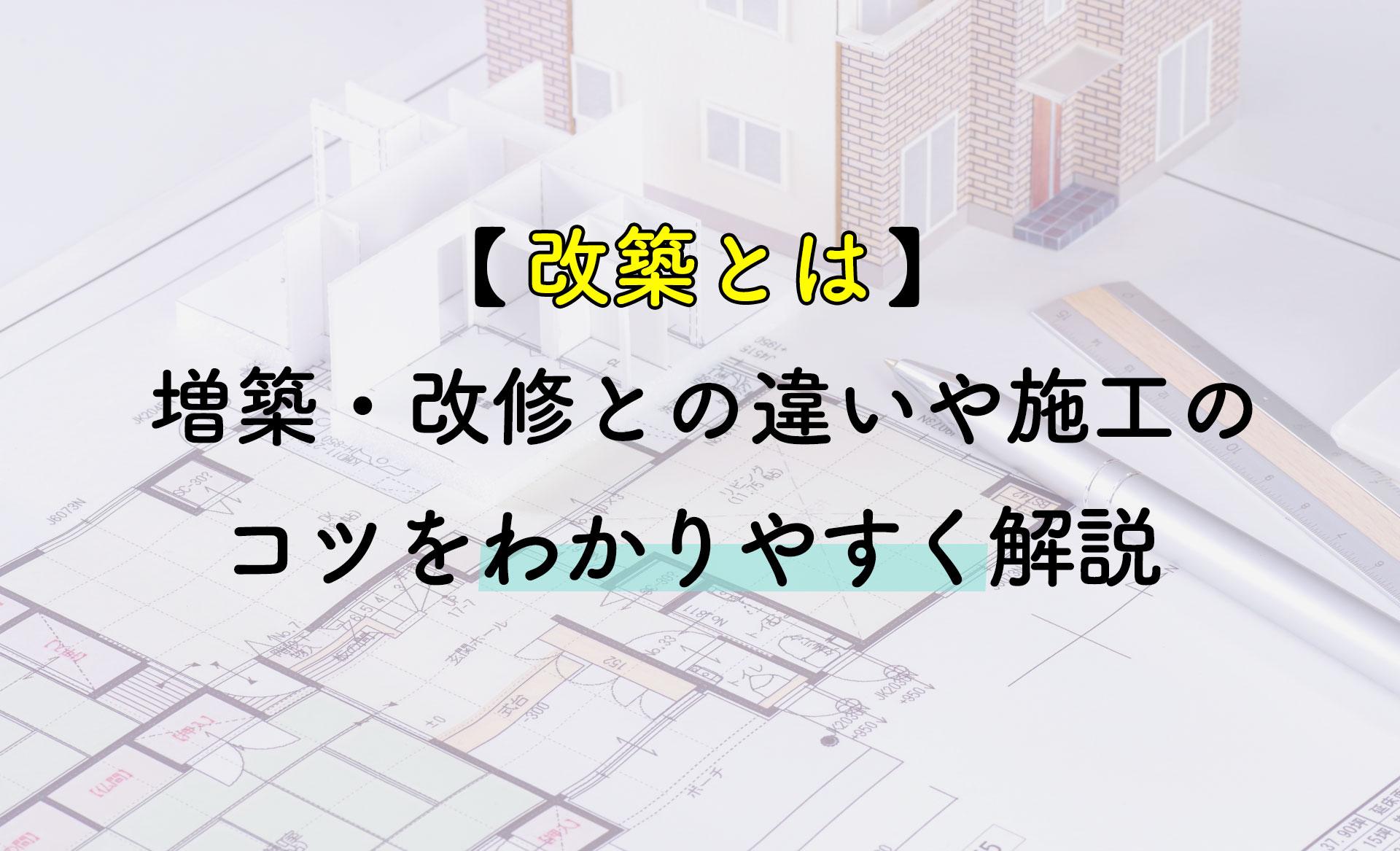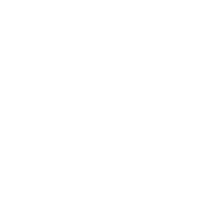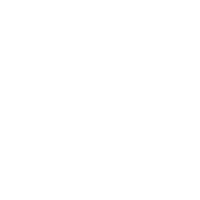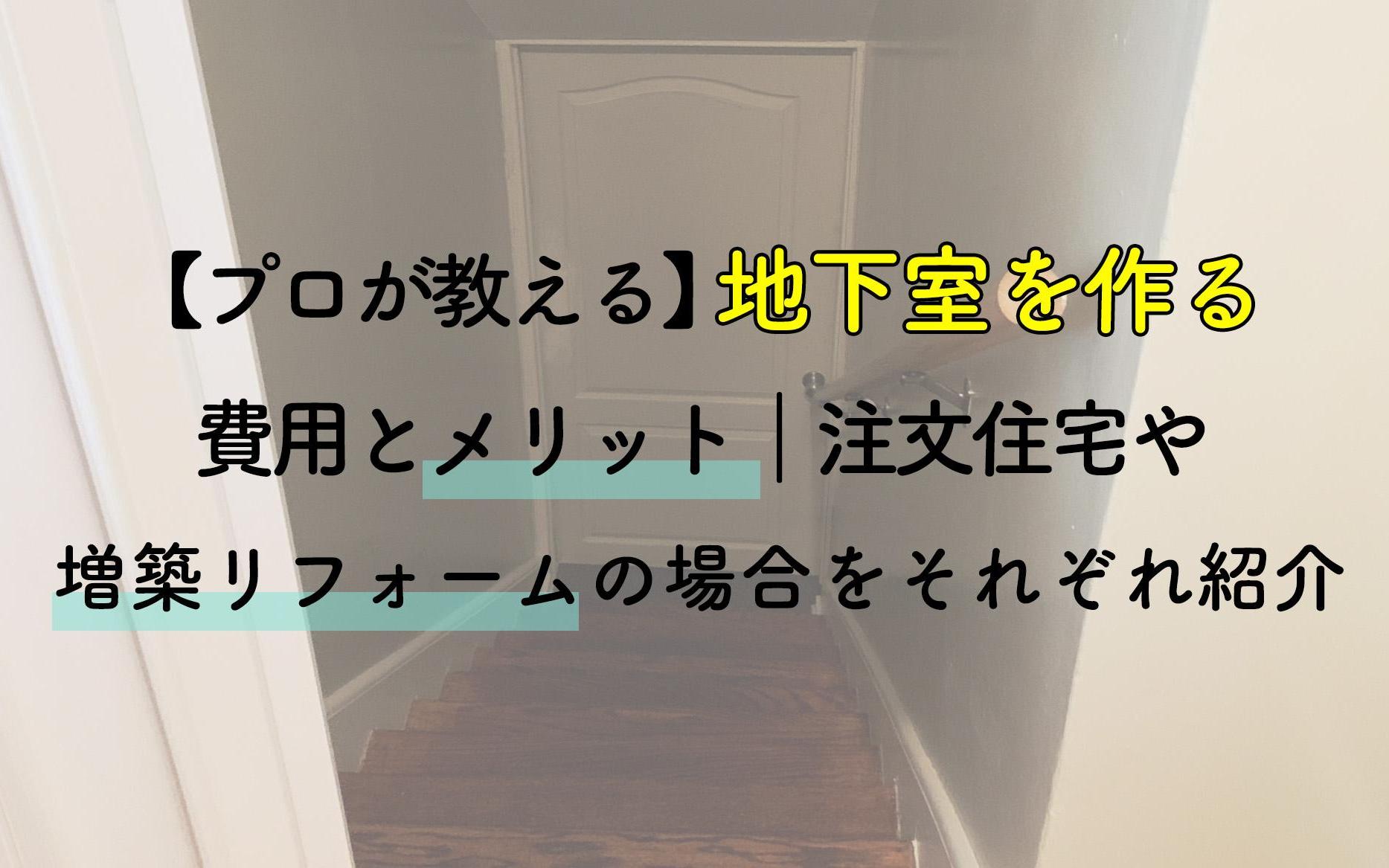
地下室のある家を建てたいけど分からない、失敗したくないという想いをお持ちではないでしょうか?私たち株式会社ユニテが30年間様々な経験から、地下室を建てる費用やメリット・デメリットをまとめてみました。
目次
まるで秘密基地のような特別感。
自分だけ、もしくは家族だけで思いっきり好きなことを楽しめるプライベートルーム。
そんな地下室に憧れたことはありませんか?
地下室はオシャレなだけの空間ではありません。
RC造で作られる地下室は頑丈で、さらには防音や断熱効果が高く、地上の部屋では実現が難しいプライベート感たっぷりの環境を作り上げられるメリットがあるのです。
既存の建屋との兼ね合いや構造面で地下室の建設が難しい場合もありますが、庭部分の利用や半地下室を選択することで希望が叶う場合もあります。
ただし、地下室を作りたい場合は、設計の早い段階で部屋を作る指針を決めなければいけません。
この記事では、注文住宅や増築リフォームで地下室を検討している方に向けて、地下室を建てられる条件や、失敗しないための対策について解説していきます。
坪単価などの基本的な建設費用も紹介していきますので、地下室が本当に必要かどうかも含めて、しっかり検討してみてください。
【戸建て】マイホームの地下室とは?

地下室を作りたい場合は、設計の早い段階で、部屋を作る指針を決めなければいけません。
地下室には地上の部屋とは違った特徴があるため、上手く活かすことで生活満足度が上がる素敵な住環境が実現できます。地下室は頑丈で気密性の高いRC造(鉄筋コンクリート製)で作られているため、地上の部屋と比べて次のような特徴があるのです。
- 音が響きにくい
- 振動が伝わりにくい
- 熱が伝わりにくい
地下室は、空気に触れている面積が小さいという特徴があるため、外部からの熱や振動が遮断されやすい傾向があります。まずは、「地下室はどのようなニーズがある人に役立つのか」を考えていきましょう。
【戸建てにおける地下室とは】
- 地下室の種類
- 地下室の活用方法
- 地下室の具体的な活用例
【全地下室と半地下室】地下室の種類
部屋の大部分を地中に埋める地下室の建設では、第一に安全性の確保、そして水や土などの侵入を防ぐ作りがとても大切です。地下室は、部屋の埋まっている度合いによって、3種類に分けられています。地下室の種類と特徴は以下の通りです。
| 地下室の種類 | 説明 |
| 全地下室 | 部屋の全てが地下に埋まっている地下室 ・断熱性・遮音性・室温安定性に優れているが、採光や風通しが悪い |
| 半地下室 | 部屋の一部が地上に出ている地下室 ・高低差のある敷地を有効活用できるため、コストが少なく明るさ確保や除湿がしやすい |
| ドライエリア付き地下室 | 地下室の周囲を空堀りして、外気と直接触れる部分を作っている地下室 ・採光や風通しが良く快適だが、ドライエリアを設置するのに費用がかかる ・地下室を居室として利用できる |
「全地下室」は、部屋の全てが地盤に埋まっている地下室で、断熱性・遮音性・室温安定性に優れている特徴があります。
「半地下室」は、部屋の一部が地上に出ている地下室で、傾斜や段差のある土地の形状を利用して作るケースが多いです。半地下室は完全な地下室と比べて、掘る土の量や土留めの程度が軽くなるため、割安な費用で施工にできるケースもあります。
一方、「ドライエリア付き地下室」は、周囲を深く空堀りして外気と直接触れる部分を作っている地下室のことです。
上記からもわかるように、完全に地中内に埋まっていない部屋も「地下室」と定義されるため、しっかり覚えておきましょう。
地下室の種類別の活用方法
地下室には大きく3つの種類があると前述しましたが、それぞれには更に細かい特徴があり、用途ごとにオススメの使い方が変わってきます。
地下室の種類別のおすすめ活用方法は以下の通りです。
| 窓の作りやすさ | 断熱・防音こうか | 建築コスト | オススメの用途 | |
| 全地下室 | △ | ◎ | やや高い | 倉庫、ワインセラー、音楽スタジオ など |
| 半地下室 | ○ | ○ | やや低い | 居室 など |
| ドライエリア付地下室 | ◎ | △〜○ | 高 | 居室 など |
全地下室は断熱性や防音性が高く、熱や音をシャットアウトしてくれますが、採光や風通しが悪いため居室向きではありません。
そのため、リビングや寝室などの「居室」を作る場合は、一定の大きさの窓を設置して、採光・通風の基準に適合させる必要があります。
居室目的で地下室を作りたいなら、窓や換気口が設置できる「半地下室」や「ドライエリア付地下室」が最適です。 窓の必要性や、断熱・防音性能がどの程度欲しいかなどを考え、用途に合った地下室のタイプを選びましょう。
ドライエリアの設置はよく考えて
ドライエリアとは、地下室の周りに作る空堀りのことです。ドライエリアを設置すれば、採光や換気がとてもしやすくなり窓が設置できるため、寝室や居室として大いに活用できます。
そんな地下室づくりの心強い味方になるドライエリアですが、実はメリットばかりではありません。ドライエリアを作るメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。
| メリット | デメリット | |
| ドライエリアの設置 | ・採光や換気のために窓を設けやすくなる ・外気との温度差が小さくなるため結露対策になる |
・工事費用が発生する ・防音性能が低くなる |
気を付けたいのが、ドライエリアの工事費用は決して安くはないことです。地下室周りを深く空堀りをするため、大量の土が掘り起こされます。土留めや土処理の増加分も含めると、ドライエリアの工事費はおおよそ200万円ほどになるでしょう。
また、地下室を覆う地盤が減るため、防音性能が低くなることにも注意が必要です。このようにドライエリアの設置はメリットばかりではないので、地下室の用途や必要性をよく検討してから施工することをおすすめします。
地下室の具体的な利用例
地下室のメリットを活かした、具体的な利用例は以下の通りです。
- ホームシアターや音楽スタジオといった大きな音を楽しむ趣味スペース
- 災害時のためのシェルター
- 温度変化の小ささを活かしたワイン貯蔵庫
- 省エネで快適に過ごせるリビング
- プライバシーが守られる寝室
- 収納力のある倉庫
このように、周りの目を気にせず、自分や家族の時間をマイペースに楽しむ際に地下室は効果を発揮します。
また、狭小住宅で広さとスペースを確保したい方にも、地下室は役立つ選択でしょう。
【注文住宅・増設リフォーム】地下室を作る費用相場と工期
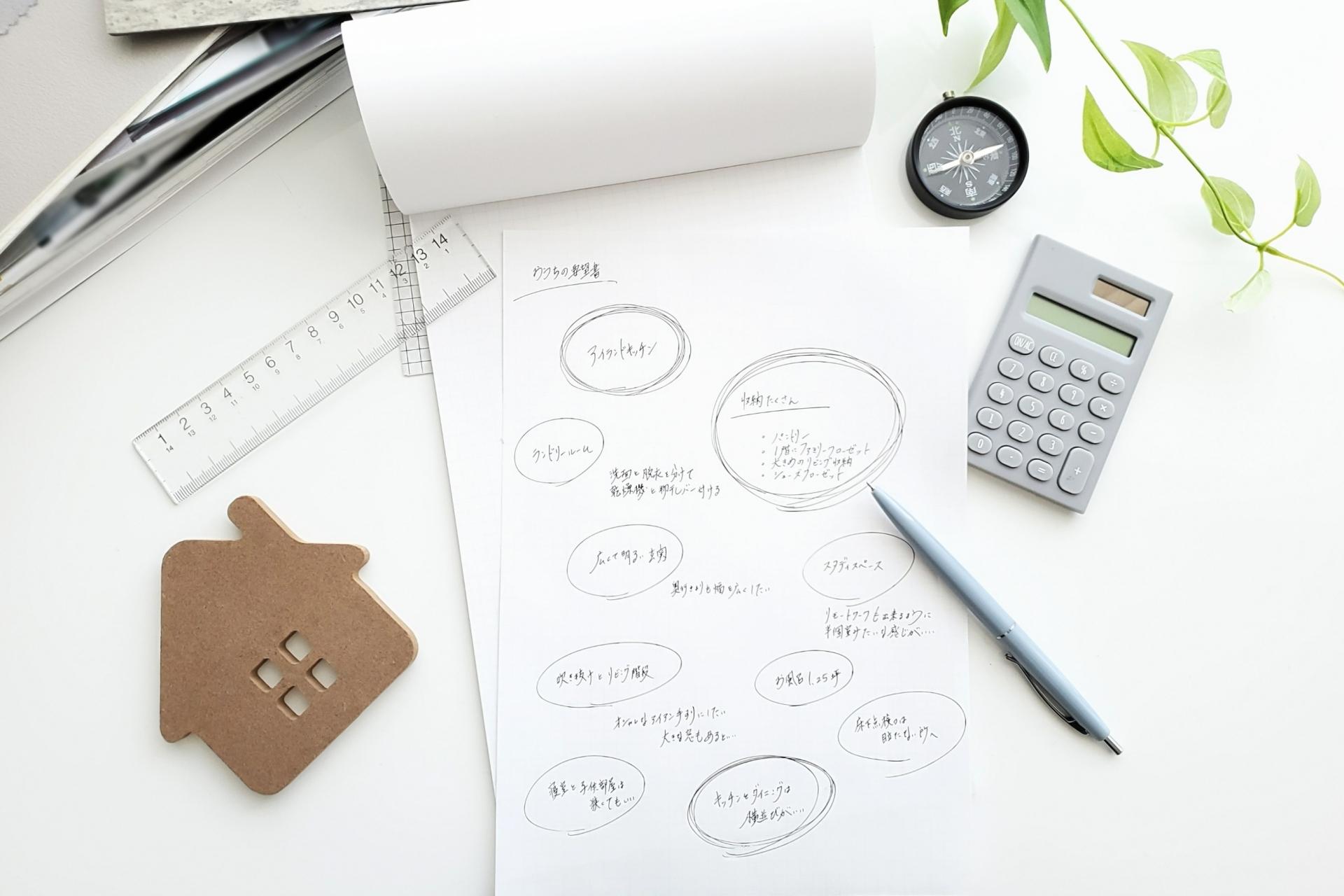
地下室を作ろうと思った時に、気になるのが施工費用です。ここからは、実際に地下室を作るための費用相場をケース別にみていきましょう。
【地下室を作る費用相場と工期】
- 注文住宅で地下室を新設するケース
- リフォームで地下室を増設するケース
全体の大まかな目安の他、部分ごとに分けた内容も紹介しますので、地下室の建設を考える際の参考にしてみてください。
なお、地下室の建設の費用が高くなりがちなケースは次のようなものが挙げられます。
- 地下室を居室(生活スペース)として使いたい
- 地下室の規模が大きい
- 既存建物の移築や建て替えが必要になる
- 地盤が弱いため改良が必要になる
また、地下室を作る際の工期は、通常の施工に比べて1.5〜2か月ほど長くなる傾向があります。掘った土壁が崩れないよう慎重に工事を進めなければならず、RC造のコンクリートを十分に乾燥させる時間も必要になるためです。
特殊な施工や近隣への配慮が特に必要なため、地下室の建設の工事は時間をかけて慎重に進めることになります。工期には十分な余裕を持っておきましょう。
注文住宅|地下室を新設する場合の費用

地下室を作る費用は、地上で同じ面積の建造物を作る場合と比べて、2倍以上の費用が掛かると言われています。地下室建設にかかる費用の大まかな目は以下の通りです。
- 1坪あたり50~200万円
- 10畳(約5.5坪)の居室用の地下室を作るケースだと約1,200万円〜
一般的に、地下室を作る施工額の相場は、総額で600〜1,000万円ほどかかります。もちろん施工内容や使う建材、地質や土地の天候などによっても工事費は変動するので、一概には言えません。
しかし、地下室は地盤調査や建屋基礎の補強が必要になるため、地上の部屋を作る費用よりはどうしても高額になってしまうでしょう。
とくに、地下室を居室として使う場合は、建築基準法で定められている採光や換気の要件を満たす必要があります。その対策のために追加料金が発生する場合もあるため、注意が必要です。
リフォーム|地下室を増設する場合の費用
リノベーションなどで地下室を増設する場合は、広さや設置場所などによっても左右されますが、おおよそ1坪あたり80〜130万円が相場になります。
トータルだと600〜1,000万円程度必要になりますが、既存の建物の建て替えや移築が発生するケースでは、相場以上の金額が発生する可能性もあるため注意が必要です。
地下室を作りたい!具体的な費用の内訳
地下室は地上の建物の施工と比べて、地盤調査や頑強な基礎施工が必要になる工事です。では、一体どのような項目に費用がかかるのでしょうか。以下はトータルでかかる地下室費用の一覧です。
| 項目 | 費用相場 | 内容 | |
| 調査 | ボーリング調査 | 25~30万円 | 地盤の状態を正確に把握するための調査。 |
| 設計 | 構造計算費用 | 地下部分30~45万円 地上階20~30万円 |
一般的な木造住宅とは異なり、簡略化されていない構造計算が必要。 |
| 鉄筋コンクリート設計 | 30~80万円 | RC造は変更が容易に行えないため、綿密かつ詳細な実施設計図が必須。 | |
| 堀削、運搬 | 土留 | 150~200万円 | 掘削工事を進める上で、周囲の地盤を崩れないように守り、安全に完成させるために必要。 |
| 土の運搬 | 200万円 | 掘削した残土を搬出先まで運搬し、処分するための費用。 | |
| その他 | 地盤改良 | 100~300万円 | 調査の結果、地盤を固くしたり補強したりする必要がある場合に発生。 |
| 浸水対策 | 外壁防水 | 90~180万円 | 地下水や地盤からの浸水を防ぐために施す、外壁の防水処理。 |
| 排水ポンプ | 70~110万円 | 雨水や結露水などを汲みだすために必要。 | |
| 止水板 | 30~60万円 | 入口からの浸水を防ぐ目的で設置。 | |
| 結露対策 | 壁・床の除湿素材 | 10~60万円 | 左官材料や調湿性能のあるタイルなどの素材を使った場合に発生。 |
| 除湿・自動排水システム | 45万円 | 除湿器と除湿水の自動排出設備を設置した場合に発生。 | |
| 熱交換器 | 15~25万円 | 気温差を防いで結露を抑えるために使用。 | |
| 換気対策 | 換気システム | 5~10万円 | 空気の循環を促すために設置。 |
| 追加対策 | ドライエリア | 150万円 | 採光や換気、排水を効率的に行うための空堀り。窓の設置が難しい場合の対策。 |
実際にはこの内容を全ておこなうわけではありませんが、地盤や周囲の状況、目指す完成形によっては様々な工事が発生します。安全面の確保と快適な住空間の実現に必須である工事を削ることは難しいでしょう。
どのような地下室を作りたいのか、資金とのバランスを考えながら検討することが大切です。ここからは、地下室費用の中でも特に大切な費用について簡単に紹介していきます。
ボーリング調査費用
「ボーリング調査」とは、穴を掘って地盤の強度や地下水の位置、地層の境界の深さなどを調べる土壌調査のことです。
マンションの建築など、大きい建築物を施工する際におこなわれる調査ですが、地下室を設置する際にも必要になります。事前に液状化のリスクなどがないかチェックするためです。
ボーリング調査には20〜30万円程度の費用がかかります。
構造計算費用
「構造計算」は、地下室の設計のために必要な計算書です。一般的には木造三階建てなどの複雑な構造の時に採用されますが、地下室の設置時にも必要になります。
地下室を設置する場合は、土圧や水圧に耐えうる構造にするため、細部まで詳細に検討しなければなりません。構造計算をおこなうと、100ぺージ以上の計算書を作製することになります。
構造計算にかかる費用は、鉄筋コンクリート造の地下室部分に30〜45万円、地上の木造部分に20〜30万円ほどが相場です。トータルすると50〜70万円ほどのコストが必要になるでしょう。
専門家でないと理解できないような難解かつ膨大な情報量なので、それなりのコストがかかってしまうのです。
鉄筋コンクリート部の設計費用
施工箇所が木造の地上階だけである場合は、工事が開始した後でも電気や配管の移動は可能です。設計図は標準化されていることが多く、費用もそこまでかからない傾向があります。
しかし、鉄筋コンクリートである地下室は、1度工事に着手してしまうと原則やり直しがききません。そのため、やり直しが発生しないよう綿密に設計図を作製しなければならないのです。
鉄筋コンクリート部分の設計費用は、30〜80万円ほどが相場になります。
山留工事費用と残土処分費用
「山留」は、土を掘る際に周囲の地盤が崩れないよう、6mほどの太い鉄骨を地面に打ち込む工程のことです。この山留工事費用には、おおよそ200万円程度のコストがかかります。
また、地下室を作るために掘った土を捨てるための費用が「残土処分費用」です。この費用も最低200万円ほど必要になるため、あわせて用意しておく必要があります。
地盤改良工事費用
「地盤改良工事」は、ボーリング調査の結果から地盤改良が必要になった場合にかかる追加の工事費用です。地盤を固めるために固化剤を入れたり、コンクリート杭を作って地盤を支えたりします。
係る費用は、工事の内容や掘る深さによって変動する傾向がありますが、平均相場は100万円〜300万円程度です。
防水工事費用や室内環境対策費用
コンクリートは水がしみ込みやすいため、アスファルトやウレタンでコーティングする防水工事をおこなう必要があります。防水工事には80万円ほどのコストが必要です。
この工事の質が悪いと結露やカビ、最悪の場合浸水などを引き起こしてしまうため、しっかり対策しなければなりません。
また、地下室の室内環境を向上させるため、断熱工事や除湿器・熱交換器の設置も必要になります。断熱工事に35万円程度、自動排水システムや除湿器設置などに45万円程度かかるのが相場です。
ドライエリア用工事費用
ドライエリア付地下室を作る場合は、ドライエリアの設置費用も加算されます。サッシの設置や雨水対策用の設備も必要になるため、おおよそ150万円ほどの費用がかかるでしょう。そのため、ドライエリアの有無は地下室の用途によって検討するのがおすすめです。
マイホームに地下室を作るメリットとは?

ここからは、実際に戸建てに地下室を作るとどのようなメリット・デメリットがあるのか詳しく解説していきます。
【戸建てに地下室を作るメリットとデメリット比較】
| 地下室を作るメリット | 地下室を作るデメリット |
| 音に関するトラブルを減らせる 住まいの防災性能を上げられる 季節に左右されずに省エネ&快適 狭小住宅に部屋を増やせる |
建築コストが高い 結露しやすい |
地下室をうまく活用して生まれる暮らしのメリットは、以下の通りです。
地下室の設置にはさまざまなメリットがありますが、地下室の設置は難易度が高い工事になるため、通常の工事よりも工程が増えコストがかさむ傾向です。また、換気しづらく湿度が高くなりやすいことから結露しやすいというメンテナンス面の問題点もあります。
まずはメリットから詳しく見ていきましょう。
メリット①:音に関するトラブルを減らせる

地下室は地上にある部屋よりも音が響きにくい構造のため、室内で大きな音を出しても外部へ伝わりづらくなります。逆に、外部からの音も室内へと伝わりにくい傾向です。
この特徴を活かせば、以下のような「音に対してのストレスが減る空間」を作れます。
- 音楽や映画など、大きな音を出す趣味を自宅で楽しめる
- 生活音や子どもの声などで、近所へ配慮する必要がなくなる
- 外部の音を気にせずぐっすり眠れる・静かに過ごせる
- 生活時間帯の異なる同居家族に気を遣わずに生活ができる
今まで生活音に関するトラブルで悩んでいた方には、特に魅力的なメリットとなるかもしれませんね。
メリット②:住まいの防災性能を上げられる
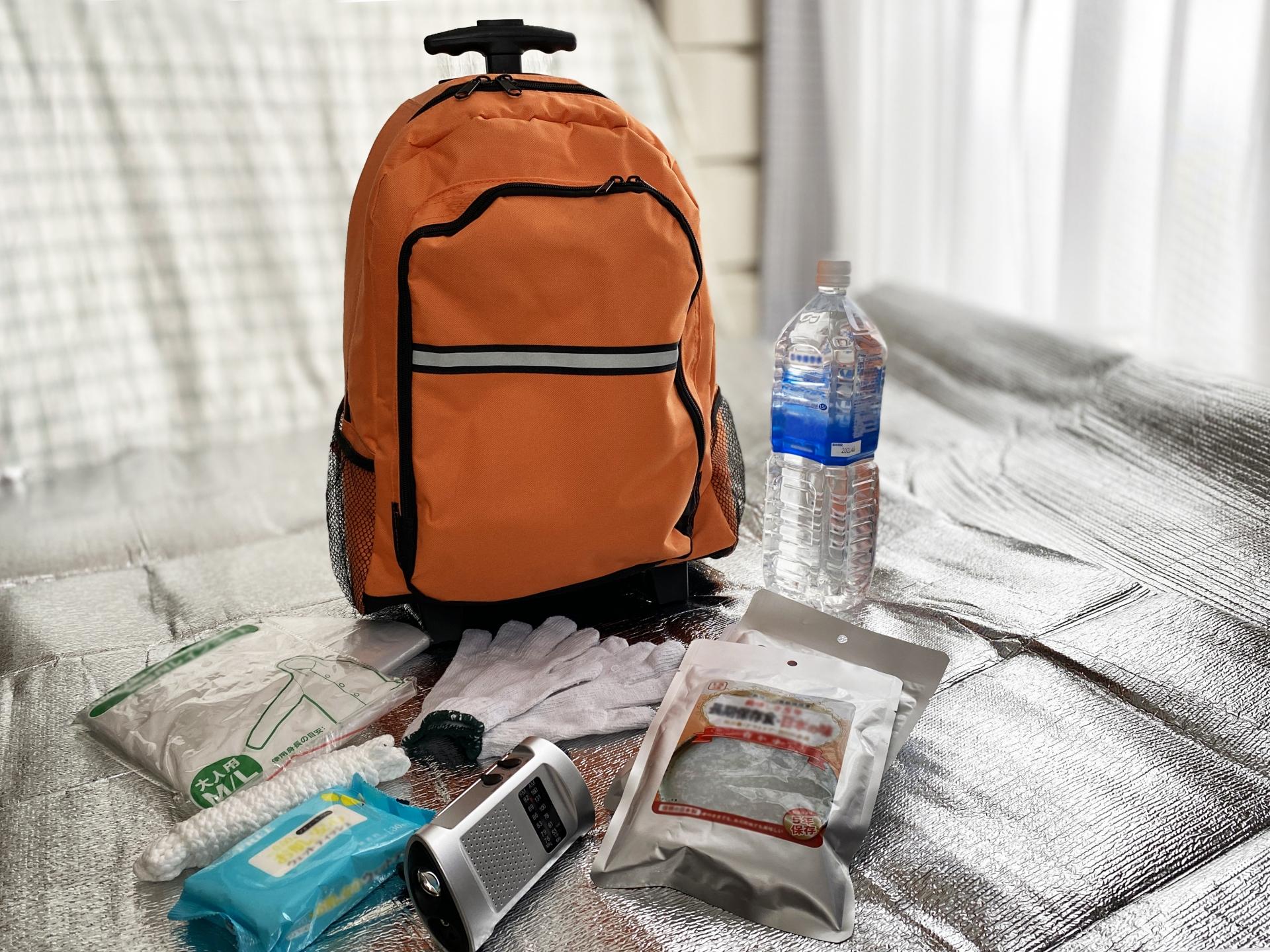
地下室のある家は地震に強いといわれていますが、その理由は、主に以下の2つです。
- 地震の揺れの最中は、地下室も地表・地盤と一体となって動くため、内部に伝わる揺れが小さくなる。
- 地下室自体が建屋の頑丈な基礎となるため、地上階を支える力が大きくなる。
地下室がある一戸建ては、その分基礎を深い部分から打っていることになるので、地震の揺れに強くなります。木造2階建てで比較したケースでは、地下室ありの住宅は地下室なしの住宅よりも揺れが40%カットされているのです。
つまり、戸建てに地下室を作ることにより、地下部分を防災シェルターとして使えるだけでなく、建屋の地上部分を強固に支える役割も期待できます。
住まいの防災機能を強化する目的で、地下室の建設を考えるのも1つの選択です。
メリット③:季節に左右されずに省エネ&快適に過ごせる

地中は地表に比べて温度の変化が少なく、年間を通して10~20℃の範囲内で安定することが多いです。
地中にある地下室もその影響を受けて、年間を通じて温度変化が小さくなります。
つまり、エアコンを使わなくても、夏は涼しく冬は暖かいと感じる快適な住環境となるわけです。省エネ対策にもなりますし、エアコンの温度変化が苦手な方も快適に過ごせますね。
メリット④:狭小住宅に部屋を増やせる

狭小住宅に地下室を設置することにより、容積率の緩和が期待できます。つまり「地上階の階数が増やせない建物でも地下室なら作れる場合がある」というメリットがあるのです。
容積率とは、建築基準法で決められている場所や建物のタイプによる大きさの制限のことを指します。この土地にはこの大きさの建物までしか建ててはいけないという上限が、法律によって決められているのです。
狭小住宅の建設で頭を悩ませるのが、容積率に関する問題です。狭い土地での建屋で広さを確保したい場合、階数を多くすることで対策しようとしますが、容積率の問題で階数を増やすには限界があります。
ただし、地下室付き住宅は要件を満たせば容積率が緩和されるメリットがあるのです。具体的に言うと「住宅の地下室は建物の床面積の3分の1までの広さであれば、容積率に参入しなくてよい」とされています。
例えば、2階建ての建物を建てる際、容積率の都合で3階建てにすることはできなくても、地下室付きにすることはできる可能性があります。 土地を最大限に活用して居住スペースをゆったりと取りたい場合は、地下室は便利な選択となるでしょう。
戸建てに地下室を作るデメリット
戸建てに地下室を作る際には、以下のデメリットに注意する必要があります。
【地下室を作るデメリット】
- 建築コストが高い
- 結露しやすい
「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、しっかり把握した上で地下室の設置を検討してください。
デメリット①:建築コストが高い
最も大きなデメリットは、地下室の建築コストが高いことでしょう。地上のみの戸建てと地下室付きの戸建てでは、圧倒的に地下室付きの方が費用がかかるといわれています。
しかし、コストを抑えるためにコンクリートの質や基礎部分などのグレードを下げてしまうと、戸建ての堅牢性が失われる可能性が高く危険です。
詳しくは後述しますが、地下の設計や建築には通常の戸建て以上に技術が必要になるため、依頼する業者にも十分注意しましょう。コストが安いからと実績の少ない業者を選んでしまうと、莫大な損害や建築遅延が発生する可能性があります。
デメリット②:結露しやすい
地下室は湿気が溜まりやすく、特に湿度の高い夏場は結露しやすくなるデメリットがあります。梅雨の時期は80〜90%を超えてしまうため、湿度に弱い革製品や木造家具、精密機械を置く場合は十分注意しましょう。
水分に強い特殊加工や断熱処理を施したコンクリートを採用したり、乾燥材や除湿器を複数設置したりなど、徹底した対策をおこなってください。
【地下室の必要条件】作れるケースと作れないケース

特徴をうまく活用することで暮らしを豊かにしてくれる地下室ですが、実はどんな住宅でも地下室を作れるわけではありません。
ここからは、地下室を建てるためにクリアしなければいけない条件について、詳しく解説をしていきます。
【地下室の必要条件】
- リフォームやリノベーションで増設するケース
- 新築で作るケース
- 地下室が作れないケース
上記3つのケースを紹介していきますので、必要条件についてもしっかり把握しておきましょう。
地下室の必要条件①リフォームやリノベーションで増設するケース

まず、リフォーム・リノベーションによって、既存の建物に追加する形で地下室を作りたい場合についてみていきましょう。地下室を作るためにクリアしなければいけない条件が、大きく分けて次の2つです。
- 地盤の状態が工事可能であるか
- 既存の建物の状態が工事可能であるか
まず押さえておきたいのが、既存の建物に地下室だけを追加して建てるケースは、実現の難易度が少し高めになるということです。
既存の建物を活かしながらの施工は、全てをゼロから始める新築よりも難しい工事になる場合があります。
- 建築基準法の制限によって確認申請の難易度が上がる
- 地盤や住宅の状態などによっては、施工できる内容が制限される
- 高度な作業が必要になるので、施工できる業者が限られる
当然ながら地下室は地中に作る必要があり、建物の基礎部分に手を加えなければなりません。
既存の建物に地下室を作る場合、以下の作業が追加で発生します。
【既存の建物に地下室を作る場合に発生する作業】
- 設置する箇所にある基礎部分の一部を壊す
- 建物全体をリフトアップする
上記は技術的にも難しい施工であるため、住宅の構造や地盤の状態によっては施工できないケースも多いです。また、建築基準法の制限なども考慮した上で施工しなければならないでしょう。
さらに地盤や既存建物の状態が原因で、工事の安全性や建物の強度などが担保できない場合には、残念ながら地下室を作ることはきません。
ただし、既存建物への増築が不可能な場合でも、庭などの建物が建っていないスペースを使って地下室を作れるケースもあります。事前に業者と相談し、施工ができるか現地調査をしてもらいましょう。
地下室の必要条件②新築で作るケース

次に、新築で地下室のある家を作る場合をみていきましょう。
新築の場合も、地盤や周辺環境の状態次第では施工ができないケースも発生します。例えば、以下のような場合は地下室を作ることが難しいです。
他にも、地盤が特殊な場合や周辺環境による制限で、ハウスメーカーから地下室の建設をオススメされないケースもあります。事前に十分な相談を行い、建設プランを練ることが大切です。
地下室が作れないケース
土地の条件が厳しければ、地下室が作れない場合もあります。主に以下の3つのケースのうちのどれかに該当する場合は、設置は難しいでしょう。
【地下室が作れないケース】
- 地盤が柔らかい
- 水害の危険性がある
- 土地のすぐ下に水脈がある
- 地下に障害物や建造物(トンネル等)がある
- 土地に道路の制限がかかっている(計画道路など)
場合によっては地下室にこだわらず、地上の部屋で代用ができないかを考えてみるのも賢い選択です。例えば、自宅シアタールームが欲しいケースなら、既存の部屋の防音性能を上げることで希望が叶うかもしれません。
なぜ地下室が欲しいと思ったのかをもう一度振り返り、近い機能を実現できる方法がないかを業者に相談してみると良いでしょう。
【注意点と対策】地下室のある家を作る際のポイント

実は、地下室はその特性上、気を付けなければ暮らしのデメリットになってしまう点もあります。事前に地下室の特性を理解して、しっかりと対策をすることが大切です。
住みよい地下室を作るために注意が必要なことと、その対策方法についてご紹介します。
- 地盤調査を怠らない
- 採光量を確保する
- 湿気・カビ・結露に注意する
- 施工業者選びにこだわる
それぞれ見ていきましょう。
地盤調査を怠らない
地下室を作る際は、地下を掘れるだけの強固な地盤が必要不可欠です。最終的な費用や施工期間にもかかわる問題なので、必ず地盤調査をおこないましょう。
軟弱な地盤のまま施工開始してしまうと、地盤改良の費用が跳ねあがってしまったり、最悪地下室を作れなかったりします。
また、床下浸水や冠水などの可能性のある土地、地盤沈下の可能性がある土地においては、地下室を作ることはできません。地下室施工の有無を確認する意味でも、事前にしっかり地盤調査をしておきましょう。
採光量を確保する

地下室は構造上、窓が作りづらい難点があります。照明器具で明かりを確保すれば問題がないように感じますが、実は窓がないことで法律上の問題で問題が出てくることも。
それは、地下室を居室(生活スペース)として使用する場合です。居室を建築する際は、一定基準の採光を確保する必要があり、要件を満たさないと建築確認申請が通りません。
採光量の確保のために考えられる対策としては、以下のようなものがあります。
- 天窓を開ける
- 地下室の一部を地上に出し、半地下室にする
- ドライエリア(空堀り)を設ける
地上と地下室天井をつなげる天窓は、イメージがしやすいですね。
その他、半地下室やドライエリア付きの地下室にすることで、地下室の一部が外気と接し、窓を作るスペースをうまく作ることができます。
地下室を居室として使いたい方は特に、採光対策をしっかりと行いましょう。
湿気・カビ・結露に注意する

地下室の特性に、断熱性の高さが挙げられます。
この特性は夏は涼しくて冬は暖かい、過ごしやすい環境を作ってくれるという点ではメリットです。
しかし、気を付けたいのが結露の発生。外気と室内の温度差が結露を生み、湿気やカビの原因となってしまいます。結露の主な対策としては、以下の通りです。
快適な地下室ライフを送るために、これらの対策をしっかりと行いましょう。
施工業者選びにこだわる
実際に地下室つきの家を施工する際の、業者選びのポイントを紹介します。
- 地下室の施工経験がある
- 土地購入から施工までをワンストップで行える
- 相談しやすくアフターフォローも万全な体制
地下室が建設できる条件には、地盤や周辺環境の状態が大きく影響することを前述しました。
そのため、早い段階での地盤調査と設計への反映が大切です。
当社では土地選定から施工までをワンストップでおこない、最適な建設プランを提案できる体制が整っています。
お客様の悩みに寄り添い、よりよい住まいづくりを目指していくことが私たちの喜びです。どうぞお気軽にご相談ください。
地下室に関するよくある質問にユニテが答えます
最後に、地下室の新設・増設に関するよくある質問に、リフォーム・リノベーション業に約30年間携わってきたユニテがお答えしていきます。
【地下室に関するよくある質問】
- 地下室は自分でDIYできる?
- 自宅に地下室を設置した失敗談は?
上記のような疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
地下室は自分でDIYできる?
地下室のDIYは大変危険なのでやめましょう。コスト削減を優先する方の中には、DIYで地下室を作ることを検討することもあるかと思います。しかし地下室を作るためには、高度な技術や綿密な設計、専門知識が必須です。
安全面からの観点からも、通常のリフォーム・リノベーションよりも難易度が高い地下室の施工は素人には難しいでしょう。施工はプロに任せるのが一番です。
自宅に地下室を設置した失敗談は?
自宅に地下室を設置した人が後悔しがちなポイントは以下の通りです。
【自宅に地下室を設置した失敗談】
- 作ったときは問題なかったが、梅雨時期に結露が発生してしまった
- 集中豪雨による浸水で、家具や壁紙など部屋がダメになってしまった
- 地下室を作ったはいいものの、使い勝手が悪く結局物置になっている
地下室を作る際は、季節や天候による湿度の変動も考慮した上で、適切な湿気対策・換気対策をすることが大切です。また、万が一のことを考えて排水ポンプを設置したり、道路などの侵入経路を絶つためのステップを設置したりする工夫も必要になります。
さらに、明確な使用目的がないまま地下室を作ってしまい、使わなくなってしまったという声も多いです。たとえば、収納スペースを増やすのが目的であれば、地下室である必要はないかもしれません。
本当に地下室が必要かどうかよく検討し、明確な使用目的を持って施工しましょう。
まとめ
この記事では地下室の建設とその費用について解説しました。ポイントをまとめると以下のとおりです。
- 地下室は防音性や断熱性、耐震性の高さなどが特徴。地上の建物とは違った活用の仕方ができる。
- 狭小住宅の土地活用にも地下室は有効。
- 地下室を建てられるかどうかは、既存の建物や地盤、周辺環境の状態が大きく影響する。施工の判断には現地調査が必須。
- 地上の建物の建設と比べて、地下室建設の費用は高め。工期も長めにかかる。
- デメリット対策、地下室建設のポイント3つを参考に、後悔のない建築プランづくりをすることが大切。
オシャレで機能的な地下室の建築に憧れる人も多いでしょう。
地下室をうまく活用すれば、生活を豊かにして、自分と家族の時間を思いきり楽しめる空間が作れます。
地下室の建設を実現するには、求める完成形と資金計画とのバランスが大切です。
決して安くない買い物となる分、叶えたいポイントを明確にして建設プランづくりに反映させましょう。