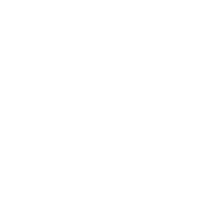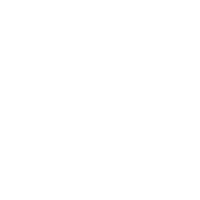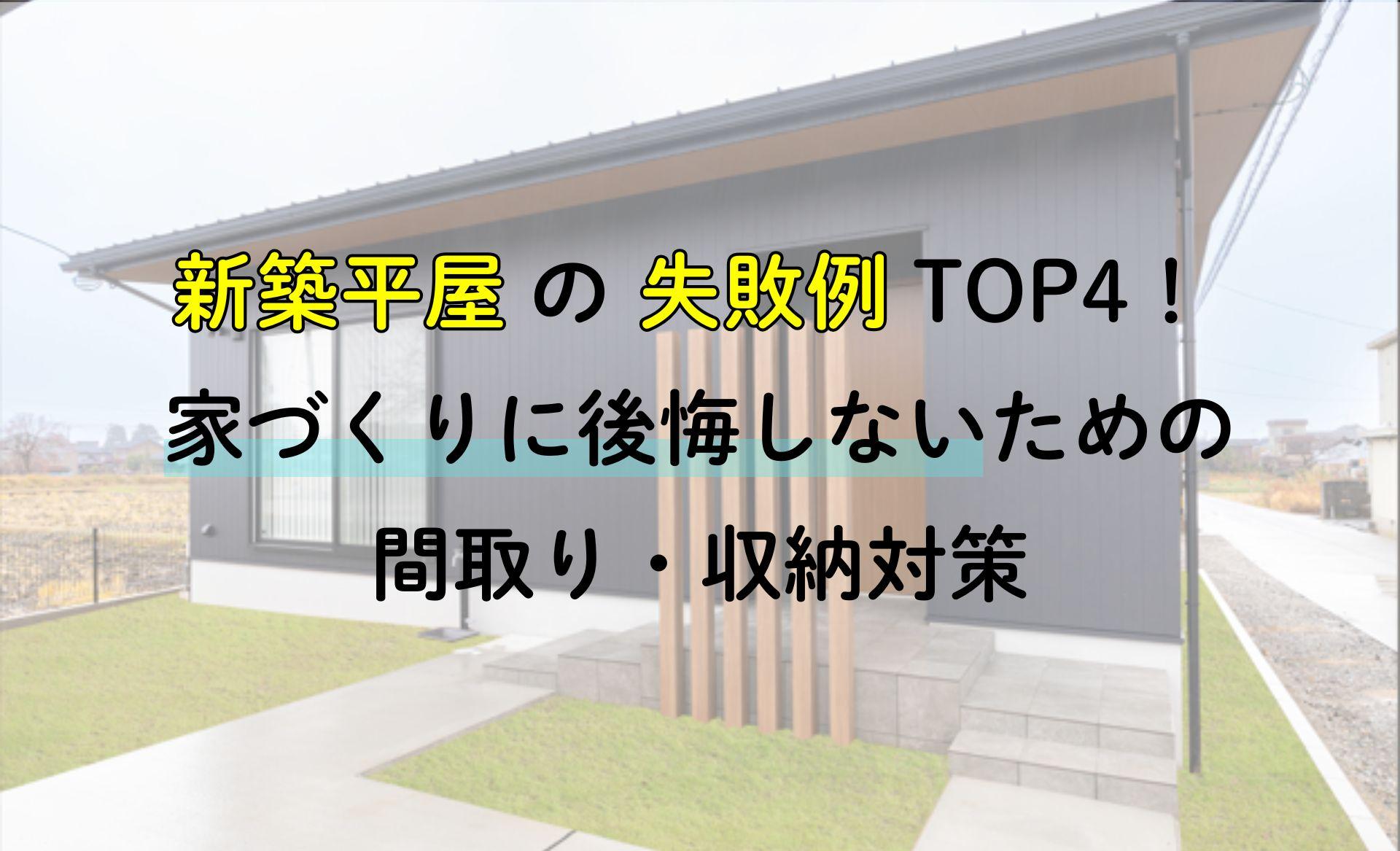
新築平屋の失敗で特に多い理由4つをご紹介!専門家の視点から、平屋ならではのメリット・デメリットを踏まえた対処法を解説します。各失敗を防ぐために、事前にできることを詳しくご紹介しますので、新築で平屋を建てたいと思っている方は必見です。
目次
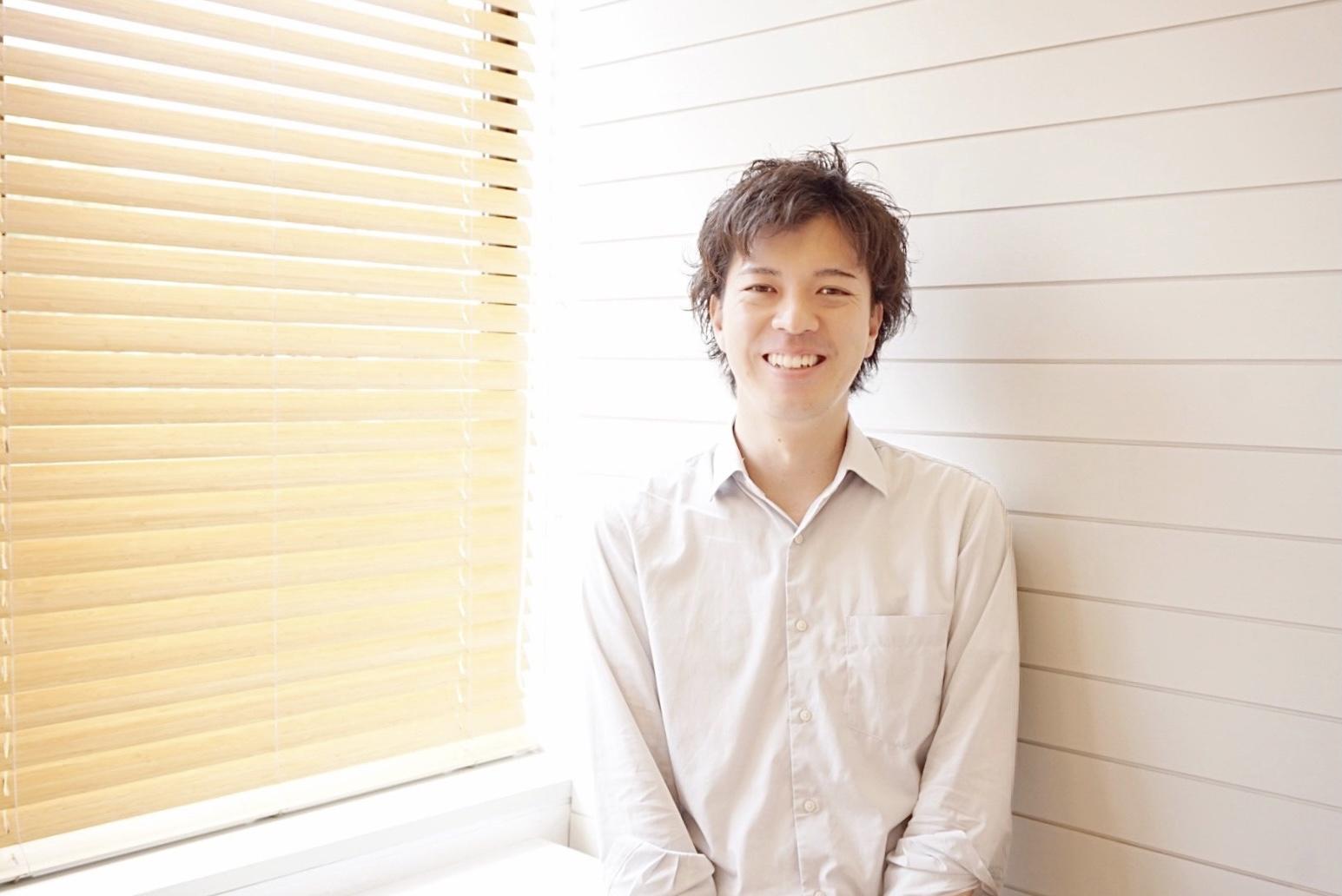
株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
近年おしゃれな平屋に人気が集まっていますが、平屋は限られた空間をうまく活用しなければ、満足のいく家が作れない難しさがあります。そのため、深く考えずに施工してしまい、後悔しているという方は意外と多いです。
「後悔しない新築平屋を建てるには、どんな準備が必要?」
「平屋を建てた人がどんなことに後悔しているか知りたい」
そこでこの記事では、新築で平屋を建てた先人のよくある失敗例を参考に、後悔しない理想の平屋を実現するためのコツを解説していきます。
さらに、失敗しないための注意点や、業者選定時のポイントもあわせて紹介していきますので、新築平屋を検討している人はぜひチェックしてみてください。
【TOP4】新築平屋の失敗例ランキング!

平屋のメリットとデメリットをよく把握せずに新築を建ててしまい、後悔しているという人は少なくありません。まずは、新築平屋を建てた人が後悔している内容の中から、最も多くみられた失敗例4つを紹介していきます。
- 間取りや収納に関する後悔
- 外からの視線や防犯面への不安
- 採光や風通しに関する後悔
- 土地選びに関する後悔
上記の失敗例を事前に把握しておけば、自身の新築平屋を設計・計画する際のヒントとして活用できます。上記の4つの要素は相互に関係しあっているため、それぞれの側面から慎重に検討することが求められるでしょう。
たとえば、生活動線がうまくいくように設計できたとしても、外観対策や採光などに配慮できていないと失敗してしまう可能性が高いのです。それぞれ詳しく紹介していきますので、一緒にみていきましょう。
平屋に限定せず、新築全体の失敗例と対策を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
「新築のよくある失敗事例15選!住宅購入や間取りに後悔しないための対策」
平屋の間取りや収納に関する後悔

新築平屋の後悔として最も多いのが、間取りや収納に関する失敗例です。
- 平屋だとすべての部屋がリビングに隣接していてうるさい
- 平屋でプライバシーを確保する間取りが難しい
- 収納が少なく部屋が片付かない
- 家事動線が悪く効率よく動けない
- 生活導線が悪く不便に感じる
- 土地が狭くて思い通りの間取りができなかった など
平屋では居住空間が限られているため、間取りが難しいという特徴があります。無駄なスペースが多いと、家事の効率や家族の生活効率が下がってしまうでしょう。
朝の忙しい時間や家事をおこなう場面において効率的な動線が整っていないと、何度も同じ場所を行き来しなければならず、スムーズに動けないのです。家族とぶつかったり譲り合って移動したりなど、小さなストレスがたくさん生まれることになるでしょう。
外からの視線や防犯面への不安

平屋ならではのデメリットである「外からの視線」や「防犯面」が気になってしまい、安心してくつろげないというケースも多く耳にする失敗例です。
- 平屋だとすべての部屋がリビングに隣接していてうるさい
- 外観にこだわらなかったので目隠しができていない
- 人通りの多い時間に外からの視線が気になる
- 隣の家と距離が近くて視線が気になる
- 洗濯物が干しにくい
- 泥棒に侵入されないかという不安がある
平屋はすべての部屋がワンフロアで完結するため、移動や掃除の面での利便性が高いのが魅力ですが、道路や隣接する家から室内が見られやすくなります。
さらに、平屋は窓の数が多くなる傾向があり、泥棒の侵入ルートが増える可能性があるのです。寝室や子ども部屋も1階にあるため、万が一の事態を考慮すると安心して寝られないと感じている人も少なくありません。
採光や風通しに関する後悔

平屋では、すべての部屋をワンフロアに配置しなければならないため、日当たりや風通しの悪い部屋ができてしまうことがあるのです。そのため、以下のような失敗談も多く耳にします。
- 採光が不十分で部屋が暗い
- 風通しが悪くジメジメする
- 窓の数や位置が悪い
- 想像していたよりも寒い・暑い など
昼間でも暗く風通しの悪い部屋になると、ジメジメとした空間になり、湿気やカビの原因になってしまいます。最悪の場合は体調や精神面にも影響するかもしれませんので、十分な注意が必要です。
2階建ての場合は、採光を確保するために南側にLDKを配置するなどの対策ができます。しかし、平屋では、特に家の中心部分の採光や風通しが悪くなりがちです。周囲に2階建てや3階建ての建物が密集している場合はより難しいでしょう。
土地選びに関する後悔

平屋は二階建てよりも面積が必要になることから、狭い土地や人気の高い場所では特に土地選びの難易度が高くなる傾向があります。そのため「もっとこうすればよかった」と後悔している方も多いようです。
- 購入した土地が広すぎて持てあましている
- 庭を作ったもののちゃんと手入れできていない
- 土地選びの時点で予算をオーバーしてしまった
- 平屋のため水害が心配
また、「立地を重視したら小さい平屋しか建てられず後悔している」という声などもあります。広々と住みたいのか、通勤や暮らしやすさを重視した立地にするのかなど、土地選びも後悔しないしない平屋づくりのためには欠かせない要素です。
新築平屋の失敗1:間取りや収納への対策

新築平屋の間取りや収納に失敗しないためには、以下の5つの対策が重要です。
- 効率的な動線を考慮する
- 各部屋の広さと配置のバランスを考慮する
- プライベートスペースを考慮する
- 音漏れやニオイ対策をする
- 有効活用できる収納スペースを確保する
平屋の間取りを考える際は、生活スタイルや家族構成をしっかりと把握し、無駄のない配置を心掛けることがポイントになります。詳しくみていきましょう。
効率的な動線を考慮する

新築平屋で失敗しないためのポイントとして、まず「効率的な動線を考慮する」ことが挙げられます。動線には「家事動線」と「生活動線」の2種類があり、それぞれの機能性が住みやすさに大きく影響するのです。
家事動線は、家事をおこなう際の移動ルートのことで、動線が悪いと家事効率が悪くなってしまいます。特に、家事の中でも重労働である洗濯の家事動線は重視しましょう。洗濯機と干す場所の配置や距離をしっかりシミュレーションしておくことがおすすめです。
また生活動線は、家の中での移動ルートを指します。家事の邪魔にならないよう、家事動線と別ルートになっているのが理想的です。生活動線をスムーズにすることで、家族のストレスを軽減し、快適な生活を実現できます。
各部屋の広さと配置のバランスを考慮する

平屋の間取りを検討する際は、各部屋の広さや配置のバランスを考慮することが重要です。家族の生活スタイルや習慣に合った間取りを考えることが第一優先ですが、家事やプライバシーにも配慮する必要があります。
家族全員がストレスなく過ごすためには、以下の配慮をするといいでしょう。
- リビングとキッチンの距離を近くする
- 寝室とバスルームの距離を近くする
- トイレを2つ作る、不便な位置に作らない
- プライバシーを考慮して書斎・寝室を配置する
- ニーズに応じて広さを検討する(子供部屋・趣味部屋・書斎など)
配置やバランスを検討する際は、間取り図から新築完成後の暮らしをイメージし、生活シミュレーションを立ててみるのがおすすめです。潜在的な課題が発見でき、改善策を検討することができます。
また、コスト削減を意識した壁の配置なども検討しながら、効率的な空間になるよう配慮してください。
プライベートスペースを考慮する

平屋を建てる際は、コミュニケーションが促進される反面、プライベートな時間が取れないという一長一短な側面にも着目しましょう。家族全員で同じ空間で過ごすことになるので、ストレスのない間取りや空間の工夫が必要になります。
- リビングに襖付きの畳コーナーを作る
- オープンデスクで好きなことが環境を作る
- ウッドデッキにチェアやテーブルを置く
上記のような工夫があれば、「1人になりたい」と自室にこもりがちになってしまうことを防げるでしょう。ぜひ間取り設計時に担当者へ相談してみてください。
音漏れやニオイ対策をする

平屋は上下階がなく、隣接する部屋同士で音やニオイが伝わりやすい傾向があります。特に、LDKと寝室・子ども部屋などのプライベート空間が隣接している場合、生活音やテレビの音などが気になってしまうことも多いでしょう。
- LDKと各居室の間に収納スペースを挟む
- 廊下を設置して音の伝わりを緩和する
- 隣接する部屋同士の壁を二重にする
- 防音性の高いドアや吸音性のある床材を選ぶ
- 静かに過ごしたい部屋をLDK・水回りから離す
音漏れやニオイ対策で効果的なのは、対象物から距離を取ることです。廊下を設置して、音やニオイの出所とその他居室を物理的に隔離するのがいいでしょう。
また、ニオイ対策に関しては、上記の工夫に加えて換気計画を重視することが大切です。
- 各水回りに窓を設けて自然換気する
- 強力な換気扇や24時間換気システムの導入を検討する
- キッチンとリビングの間に引き戸や間仕切りを設ける
有効活用できる収納スペースを確保する

新築平屋を成功に導くには「有効活用できる収納スペース」をしっかり確保しておくこともポイントになります。平屋は2階建てに比べて収納スペースが限られるため、以下のような収納計画が必要です。
特にリビングは、細々とした物が多くなる場所なので、適切な収納スペースを確保する必要があります。ただし、収納スペースが極端に広くなりすぎてしまい、居住スペースが圧迫されないように注意しましょう。
長年使用していないものは捨てて持ち物を整理し、見直すことで有効活用できる収納スペースが確保できます。
新築平屋の失敗2:防犯面への対策

外からの視線や防犯面の問題を回避するためには、プライバシーを守る工夫や防犯対策をしっかりと考慮することが大切です。設計段階でしっかりと取り入れるために、以下の対策を把握しておくことをおすすめします。
- 視線対策をする
- 防犯対策を考慮した設計にする
- 窓に目隠し・防犯の工夫をする
- 中庭やサンルームを作る
視線対策をする

平屋はその特性上、外の視線からプライバシーが確保できるような工夫をしなければなりません。以下は視線対策の一例ですので、設計時の参考にしてください。
- 窓の取り方に配慮する
- 建物の形状を工夫し庭を配置する
- 外構エクステリアを工夫する
- 目隠しフェンスを設置する
- 遮光カーテンやシャッターを活用する
道路からの目線が気になる場合は、目隠しフェンスを設置するのがおすすめです。
建物と駐車スペースとの間や、洗濯物を外干しする場合などは、近隣や道路から見えない死角を作ることを意識してください。玄関アプローチに合わせた木目のフェンスや、玄関ポーチ横の木製格子なども効果的です。
また、平屋では寝室や子ども部屋などもすべて1階にあります。外から見えやすいため、道路や周辺環境、近隣の窓や庭の位置なども考慮して間取りを設計するよう心掛けてください。
防犯対策を考慮した設計にする

新築平屋の防犯対策としては、以下の4つが有効です。
- 死角に防犯カメラやセンサーライトを設置する
- 家の周りに防犯砂利を敷く
- 補助錠を取付ける
- 夜間はシャッターを常に閉める
外観に上記の対策をしておくことで、泥棒が侵入を諦める可能性が高くなります。後から対策すると余分な費用がかかったり、景観を損ねたりすることがあるため、設計段階から防犯対策を考慮しておくことが大切です。
窓に目隠し・防犯の工夫をする

目隠しや防犯対策として最も有効なのが「窓の位置や種類」への工夫です。そのため、窓の設置時には以下を検討することをおすすめします。
- 大きな窓を極力少なくし、小さな窓をハイサイドに設置する
- 窓ガラスを防犯ガラスにする
- 防犯フィルムを貼付ける
- 面格子・雨戸を取付ける
窓を高い位置へ設置することで、室内から道路の様子が見えづらくなります。通行人と目が合う心配がないので、過ごしやすい空間が実現できるでしょう。さらに、侵入者にとっても厳しい環境になるので、防犯面とプライバシー確保の双方が叶います。
また、窓自体に防犯対策をするのも効果的です。平屋は窓から侵入されるリスクが高いので、パッと見て防犯対策されていることがわかる窓はそれだけで狙われにくくなります。
中庭やサンルームを作る

平屋の場合は、基本的にベランダではなく庭に干す形になるので、干す場所の日当たりやプライバシーにも配慮しなければなりません。外からの視線や防犯面が気になるという方には、以下の対策をおすすめします。
- 中庭を作る
- ランドリールームやサンルームを作る
中庭のある設計にすることで、間取りにも開放感や奥行きが生まれます。外からの視線も気にならないため、小さな子どもの庭遊び時も安心できるでしょう。
また、ランドリールームやサンルームを作ることにより、周囲の目線だけでなく天気にも左右されず、いつでも洗濯物が干せるようになります。洗濯機のある場所に隣接させれば、一か所で作業が完結するので、家事動線もよくなるでしょう。
新築平屋の失敗3:快適性への対策

採光や風通し、断熱性など、住宅の快適性にもこだわることで、新築平屋への住み心地がぐっと高くなります。失敗しないためには、事前に改善策を考慮した間取り設計をすることが大切です。
- 窓で自然光を効率的に取り入れる
- 大きな窓は断熱性への対策を
- 風通しを考慮した間取りプランを検討する
- 適切な断熱材を選択する
窓で自然光を効率的に取り入れる

平屋はワンフロア構造のため、家の中心に位置する部屋の日当たりがどうしても悪くなってしまいます。日当たりの有無は、部屋の明るさ・温かさを左右する重要な要素です。
自然光を効率的に取り入れるためには、窓に以下の工夫をすることをおすすめします。
- 屋根にトップライト(天窓)を設ける
- 高い位置に窓を配置する
- 勾配天井や高天井を採用する
間取りの設計前には、東側や南側からの太陽光がどの程度かを事前に確認しておくといいでしょう。建物の窓の位置なども参考になるので、現地調査がおすすめです。適切な窓の配置により、自然光を最大限活用した快適な生活空間が実現できます。
大きな窓は断熱性への対策を

せっかく平屋にしたのだから、と大きな窓を設置したがる人も多いですが、大きい窓はそのぶん断熱性が低下するということに留意する必要があります。窓は住宅の中でも外気の影響を受けやすい部分であり、面積が広くなるほど夏は暑く、冬は寒くなりやすいです。
そのため、以下のような対策が不可欠になります。
- トリプルガラスや樹脂サッシを採用する
- 窓のサイズや仕様を慎重に決める
開放感・デザイン性・断熱性・採光など、さまざまな側面からしっかり検討しましょう。
風通しを考慮した間取りプランを検討する

間取りプランの段階から、採光や風通しについて検討しておくことも大切でしょう。風通しを良くするための工夫は以下の通りです。
- 建物の形を「L型」や「コの字型」にして中庭を設置する
- 吹き抜け構造・間仕切りの少ない間取りにする
また、効率的に換気するために、風を取り込みやすい「縦すべり窓」を採用してみるのもいいでしょう。特に一方向にしか窓が配置できない場合は、横すべり窓を2つ並べて配置するのがおすすめです。
適切な断熱材を選択する

平屋で快適に過ごすために必要なのが「適切な断熱材を選択する」ことです。断熱性能が高い家は、夏でも冬でも快適な室内環境が維持できるため、健康にも良い影響を与えます。平屋の外皮(断熱)性能のグレードは「G2」がおすすめです。
適切な断熱材を選ぶには、建築業者が断熱性や気密性の数値を1棟1棟きちんと計算しているかどうかを確認します。性能が高い家は費用がかさむ可能性もありますが、温度差による健康被害を防ぐためにも、断熱性能にこだわるのがおすすめです。
特に、朝晩の冷え込みが厳しい地域の人や、家族に高齢者が居る場合は、室内の温度差を抑えるような配慮が必要になるでしょう。
新築平屋の失敗4:土地選びへの対策

土地選びの際は、以下のポイントを意識してみてください。
- 土地選びと間取り作りを同時進行する
- ハザードマップで水害のリスクを確認する
- 現地の下見を念入りにおこなう
- 広い土地に建てる場合は管理の負担を減らす
土地選びと間取り作りを同時進行する
土地選びに失敗しないためには、まず土地選びと間取り作りを同時におこなうことをおすすめします。家づくりの前に土地を選んでしまうと、理想通りの広さや間取りの家にならない可能性があるためです。
建物には建築基準法によってさまざまな基準が定められており、条件によっては土地めいっぱいに家を建てることができないケースもあります。そのため、理想の間取りや広さに必要な部屋数・延床面積を明確にして、それに見合った土地を探すのがいいでしょう。
また、先に土地だけ押さえてしまうと、予算が足りず建築費にお金がかけられなくなるリスクもあります。トータル予算を把握する観点でも、同時進行がおすすめです。
ハザードマップで水害のリスクを確認する

新築平屋で失敗しないためには、土地購入時の「地盤調査」もポイントになります。
平屋は水害に弱く、2階建てのような一時的な避難場所もないため、緊急時に逃げる場所がほとんどありません。
そのため、平屋を建てる前にはハザードマップを確認し、水害リスクを把握しておくことをおすすめします。最低でも2つの機関からの情報を集めて、河川の氾濫の可能性や水位の上昇範囲、避難場所・経路の有無などを調査しておきましょう。
ハザードマップを確認すれば、深水範囲や深さが確認できるので、平屋を建てるのに適した土地かどうかが判断できます。国土交通省の「重ねるハザードマップ」や「わがまちハザードマップ」を活用するのがおすすめです。
水害のリスクを最小限に抑えることで、安心した平屋での暮らしが実現できます。
現地の下見を念入りにおこなう
予算に合わせた柔軟なプランニングは、コスト管理に失敗しないための重要なポイントです。平屋は魅力の多い物件ですが、広い土地が必要になります。予算内で十分な広さの土地が確保できないと、平屋の良さは活かしきれません。
広い土地に建てる場合は管理の負担を減らす
郊外に新築平屋を建てるとなると、つい「広い庭付きの家を建てたい!」と広い敷地を確保しがちです。しかし、敷地や外構が広すぎると管理が大変になってしまうため、十分注意しましょう。
「広すぎる土地に新築平屋を建ててしまい、管理が大変で失敗した」という声は、意外と多いです。今はよくても、老後になって困るケースもありますので、ライフプランやキャパシティを考慮した上で土地を選びましょう。
たとえば、庭付きの新築平屋を建てる場合、雑草が生えにくくなるような工夫をしたり、落ち葉の少ない木を選んだりするのがおすすめです。家を建てる段階で、管理が楽になるような配慮をしておけるといいでしょう。
新築の平屋で失敗しないための注意点!

新築の平屋を設計する際のポイントについて紹介しましたが、失敗しないためには、見落としがちな以下の注意点についても把握しておくことをおすすめします。
- 家の構造面にも着目する
- 予算設定と柔軟なプランニング
- 資金調達とローンの選択
- 工事費用の見積もりと交渉術
理想の平屋を建てたい方、また建てた平屋に長く住みたい方には必要な項目なので、しっかり覚えて自身の新築計画に役立ててください。
家の構造面にも着目する

新築を建てる時は、つい間取りや内装・設備などの設計プランにばかり着目しがちですが、目に見えない部分についてもしっかりと検討しましょう。特に、以下の2点はしっかりチェックしておいてください。
- 基礎工事を重視する
- 適切な断熱材を選択する
新築の平屋で失敗しないためには、まず「建物の基礎工事を重視する」ことをおすすめします。基礎工事は家の土台を作る過程の工事で、建物の耐久性や安全性に大きく関わるものです。
平屋の場合は地盤への重量負荷が1階分しかないため、基礎工事が適切におこなわれているかどうかが非常に重要になります。万が一基礎工事が不十分だった場合は、将来的にひび割れや沈下などの問題が発生してしまう可能性があるのです。
適切な基礎工事をおこなうためには、まず地盤調査をしっかりとおこなうことが大切になります。適切な地盤改良や基礎工法を選択する必要があるため、信頼できる業者に依頼することを心掛けてください。
予算設定と柔軟なプランニング

予算内で理想通りの新築平屋を建てるには、コスト管理を徹底しなければなりません。予算に合わせた柔軟なプランニングは、コスト管理に失敗しないための重要なポイントです。
平屋は魅力の多い物件ですが、広い土地が必要になります。予算内で十分な広さの土地が確保できないと、平屋の良さは活かしきれません。
たとえば、4人家族でゆとりのある暮らしを望む場合は、35坪程度の平屋が理想的です。プライバシーや周辺との兼ね合いを考慮すると、80坪程度の土地が必要になります。
狭い土地に無理やり平屋を建ててしまうと、プライバシーが確保できず住みづらくなってしまう可能性があるのです。そのため、土地の値段が安い場所への居住を検討するか、平屋ではなく2階建てを検討することをおすすめします。
ただし、土地の広さや条件が厳しいケースでも、ハウスメーカーなどの専門家の的確なアドバイスを取り入れれば、上手く工夫して快適に住むことも可能です。予算組みやプランニングに迷ったら、まずは相談してみるといいでしょう。
資金調達とローンの選択
新築のコスト管理には、資金調達とローンの選択も大切です。住宅ローンは長期にわたる大きな負担となるので、金利や返済条件を慎重に検討しましょう。
ローンの比較検討については以下を参考にしてください。
- 複数の金融機関からローンの提案を受ける
- 固定金利と変動金利どちらかを選ぶ
- 返済期間や返済方法をチェックする
金利には「固定金利」と「変動金利」が存在します。固定金利は一定期間金利が変動しないため、リスクを抑えた融資が受けられるのが特徴です。一方、変動金利は市場とともに金利が変動しているため、金利下落が見込まれる場合に適しています。
また、返済期間や返済方法にも注意が必要です。長期間にわたる返済期間は、金利が低く月々の返済額が抑えられるものの、支払い総額は増加してしまいます。短期での返済を希望する場合は「一定期間無利息」のローンや、ボーナス時の返済が可能なプランを選択するといいでしょう。
工事費用の見積もりと交渉術
コスト削減のためには、工事費用の見積もりと交渉にも留意することをおすすめします。まずは複数の業者から見積もりを取得し、それぞれの内訳を比較検討してみてください。適切な価格提示かどうかを判断するためには、市場相場を事前調査しておくことも重要です。
また、見積もりを比較する際は、単価だけでなく「信頼できる業者かどうか」の見極めもおこなう必要があります。詳しい内容については後述しますが、いい加減な業者だと施工の品質が低くく、失敗する原因になってしまうでしょう。
見積もりを依頼した業者へ交渉してみるのも1つの方法です。ただし、他社の見積書を見せて交渉するのはマナー違反に当たるため注意してください。相見積もりを取っていることを伝え、他社との比較を口頭で伝えて交渉するのが好ましいです。
新築平屋に失敗しないために信頼できる建築業者を選ぼう

最後に、信頼できる業者選びのポイントを3つ紹介していきます。
- 口コミや評判を調べる
- 提案力やコミュニケーション能力をチェックする
- 施工品質とアフターサービスを検討する
上記3つのポイントを押さえた上で、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」をおこない、信頼できる業者の見極めをおこなってください。
可能であれば5社以上を候補に比較検討し、最終的に2〜3社に絞り込んだ上で相見積もりを取る方法がおすすめです。
1.口コミや評判を調べる
信頼できる業者探しの際に参考にできるのが、口コミや評判です。過去にその業者と取引した人の意見なので、実際の業務品質や対応がどのようなものかを掴むための参考情報になります。
インターネット上の口コミサイトやSNSなどで評判をリサーチし、以下の項目をチェックしてみましょう。
- サービス内容
- アフターサービス
- 品質
- コスト
- 担当者の印象
また、友人や知人からの紹介も有益な情報となるので、既に新築を建てたという人が身近に居る場合はヒアリングしてみるといいかもしれません。口コミや評判を調べることで、建築業者選びのリスクを最小限に抑え、安心して家づくりを進めることができます。
信頼できる業者を選ぶことは、快適な住まいを実現するための重要なステップです。
2.提案力やコミュニケーション能力をチェックする
口コミや評判などの事前情報だけに頼らず、実際に業者との面談の機会を設けたり、見積もりを取ったりすることも重要です。その際は、質問や懸念事項を積極的に伝えて、業者の対応や説明を詳しくヒアリングし、信頼性を判断してください。
建築業者には、顧客の要望や予算に応じた適切なプランを提案する能力が求められます。家づくりの過程で発生する問題や課題に対して柔軟に対応し、適切な解決策を提案できる業者なら、信頼性が高いといえるでしょう。
また、担当者のコミュニケーション能力も重視すべきポイントです。家づくりは長期間にわたるプロジェクトなので、円滑なコミュニケーションが求められます。顧客の要望を正確に理解した上で、適切なアドバイスやサポートができる業者を選定してください。
3.施工品質とアフターサービスを検討する
建設業者選びの際は、施工品質やアフターサービスについてもよく検討しておくことをおすすめします。施工品質は家の安全性や快適さに直結する要素なので、確かな技術と経験を持った業者を選定することが大切です。
施工品質を確認する方法としては、過去の実績や施工事例を確認するのがいいでしょう。建設業者のホームページなどで確認できます。さらに、建築現場を訪問したり、モデルハウスを訪れたりして、実際の建物の出来栄えを確認するのも効果的です。
また、家づくりは完成後もメンテナンスが必要なため、充実したアフターサービスを提供してくれる業者を選ぶことが好ましいでしょう。アフターサービスについては、定期的な点検や修繕サービスが提供されているか確認してください。
長期にわたって安心して暮らせる家を建てるためには、万が一のトラブル発生時に迅速かつ適切な対応が期待できるかどうかも重要なポイントです。
富山県の新築平屋でお悩みの方はぜひユニテにご相談ください

富山県周辺で平屋の新築を検討している方は、ぜひ一級建築士が在籍する弊社「ユニテ」までお気軽にご相談ください。
ユニテの新築ブランド「MagHaus」では、お客さまの要望に可能な限り寄り添った提案を心掛けております。理想のマイホームの実現に向けて、プロと共に二人三脚でプランニングできるのが特徴です。
また、弊社ユニテでは、リフォーム・リノベーション事業もおこなっており、豊富な施工実績がございます。新築物件のご相談はもちろん、「すでに新築平屋に失敗してしまってリフォームを検討している」というケースでも、どうぞ遠慮なくご相談ください。
新築平屋の失敗に関するよくある質問にユニテが答えます

ここからは、新築平屋の失敗に関するよくある質問に、弊社ユニテがお答えしていきます。以下の疑問や悩みを抱えている方は、ぜひあわせて参考にしてみてください。
- 新築平屋のその他失敗談は?
- 平屋のメリットとデメリットは?
- 新築平屋はやめたほうがいい?
- 新築は平屋と2階建てどちらにすべき?
新築平屋のその他失敗談は?
新築平屋の失敗談には、以下のような声も上がっていました。
- 外観が安っぽくなってしまった
- 内装がイメージと違った
- 圧迫感が出てしまった
デザインに関する失敗談も多いため、こだわりがある方は上記にも注意して家づくりをおこないましょう。
平屋のメリットとデメリットは?
平屋を建てるメリットとデメリットは以下の通りです。
|
|
|
|
|
|
上記をしっかり把握した上で、平屋を建てるか検討することが大切になります。特にデメリットを把握していないと「失敗した」と感じる原因になるため、知っておいて損はありません。デメリットを払拭できるような対策をおこなうことを意識しましょう。
新築平屋はやめたほうがいい?
平屋は先述したデメリットから、「やめたほうがいい?」と不安に思う方も多いです。新築を平屋にするべきか迷う方のために、向いている人と不向きな人を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
|
|
|
|
|
|
新築は平屋と2階建てどちらにすべき?
平屋と新築のどちらが最適かは、自身のライフスタイルや家族構成のほか、土地の広さや予算など、さまざまな要因によって左右されます。以下に平屋と2階建ての特徴を比較しましたので、判断材料としてお役立てください。
| 平屋 | 2階建て | |
|---|---|---|
| メリット | 階段がなく移動がスムーズ 家事動線が効率的 柱や壁の制約が少ない ワンフロアで家族の気配を感じる バリアフリー化しやすい |
狭い土地でも建築可能 プライバシーを確保しやすい 2階部分の日当たり・風通し良好 庭や駐車場などを確保しやすい |
| デメリット | 屋根・基礎が広いため割高 固定資産税が割高 広い土地が必要 日当たりや風通しが悪くなりがち 外からの視線が気になる |
柱や壁の制約あり |
まとめ
最後に、新築平屋で失敗しないためのポイントを一覧でまとめました。家を建てる際は、ぜひ参考にしてみてください。
| 失敗が多い内容 | 失敗しないためのポイント・対策 |
|---|---|
| 間取りや収納 |
|
| 外からの視線や防犯面 |
|
| 採光や風通しなどの快適性 |
|
| 土地選び |
|
新築平屋を失敗しないためには、よくある失敗例を参考に対策を練ることが大切です。特に多い失敗例である「間取り」「防犯」「採光・風通し」の3つを考慮したプラン設計をおこなうことをおすすめします。
また、コスト管理や業者選びも重要なポイントです。理想的な住まいに長く住むためにも、事前の計画や情報収集を十分におこない、納得のいく家づくりを実現させましょう。判断に迷う場合は、プロの意見を参考にしてみるのもおすすめです。
ユニテでは、定期的に相談会をおこなっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。