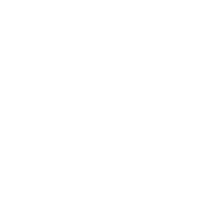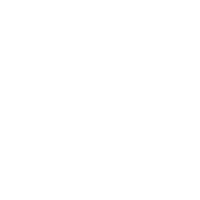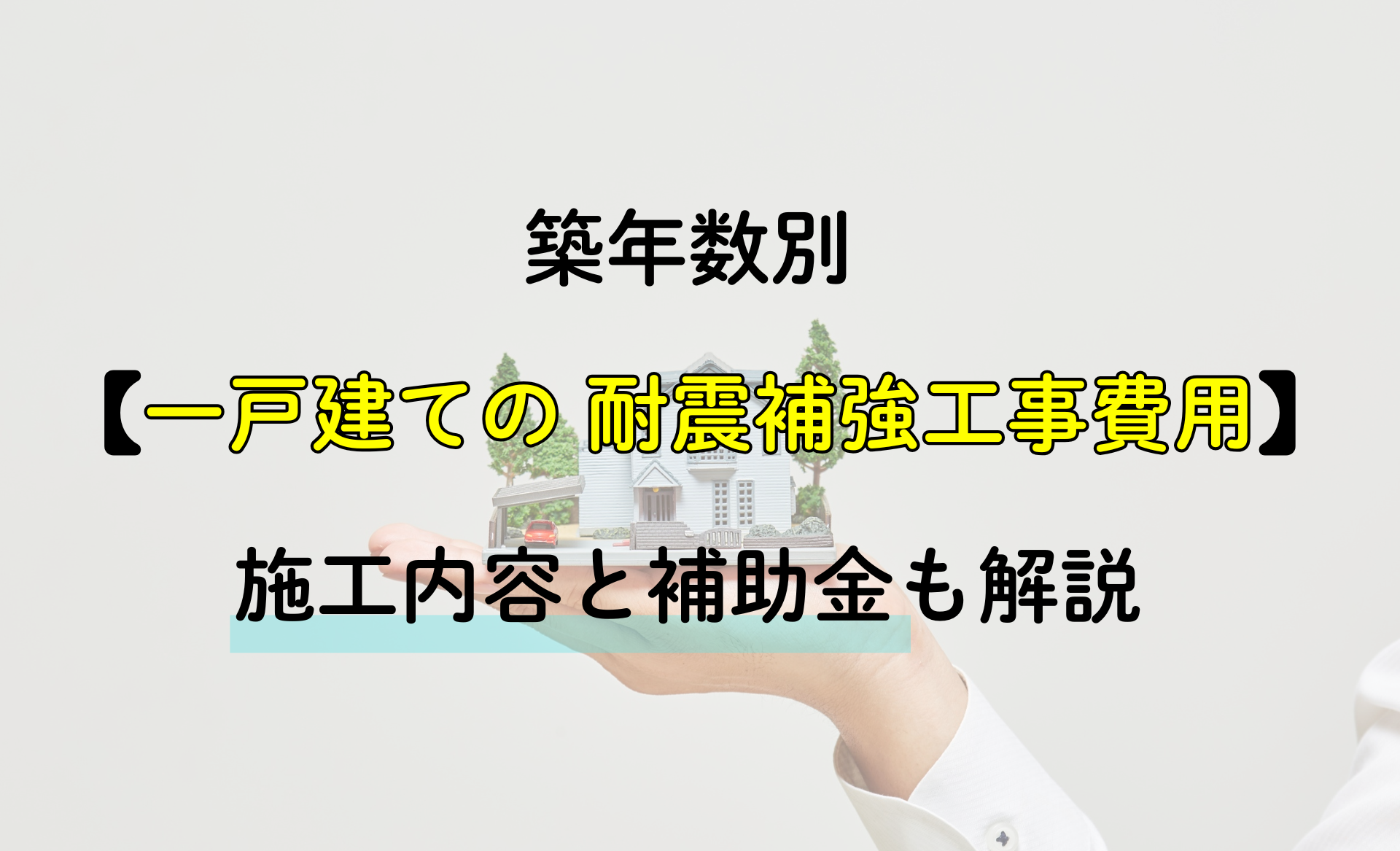
一戸建ての耐震補強費用を築年数別に解説。壁・柱・基礎などの施工内容や補助金・減税制度まで詳しく紹介し、必要な工事の判断に役立つ情報をまとめています。
「一戸建ての耐震工事をしたいけど、いくらかかるの?」
「補助金は使えるの?」
ご自宅の耐震工事を検討中の方には、上記のようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
日本は地震大国です。いざというときに、大切な家を守れるように対策はしたいですよね。
一方で、予算も気になるところです。
本記事では、一戸建ての耐震補強工事を検討中の方に向けて、以下の項目について解説します。
- 一戸建ての耐震補強にかかる費用(築年数別)
- 一戸建てでできる耐震補強の施工一覧
- 耐震補強が必要な一戸建ての特徴
- 必要な施工がわからないときの解決策
- 補助金と減税制度の概要
この記事を読むことで、耐震補強工事の実施までの具体的流れや予算の組み方がつかめるはず。ぜひ参考にしてください。
【築年数別】ひと目で分かる一戸建ての耐震補強にかかる費用

耐震補強工事にかかる費用は、築年数が古くなるに応じて高くなる傾向があります。
なぜなら、築年数が古くなるに応じて、修復が必要な箇所が増えるからです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
費用はご自宅の大きさや造りによっても変動します。
できるだけ明確な見積もりが必要な方は、施工会社の無料相談や見学会で相談してみましょう。
一戸建てでできる耐震補強の施工一覧

一戸建ての耐震補強をする際は、気になる箇所の施工をまとめて依頼することをおすすめします。
耐震補強工事の際には、足場を組む手間暇や人件費がかかります。
そのため、一度にまとめて施工をした方が、結果として時間や費用を節約できるでしょう。
一戸建てで行われる主な耐震補強工事は、以下のとおりです。
- 壁の耐震補強
- 柱の耐震補強
- 屋根の耐震補強
- 基礎の耐震補強
それぞれの費用の目安と具体的な施工内容を紹介します。
予算を考慮しながら、ご自宅に必要な施工を検討していきましょう。
壁の耐震補強
|
|
|
|
|
|
壁は住宅の構造を支える重要な役割も持つもの。そのため、壁自体の強度を高めることによって、建物が倒壊するリスクを抑えることが可能です。
また、軽量の壁材に変えることで地震時の揺れを緩和し、家具の転倒リスクも下がります。
柱の補強工事
|
|
|
|
|
|
柱は住宅の骨格でもある重要な構造部分であり、建物全体の安定性に直結しています。
そのため、柱の強度や接合部分をしっかり補強することで、地震時の倒壊リスクを大幅に減らすことができます。
一方、柱の老朽化が進んでいる場合は周辺の基礎部分の改修も必要となるでしょう。その場合は、合計で100万円以上かかる場合があります。
屋根の耐震補強
|
|
|
|
|
|
屋根材を軽量タイプに取り替えることで、地震時の建物の揺れを抑えることができます。その結果、建物自体への損傷や家具の転倒リスクも軽減されます。
軽量化に用いられる代表的な屋根材は、以下の3種類です。
<主な屋根材>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎の耐震補強
|
|
|
|
|
|
建物の基礎は、その上の構造を支えるのに欠かせない部分です。建物の基礎に損傷があると、地震発生時に住宅が倒壊するリスクが高まります。
基礎の補強費用は劣化の程度によって変動します。小さなひび割れであれば、数万円から20万円程度が目安。
基礎そのものの強度が不足している場合や劣化が進んでいる場合は、鉄筋コンクリートの増し打ちや補強が必要となります。この場合は、数百万円規模の費用がかかるでしょう。
耐震補強が必要な一戸建ての特徴
なんとなく耐震補強工事の必要性を感じつつも、「本当にやるべきなのか」「このままでも大丈夫では?」と迷っている方もいるでしょう。
確かに、建物のひび割れや木材の劣化は、外見だけでは判断が難しいものです。
そこでこの章では、耐震補強工事を検討すべき一戸建ての特徴を4つ紹介します。
- 建築日が1981年5月31日以前の家屋
- 2000年6月より前に建築された木造の家屋
- 過去に震災被害を受けた家屋
- 劣化が発生してきている家屋
該当する項目がある場合は耐震補強工事の実施を検討してみてください。
建築日が1981年5月31日以前の家屋

1981年6月1日の建築基準法改正により、新たな住宅には新耐震基準の適用が求められるようになりました。
つまり、1981年6月より前に建てられた家屋は現行の基準に則っていない可能性があり、地震発生時の倒壊リスクが高いのです。
主な違いを、表にまとめてみました。
|
|
|
|
|
|
住宅がどちらの基準に沿って建てられたかを確認したい方は、建築確認申請書や確認通知書の副本に記載された日付を見てみましょう。
図が指し示すとおり、旧耐震基準の住宅でも震度5程度までは耐えられます。
しかし、いつ大きな地震がお住まいの地域を襲うかはわかりません。念のための備えとして、耐震補強工事を検討することをおすすめします。
2000年6月より前に建築された木造の家屋

新耐震基準に加えて、木造住宅を対象とした「2000年基準」というものがあります。
これは2000年6月から施行された基準で、主に木造住宅の耐震性をさらに高めることを目的に制定されました。つまり、2000年5月までに建てられた木造建築は耐震性が劣る可能性があります。
新しい基準での変更点は、以下のとおりです。
気になる方は、耐震補強工事を検討し、現行の基準に合わせていきましょう。
過去に震災被害を受けた家屋

新耐震基準や2000年基準に沿って建てられた住宅であっても、必ずしも地震に完全に耐えられるとは限りません。
例えば、過去に地震の被害を受けたことがある住宅は地震時の倒壊リスクが高いといわれています。
外観に異常がなく普段の生活に問題がないように見えても、基礎や壁の内部にひび割れや損傷が生じている場合があるからです。
こうした状態では、建築当初に比べて住宅の耐久性や強度が低下しているかもしれません。
業者の方に、ご自宅の状態を確認してもらうことをおすすめします。
劣化が発生してきている家屋

なかには、すでに自宅の劣化に気づいているという方もいるのではないでしょうか。
以下のケースに当てはまる場合は、歪みや腐食が進んでいる可能性が高いです。
こうしたサインが見られる場合は、住宅の安全性を確保するために耐震補強工事の検討をおすすめします。
必要な耐震補強の施工がわからないときの解決策

耐震補強工事をしたいと思っても、どんな施工が本当に必要なのかわからないですよね。
その場合は、まず耐震診断を受けることをおすすめします。
耐震診断は、日本建築防災協会の定める方法と基準に従い、建物がどの程度地震に耐えられるかを4段階で評価する検査です。
この診断を受けることで、自宅の耐震性能を把握できるだけでなく、修繕が必要な箇所も明確になります。
さらに、耐震補強工事で助成金や税額控除を活用したい場合は、診断を受けておく必要があります。
なぜなら、控除や助成を受ける条件として、耐震診断の結果に基づいた改修工事であることが求められるからです。
耐震補強の費用をおさえるコツ

耐震補強工事を行う際は、以下の方法で費用をおさえることができます。
- 補助金をもらう
- 減税制度を活用する
各制度について、詳しく解説します。
補助金をもらう
耐震補強工事を行う際には、補助金を受け取ることができます。
ただし、国による全国共通の補助金制度はなく、金額や条件は自治体ごとに異なります。そのため、まずはご自身の住んでいる地域での制度内容を確認してみましょう。
また、多くの自治体では、施工前に耐震診断を受けることが補助金受給の条件となっているので注意してください。
補助金の詳細や申請方法を確認するには、以下の方法があります。
減税制度を活用する
国単位の耐震補強工事に対する補助金や助成金は用意されていない一方、以下2つの減税制度を活用することで、総合的な出費を減らせます。
以下の表を参考に、条件に当てはまるかどうかを確認してみてください。
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富山県で一戸建ての耐震補強を検討中の方は、ユニテにご相談ください
ユニテには一級建築士が在籍しており、築年数の経った住宅のリノベーションやリフォームの実績も豊富。数多くのお客様に安心と快適な暮らしを届けてきました。
住宅の状態やご希望に応じて最適な耐震補強プランを提案し、安心して長く住み続けられる家づくりをサポートします。予算がお決まりの方は、そちらも踏まえて検討します。
まずはお気軽に見学会にお越しください。
まとめ
本記事では、一戸建ての耐震補強の施工内容や予算についてお悩みの方に向け、以下の項目を解説しました。
- 一戸建ての耐震補強にかかる費用(築年数別)
- 一戸建てでできる耐震補強の施工一覧
- 耐震補強が必要な一戸建ての特徴
- 必要な施工がわからないときの解決策
- 補助金と減税制度の概要
耐震補強工事の準備を進め、安心安全に暮らせる家づくりにつながれば幸いです。