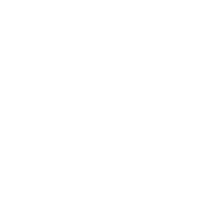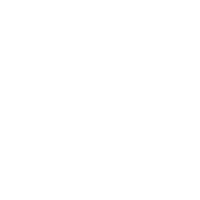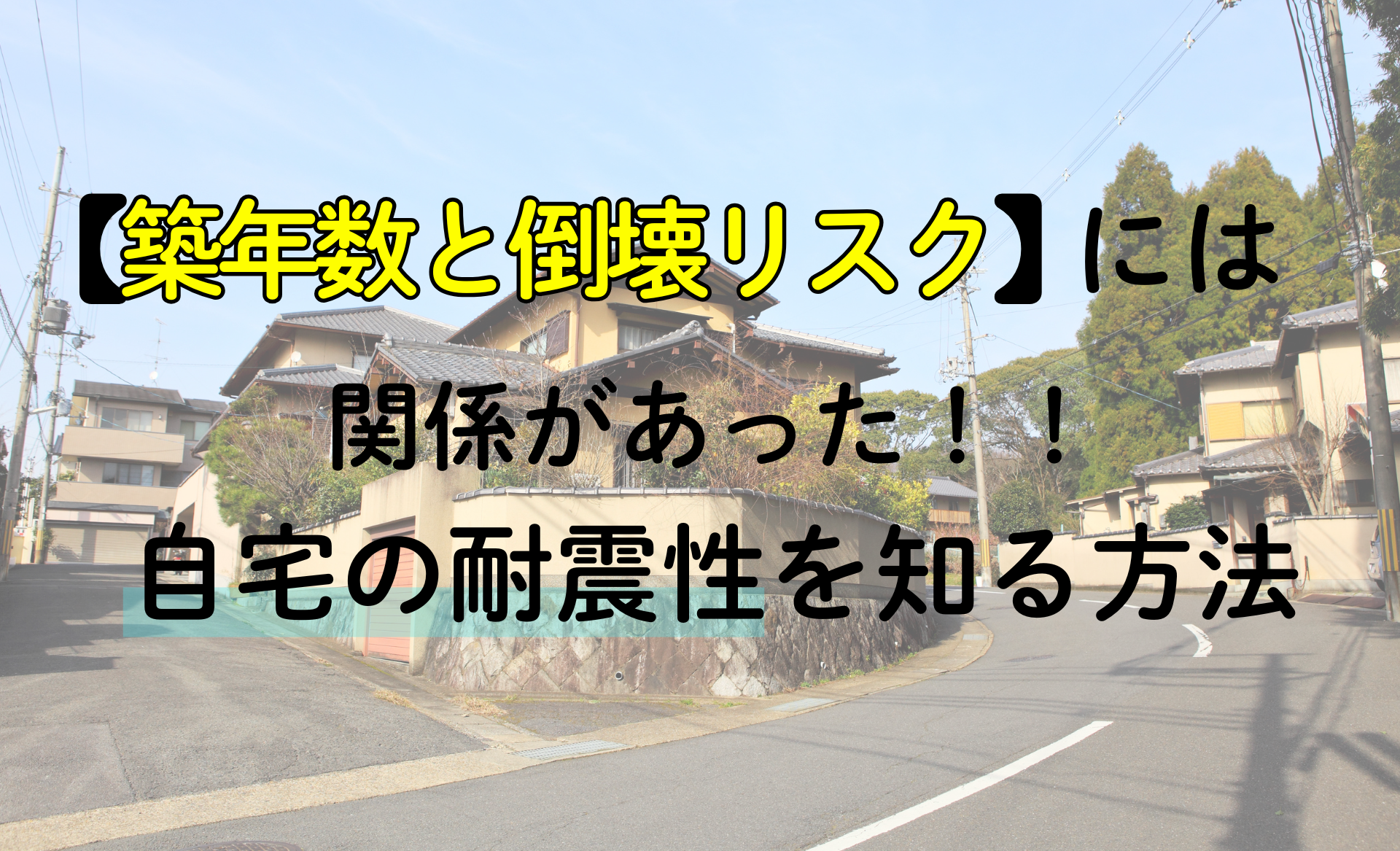
建物の築年数が長いほど地震発生時の倒壊リスクは高まるといわれています。しかし比較的新しい建物もかならず安全とはいえません。この記事では、倒壊リスクが高い住宅の特徴と、できる対策をお伝えします。
目次
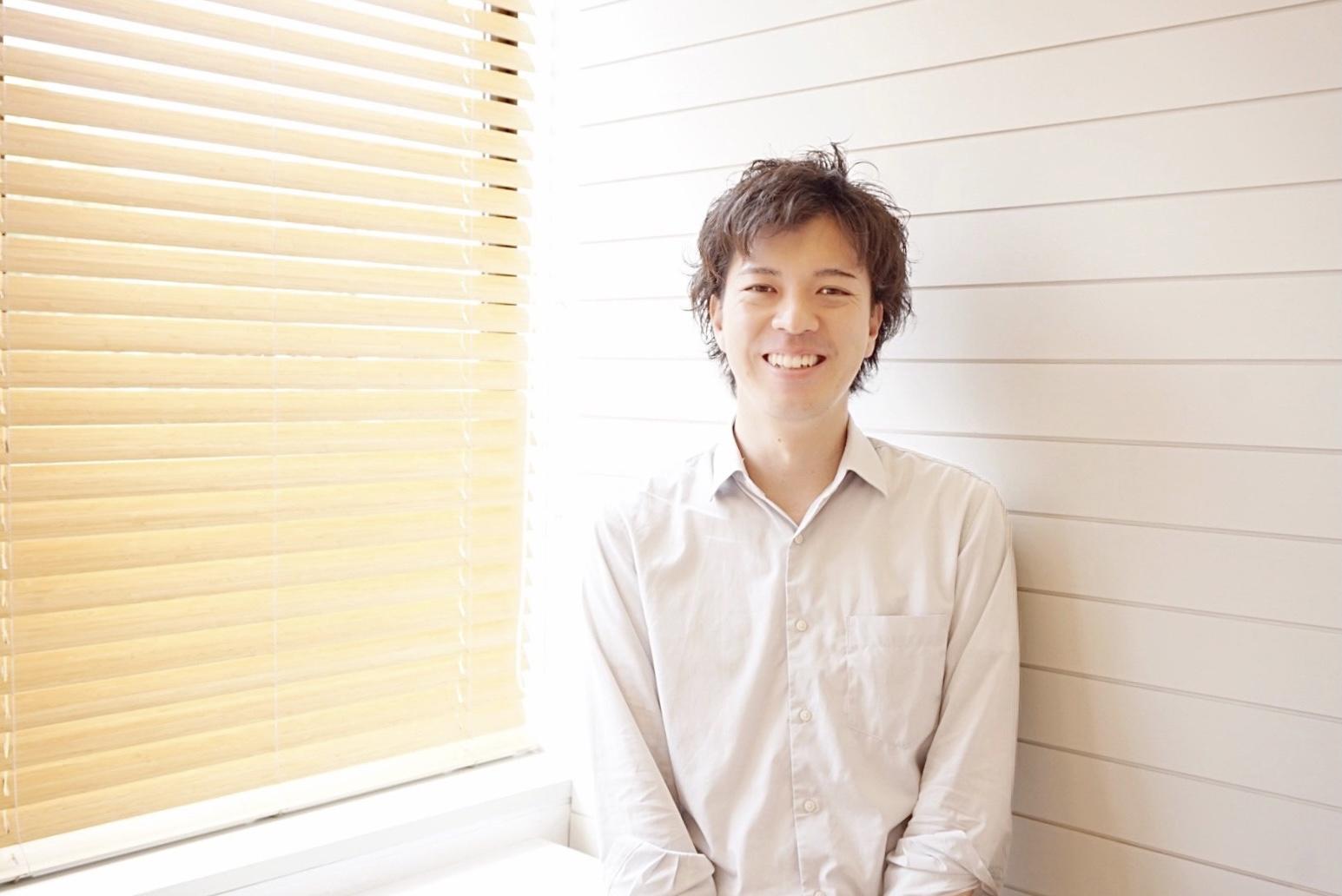
株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
「倒壊リスクが高まるのは、築年数何年から?」
「私の家は大丈夫か不安!」
など、古い住宅の耐震性が気になる方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、築年数と倒壊リスクは比例すると考えられています。一方で、築年数が浅くても倒壊リスクが高い建物もあります。
そこで本記事では、次の内容をお伝えしていきます。
- 築年数の基礎知識
- 築年数と耐震性の関係
- 耐震性が心配な建物の特徴
- 自宅の耐震性の調べ方
- 耐震工事の種類と費用
- 耐震工事に使える補助金
自宅の耐震性をきちんとチェックし改善する手順を知って、安心して暮らせる空間を叶えていきましょう。
そもそも築年数とは?

築年数とは、正式には「築年経過数」と呼ばれており、建物の施工が完了した日から何年が経過したかを指します。例えば、2020年に不動産サイトで「築年数10年」と記載された物件情報を見つけた場合、その建物が建てられたのは、10年前の2010年です。
築年数に「新築」と記載された物件があります。この場合、建物は完成から1年も経っていません。かつ過去の入居がなく完全に新しい状態であるということです。
混同しやすい「耐用年数」との違い
築年数とよく間違われる言葉に、「耐用年数」があります。これは税務上、減価償却処理をする際に基準となる項目。その物件を資産として使用できる期間を示し、時間が経つほどに資産価値は減少していきます。
そのため、耐用年数は実際に住める年数や建物が建てられた年数を示す数字ではありません。建物がいつ建てられたかを知りたい場合は、気にしなくて大丈夫です。
築年数と耐震性の関係

一般的に、築年数が古ければ古いほど地震発生時の倒壊リスクは高まるといわれています。
その理由は、以下の2つです。
- 傷みや腐食が進行している可能性があるため
- 耐震基準が築年数によって異なるため
傷みや腐食が進行している可能性があるから
築年数が古くなるほど、内部の腐敗が進んでいる可能性があります。特に木造は、湿気が溜まると木材が腐食したりシロアリの被害に遭ったりする可能性が高まります。
建物を支えるために必要不可欠な基礎部分や柱が傷んでいる可能性もあるので、湿気対策を怠らないようにしましょう。
耐震基準が築年数によって異なるため
建物を建築する際、建築基準法によって定められている耐震基準を守ることが義務づけられています。これは地震が発生しても建物が崩壊せず、その建物を利用する人が安全に避難できるように設けられた法律です。
1950年に建築基準法が定められて以降、耐震基準の改正は3回行われています。実際の災害被害や科学的な研究に基づき、より安心して日常生活を送れるようにするためです。
耐震制度が心配な築年数はこの2つ
自宅の耐震性が心配な方や中古物件の購入を検討されている方に確認してほしいのは、以下2つに該当していないかどうかです。
- 1981年5月31日以前に建てられた住宅
- 2000年5月31日以前に建てられた木造住宅
1981年5月31日以前に建てられた建物
1981年に建築基準法が改正され、同年6月以降に建てられた建物には「新耐震基準」にのっとった建築・設計が義務付けられています。そのため、震度6強~7の地震では、倒壊・崩壊しない設計になっています。
それまでに採用されていた「旧耐震基準」との違いは以下の通りです。
|
|
|
|
|
|
旧耐震基準でも、震度5までは耐えられると考えられています。しかし、建物の老朽化が気になる方やより大きな地震に備えたい方は、耐震補強工事の必要性を相談してみましょう。
2000年5月31日以前に建てられた木造住宅
2000年6月から、新耐震基準をさらに強化した基準が定められました。一般的に「2000年基準」と呼ばれるものです。
特に木造住宅に焦点を当てた基準であり、以下の項目が新たに加わりました。
築年数が浅くても安心できない理由

1981年6月以降に建てられた鉄筋コンクリート・軽量鉄骨の住宅、ならびに2000年6月以降に建てられた木造住宅は、現行の耐震基準にのっとった設計がなされています。
しかし、耐震性に影響を及ぼすのは法律で定められた耐震基準だけではありません。住宅の構造や立地条件によっては、十分な耐震性が期待できない場合があります。
ここでは、耐震性に影響を及ぼす5つの要素を紹介します。
- シロアリや湿気による腐食
- 増築リフォームの接合不良
- 過去の災害によるダメージ
- 建物の形状
- 地盤の弱さ
1.シロアリや湿気による腐食
築年数がさほど古くない住宅であっても、湿気が溜まりやすい場合は湿気やシロアリによって柱や基礎部分に腐食が進んでいる可能性があります。
特に木造住宅は湿気の影響を受けやすいため、日ごろから湿気対策を行っておくことが重要。換気や除湿器の使用などに加えて、床下に換気システムを導入したり、調湿剤を入れたりして、適切な湿度を保つ対策を検討してみてください。
湿気やシロアリによる被害が起こると、以下のような兆候があらわれます。
2. 増築リフォームの接合不良
増築リフォームは難易度の高い施工であり、接合不良の問題を抱えるリスクが比較的高くなっています。
増築リフォームをする際、既存の住宅に新しい壁を取り付けます。本来であれば壁1枚であった場所に接合部分ができ、ここから雨漏りが発生する恐れがあります。そうすると腐食が進んでいき、災害発生時に倒壊リスクが高まってしまいます。
今後増築を考えている方は、以下の2つをリフォーム会社に相談しておきましょう。
3. 過去の災害によるダメージ
過去に災害を経験している場合は、建物の内部に亀裂などのダメージが入っている可能性があります。この場合、徐々にダメージが進んでいき倒壊リスクを高める可能性があります。
例えば小さなひび割れであっても、雨漏りの原因となり、湿気を溜めて木材の腐敗やシロアリ被害の原因となってしまうことも。
まずは以下の点をチェックし、少しでも違和感があれば専門家に相談することがおすすめです。
4. 建物の形状
建物の形状は、地震発生時にどのようにエネルギーが分散されるかに影響を及ぼします。
最も倒壊リスクが低いとされているのは、四角形の建物。これはエネルギーが平等に分散されるためです。
一方でL字やコの字型の建物は、四角形ほどの耐性は期待できないといわれています。
5. 地盤の弱さ
地盤は、硬く丈夫な地盤と軟弱な地盤の2種類に分けられます。軟弱な地盤の場合、地震発生時に液状化してしまうリスクがあるため、避けた方がいいでしょう。
地盤の弱さによって、建物に傾きや沈下が発生した場合、以下のような現象が起こります。
河川や海など付近に水辺がある住宅に住んでいる方や埋立地に住んでいる方は、注意が必要。ハザードマップを使えば、ネットですぐにお住まいの地域の地盤の強弱を確認できます。
築年数や耐震性が心配なときの解決策
自宅の耐震性に不安がある方や耐震工事を検討している方は、財団法人日本建築防災協会の基準にのっとった「耐震診断」がおすすめ。プロの目を通して、自宅の倒壊リスクを確認するようにしましょう。
- 自宅の耐震性を調べる
- 具体的な施工内容を知る
- 住宅ローンに必要な耐震基準適合証明書を得る
- 工事内容を確定し、費用の見積をつくる
耐震診断で分かること

耐震診断では住宅の内部から周辺まで細かい点に目を配り、倒壊リスクと必要な耐震補強工事内容を調べます。
調査箇所と項目は、以下の通りです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐震診断にかかる費用

耐震診断の費用は、業者・延床面積・構造の3点によって異なります。
費用の目安は以下の通りです。
鉄筋コンクリート造
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄骨造
|
|
|
|
|
|
|
|
|
木造(在来軸組構法)
|
|
|
|
|
|
費用は竣工時の一般図・構造図の有無などによっても異なります。
築年数に不安を感じたときにできる耐震補強工事

築年数や耐震性に不安がある方は、以下の耐震補強工事で自宅の耐震性を高めることができます。
- 壁の補強工事
- 天井の軽量化
- 基礎の補強工事
1.壁の補強工事
|
|
|
|
|
|
2. 天井の軽量化
|
|
|
|
|
|
3. 基礎の補強工事
|
|
|
|
|
|
耐震補強工事での出費が心配なときの解決策
「耐震補強工事をする余裕がない……」
「出費を抑えたくて古い住宅を買ってしまった……」
といった不安やお悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?
耐震補強工事にかかる平均費用は総額150万円前後といわれており、築年数や施工内容によって左右されます。さらに耐震診断を受けると、総額はさらに膨らむでしょう。
しかし災害によって住宅が倒壊した際、再建にかかる費用は約2,500万円ほど。災害時の公的支援金は400万円のため、約2,000万円の自己負担が必要となります。
つまり、耐震補強工事を行い倒壊リスクを下げておくほうが将来的にかかる費用は安く済みます。そのうえ、自身や家族が安心して暮らす空間づくりにもつながります。
もし耐震補強工事を前向きに考えながらも費用が心配な方は、以下3つの制度の利用を検討してみてください。
- 自治体による補助金
- 所得税減額の控除
- 固定資産税の減額措置
自治体による補助金
耐震補強工事を受ける際は、お住まいの自治体の補助金制度が活用できます。国による全国的な補助金制度はないため、受給できる金額は自治体によって異なります。
ほとんどの場合、事前に耐震診断を受けたうえで、その診断結果にのっとった工事を行う必要があります。そのため、リフォーム会社への相談のみで施工内容を決定するのは避けてください。
自治体の補助金制度は、以下3つの方法で確認できます。
- 自治体のホームページで調べる
- 担当の窓口に行って、係りの人に聞いてみる
- 一般社団法人「住宅リフォーム推進協議会」の検索ページから探す
所得税減額の控除
以下の条件に沿って自宅の耐震補強工事を行った場合、所得税のうち5%~10%が控除を受けられます。
- 耐震改修にかかった費用であること
- 1981年6月よりも前に建築された家屋であること
- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること
- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること
- 税務署に確定申告を行うこと
- 控除上限は62.5万円
控除を受ける際には、確定申告が必要になります。以下の書類を税務署に提出する必要があるため、用意しておきましょう。
固定資産税の減額措置
以下の条件に沿って自宅の耐震補強工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が半分に減額されます。
- 1982年1月1日よりも前に建築された家屋であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること
- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること
- 工事後3カ月以内に申告していること
- 工事にかかった費用が50万円以上であること
減額措置を受けるためには、お住まいの地域の役所での手続きが必要です。工事完了の日から3カ月以内に、以下の書類を役所に提出しましょう。
築年数が古い家屋の耐震補強工事を受ける手順
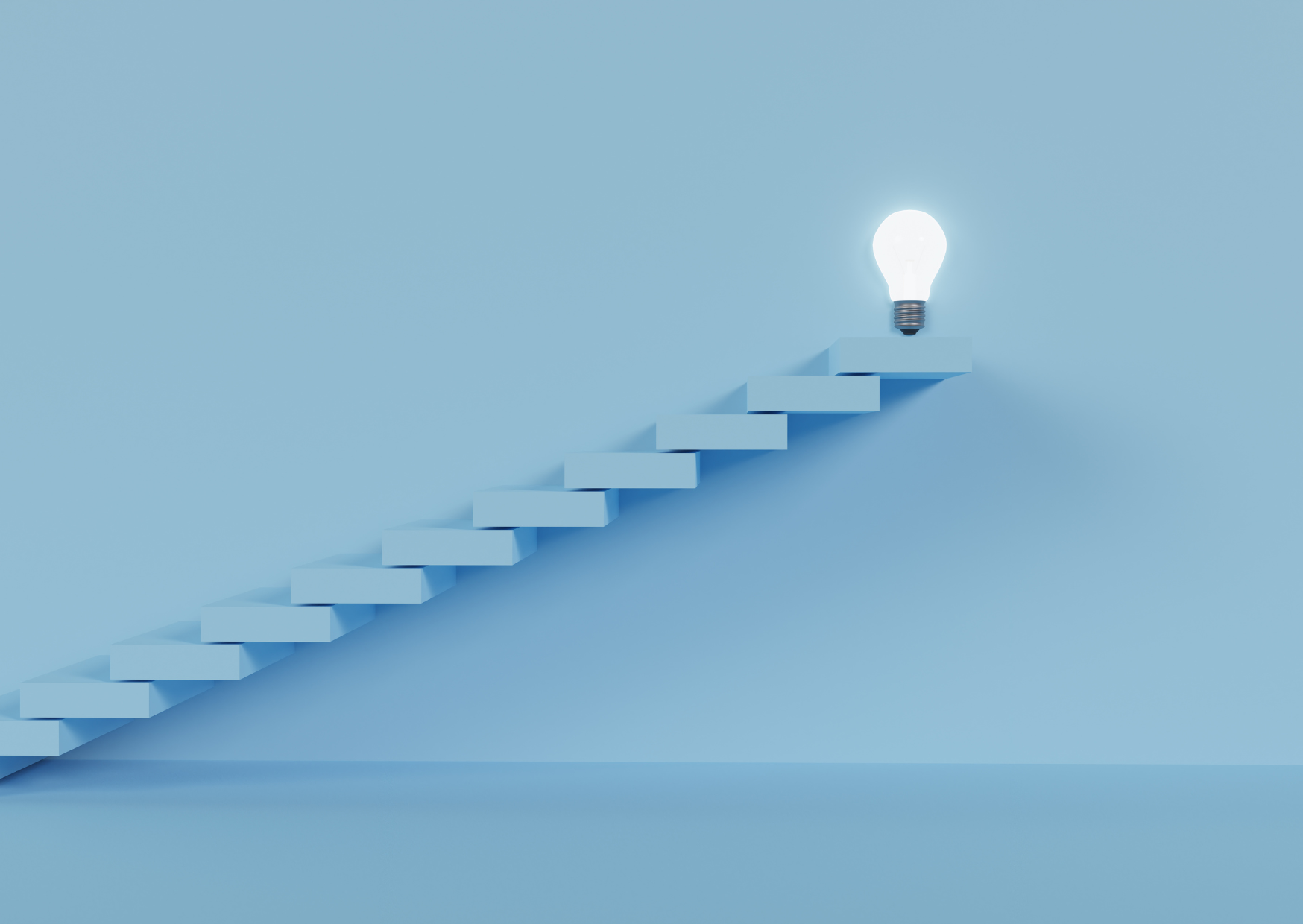
築年数が経った住宅の耐震補強工事では、所得税の控除や固定資産税の減額措置を受けることが可能です。これによって総合的な出費を抑えられます。
しかし、耐震診断を受けたうえで現行の新耐震基準に合った設計に改良する必要があります。
そのため、耐震補強工事を受ける際は以下のステップで進めていきましょう。
(※)申請する時期は自治体により異なります。
富山県で耐震補強工事をお考えの方はユニテにご相談ください

一級建築士が在籍しているユニテは、古い住宅のリフォーム・リノベーション実績が豊富です。築年数が古い建物であっても、ご要望をしっかりとくみ取りながら施工内容を決めていきます。
「耐震診断はまだ受けてないけど、まずはどんな施工ができるかを知りたい」
「同時にリノベーションもできるの?」
といった興味をお持ちの方も、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
今回は築年数が経った住宅の耐震性について、以下の6点をお伝えしました。
- 築年数の基礎知識
- 築年数と耐震性の関係
- 耐震性が心配な建物の特徴
- 自宅の耐震性の調べ方
- 耐震工事の種類と費用
- 耐震工事に使える補助金
家族が快適に日々を過ごしていけるよう、参考にしてください。