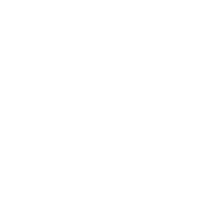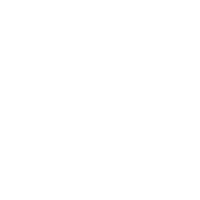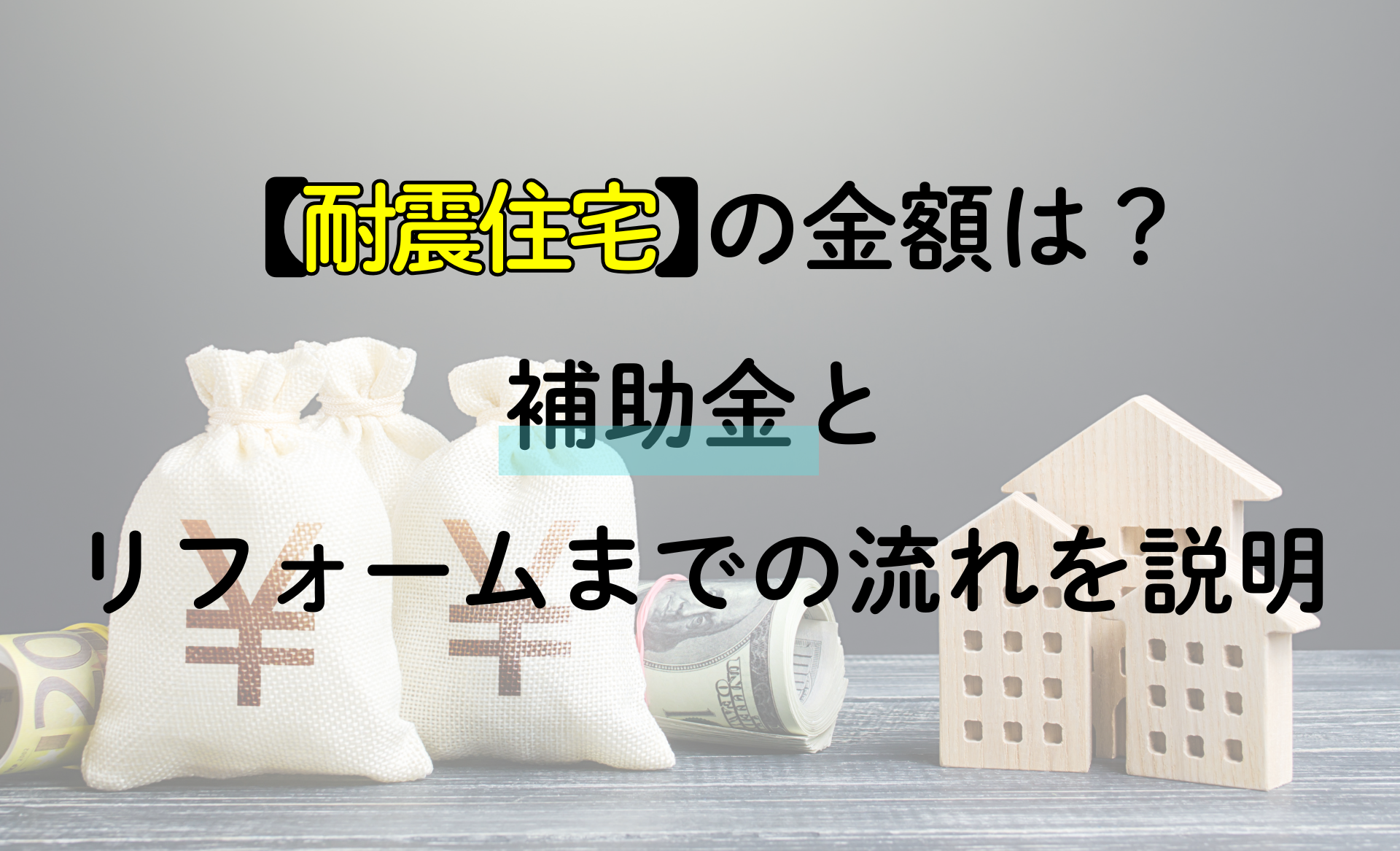
地震にそなえるための工事を考えている一方、出費が心配な方も多いのではないでしょうか。耐震補強工事をする際には、補助金や国の制度が受けられます。この記事では、実際に利用できる補助の種類と、受け取るための条件をお伝えします。
目次
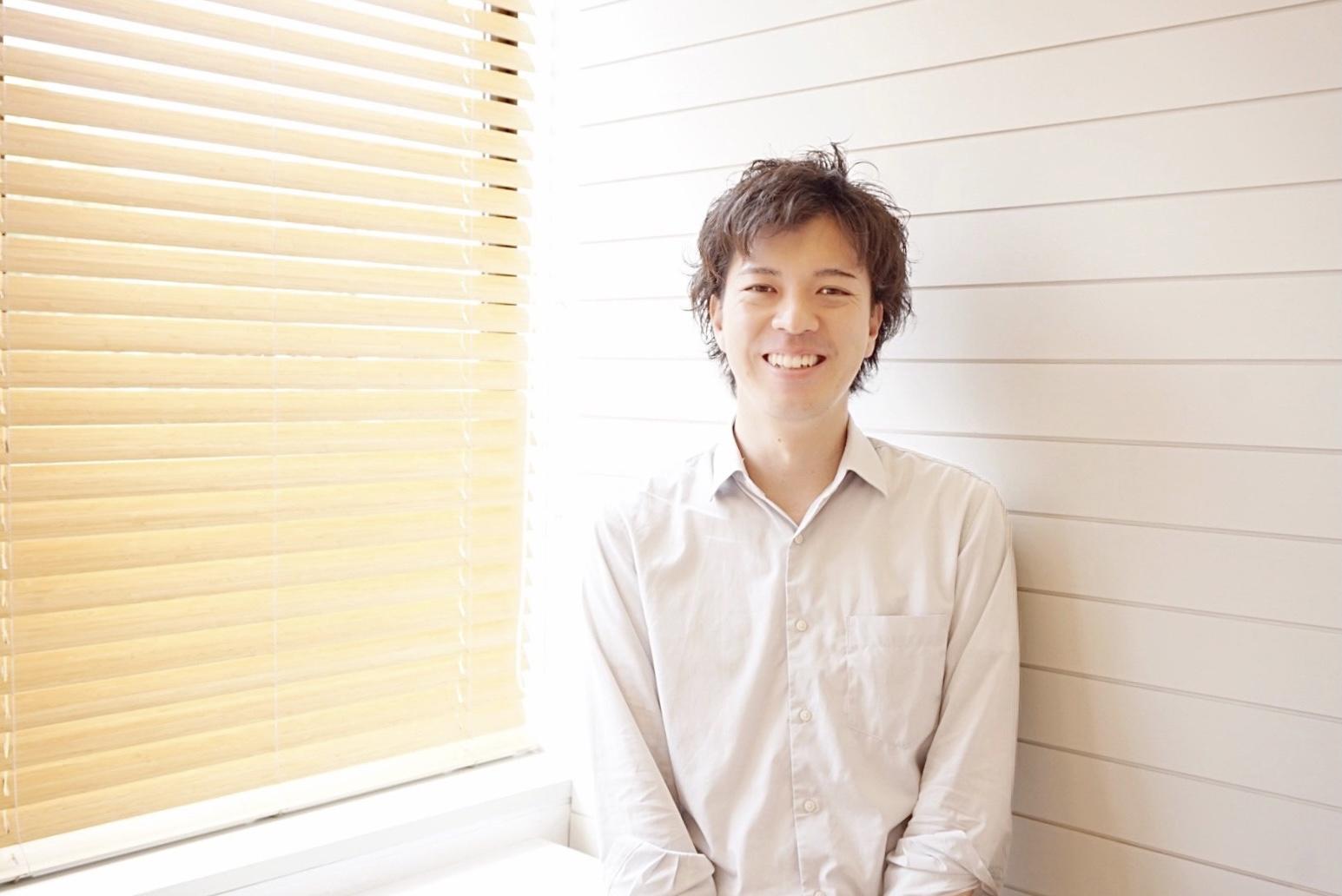
株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
「自宅の耐震補強をしたいけど、お値段が気になる」
「補助金は活用できるの?いくらもらえるの?」
など、耐震補強工事のコスト面が気になる方も多いのではないでしょうか。
できるだけ費用を抑えて地震発生時にそなえるために大切なのは、自宅に必要な補強工事が何かを把握することと、活用できる補助金を知ることです。
そこで本記事では、次の内容をお伝えしていきます。
- 耐震補強工事の種類と金額
- 耐震補強工事が必要な家屋と必要ない家屋の見極めポイント
- 施工を受けるまでの流れ
- 耐震補強工事の補助金と節税対策
ムダな支出を抑え、かしこく災害時にそなえるために参考にしてください。
耐震補強工事とは?種類と金額
耐震補強工事とは、建物の強度を高めたり、地震発生時の家屋の揺れを最小限に抑えたりする施工のこと。震災が起きたとき、家屋の倒壊や家具の転落といったリスクを軽減させます。
ここでは、主な4つの施工と費用を説明します。
- 壁の補強工事
- 天井の軽量化
- 基礎の補強工事
- 接合部分の補強工事
- 鉄筋コンクリート構造への改修工事
1. 壁の補強工事

壁は部屋を区切るだけではなく、建物を支える役割を担っています。そのため、壁の強度そのものを高めることで、家屋の倒壊リスクを軽減させます。また、壁材を軽く柔軟なものに変えることで、地震発生時の揺れを和らげ、家具転落のリスクを下げることも可能です。
主な施工は、次の2種類です。
- 壁に筋通いや構造版を追加することで、壁の強度を高める
- 壁を増やすことでバランスを整え、地震発生時の負担を分散させる
- 軽量の壁材に変更し、地震時に家屋につたわる揺れを抑える
- 柔軟性のある壁材に変更し、地震発生時のヒビ割れを防ぐ
2. 天井の軽量化

屋根材を軽量のものに変更すると、地震発生時の家屋の揺れを小さくできます。これにより、家屋へのダメージや家具転落のリスクを下げることができます。軽量な屋根材も幅広いデザインから選ぶことができ、劣化しにくい素材が多くあります。
軽量化で使われる主な屋根材は、次の3つです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 基礎の補強工事
建物の基礎にダメージが入っている場合、地震発生時に家屋が倒れてしまう可能性が高まります。震災後に見た目に異常がなくても、基礎コンクリートにヒビ割れが起きていたということも。
多少のダメージであれば大きな影響はありませんが、気づかぬうちに次のような状況に陥っている可能性があります。
不安な方は業者に相談し、基礎土台の状況を確認してもらいましょう。
4. 接合部分の補強工事

家屋のなかには、柱や梁などがしっかりと接合されていないものがあります。なかでも過去にリフォームをして間取りを変えた方や増築された方は、新しく追加した箇所が既存のパーツにうまく接合されていないかもしれません。
一度業者に見てもらい、しっかりと接合されているか確認してもらうようにしましょう。
改修する際に使われるのは、主に次の2つです。
|
|
|
|
|
|
5. 鉄筋コンクリート構造への改修工事

鉄筋コンクリートとは、壁や柱などがコンクリートで構成されており、なかに鉄筋が入っている構造です。住宅の重量が増えてしまうため、地震の際に揺れが大きくなるデメリットがありますが、倒壊リスクは木造住宅より低いといわれています。
鉄筋コンクリートへの改修で行われるのは、主に次の2つの施工です。
- 木造住宅をリノベーションし、鉄筋コンクリート構造に変える
- 無筋コンクリートの家屋に鉄筋を追加する
各工事の価格一覧
実際に耐震補強工事をする際、安くても20万円、高いものだと1000万円以上かかります。
以下の表を参考に、気になる箇所とご予算を照らし合わせて施工内容をプロに相談するのも、おすすめです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐震補強工事は、ほんとうに必要?

地震大国の日本では、いつ地震がきてもいいように耐震補強工事をお考えの方も多いでしょう。しかし、現在は建築基準法によって、震度6~7の揺れであれば倒壊しない家屋の建築が義務付けられています。そのため、かならず耐震補強工事が必要なわけではありません。
ここでは、耐震補強工事を受けたほうがいい家屋の特徴を5つ紹介します。
- 1981年6月より前に建築された
- 2000年6月より前に建築された
- 過去に震災被害を受けた
- 増築や改築の経験がある
- 何かしらの不安がある
1. 1981年6月より前に建築された家屋
建築基準法の改正にともない、1981年6月1日以降に建築された家屋には新耐性基準の適応が求められました。
違いは以下のとおりです。
|
|
|
|
|
|
正確には、役所で建築確認申請が受け取られ、確認通知書(副)が発行された日付で、家屋がどちらの基準に沿っているかが分かります。
旧耐震基準の家屋でも震度5まではそなえられますが、大きな震災にそなえたい場合は、耐震補強工事の実施を検討してみてください。
2. 2000年6月より前に建築された木造の家屋
新耐性基準に加え、「2000年基準」と呼ばれているものがあります。これは2000年6月から適用が開始された基準で、木造家屋のみを対象としています。
主に以下3点に関する震災対策が強化されました。
- 地盤に適した基礎の設計
- 柱や筋交いの接合
- バランスのよい耐震壁の設置
2000年6月よりも前に建てられた木造家屋にお住まいの方は、地震へのそなえが十分でない可能性があります。
3. 過去に震災被害を受けた家屋
新耐性基準や2000年基準にもとづいて設計された家屋であっても、かならずしも安全とは言い切れません。
例えば過去に震災被害を受けている場合、家屋の見た目に異常がなく、問題なく日常生活を送っていたとしても、基礎部分や壁の内部に割れ目などのダメージが入っている可能性があります。
この場合、建築されたときよりも建物の強度が低くなっている可能性があります。
4. 増築や改築の経験がある家屋
増築や改築をする際、柱などがきちんと接合されていない可能性があります。そのため、比較的新しい家であったとしても、建物の強度が低くなっている場合も。
もし不安がある場合は、リフォームを担当した会社だけではなく、耐震診断などを受けて第三者から評価を受けてください。
5. 何かしらの不安がある
上記4つに該当しない場合であっても、次のようなお悩みを抱えてはいませんか。
こうした場合、知らず知らずのうちに家屋が老朽化してる可能性があります。放置せずに、耐震補強工事を検討しましょう。
耐震補強工事を受けるまでの流れ
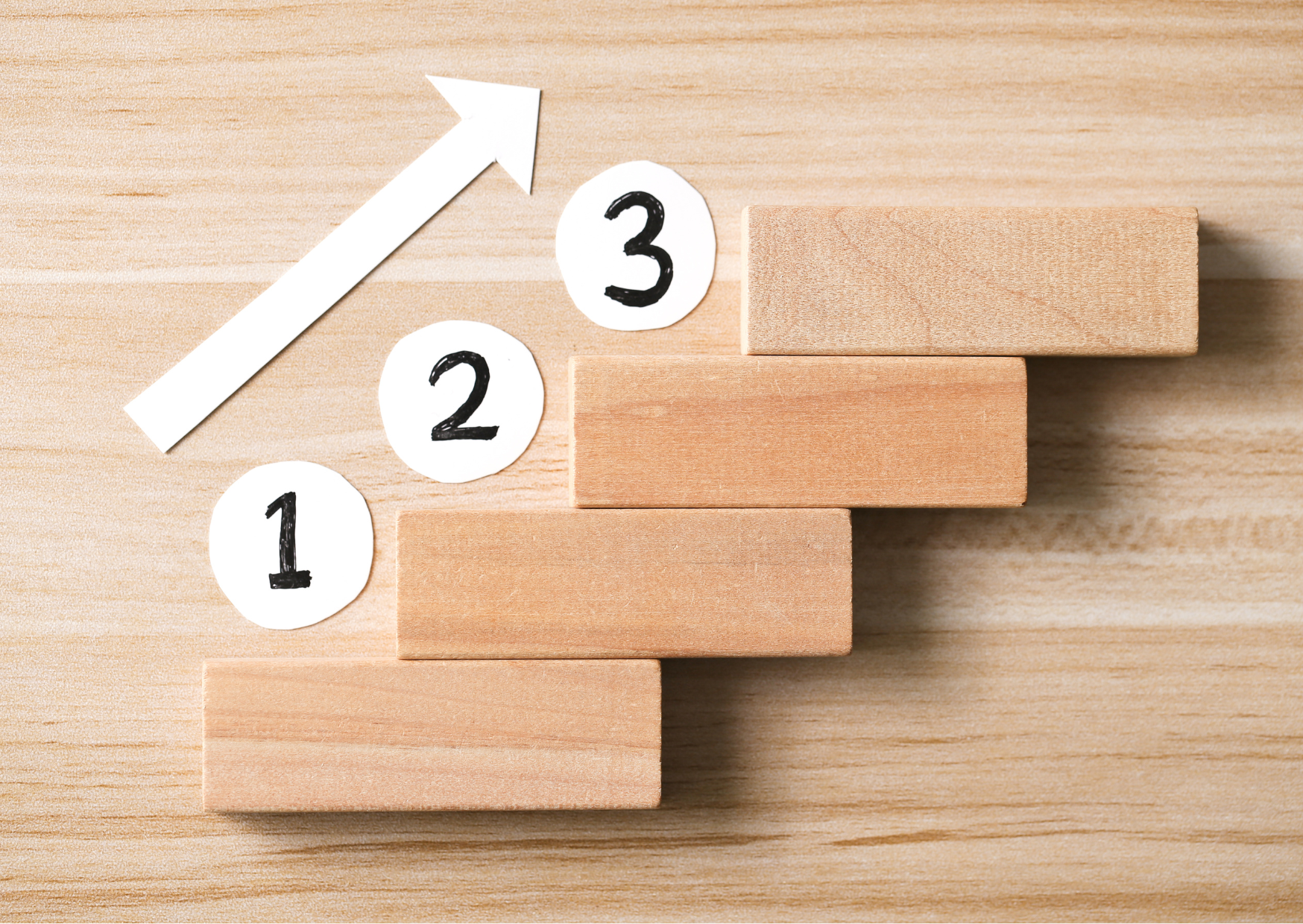
「耐震補強工事を受けたいが、具体的にどの工事が必要か自分では分からない」
「不必要な工事をして、出費を増やしたくない」
そういったお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?耐震補強工事を受ける際は、施工会社に依頼する前に「耐震診断」を受けて、必要な耐震補強工事を明確化することがおすすめです。
実際の流れは以下の通りです。
|
|
|
|
|
|
|
|
耐震診断とは
耐震診断は、日本建築防災協会が定めた方法と基準にもとづき、建物の倒壊リスクを4段階評価で評価します。自宅の地震への耐性を確認できるだけでなく、必要な耐震補強工事を教えてくれます。そのため、補強耐震工事をおこなう前に診断を受けておくことがおすすめ。
また、耐震補強工事をする際に助成金や税額控除を受けたい方は、かならず耐震診断を受けてください。耐震診断の評価にもとづいた改修が控除を受ける条件となっているためです。
耐震診断で知れること
耐震診断では、家屋そのものだけではなく、周辺環境についても調べてくれます。
実際の箇所と詳しい診断内容をまとめたので、参考にしてください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐震補強工事でもらえる助成金
耐震補強工事をおこなう際、助成金がもらえます。
しかし国による全国的な助成金制度はなく、基準や金額は自治体によって異なります。そのため、まずはご自身がお住まいの地域の条件を調べるようにしましょう。
ほとんどの自治体において、施工前に耐震診断を受けることが条件となっているので注意してください。
受け取り方や支給条件の調べ方は、次の3つです。
- お住まいの自治体のホームページで調べる
- 役所に行って直接相談する
- 一般社団法人「住宅リフォーム推進協議会」の検索ページから探す
耐震補強工事をおこなった際にしたい、節税対策

耐震補強工事に対する国からの助成金はありませんが、次の2つの税金を減額できます。
- 所得税
- 固定資産税
1. 所得税の特例措置
以下の条件に当てはまる工事をおこなった場合、施工費用の10%相当が所得税から控除されます。
- 耐震改修にかかった費用であること
- 1981年6月よりも前に建築された家屋であること
- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること
- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること
- 税務署に確定申告をおこなうこと
- 控除上限は62.5万円
2. 固定資産税の特例措置
以下の条件に当てはまる工事をすると、1年間、1戸あたり120㎡分の固定資産税を半額にすることができます。
- 1982年1月1日よりも前に建築された家屋であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること
- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること
- 工事後3カ月以内に申告していること
- 工事にかかった費用が50万円以上であること
富山県で耐震補強工事をお考えの方はユニテにご相談ください
一級建築士が在籍しているユニテは、古い家屋におけるリノベーション・リフォーム実績も豊富。必要性やご要望に合わせた施工を提案し、安心して住み続けられる家づくりをお手伝いします。
ぜひ、一度ご相談ください。
まとめ
木造住宅の耐震補強工事について、以下の4点をお伝えしました。
- 耐震補強工事の種類と金額
- 耐震補強工事が必要な家屋と必要ない家屋の見極めポイント
- 施工を受けるまでの流れ
- 耐震補強工事の助成金と節税対策
不必要なコストをかけずに、十分な耐震補強工事をする際の参考にしてみてください。