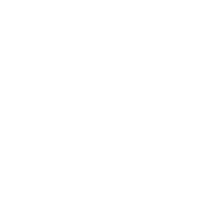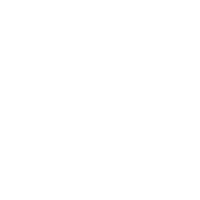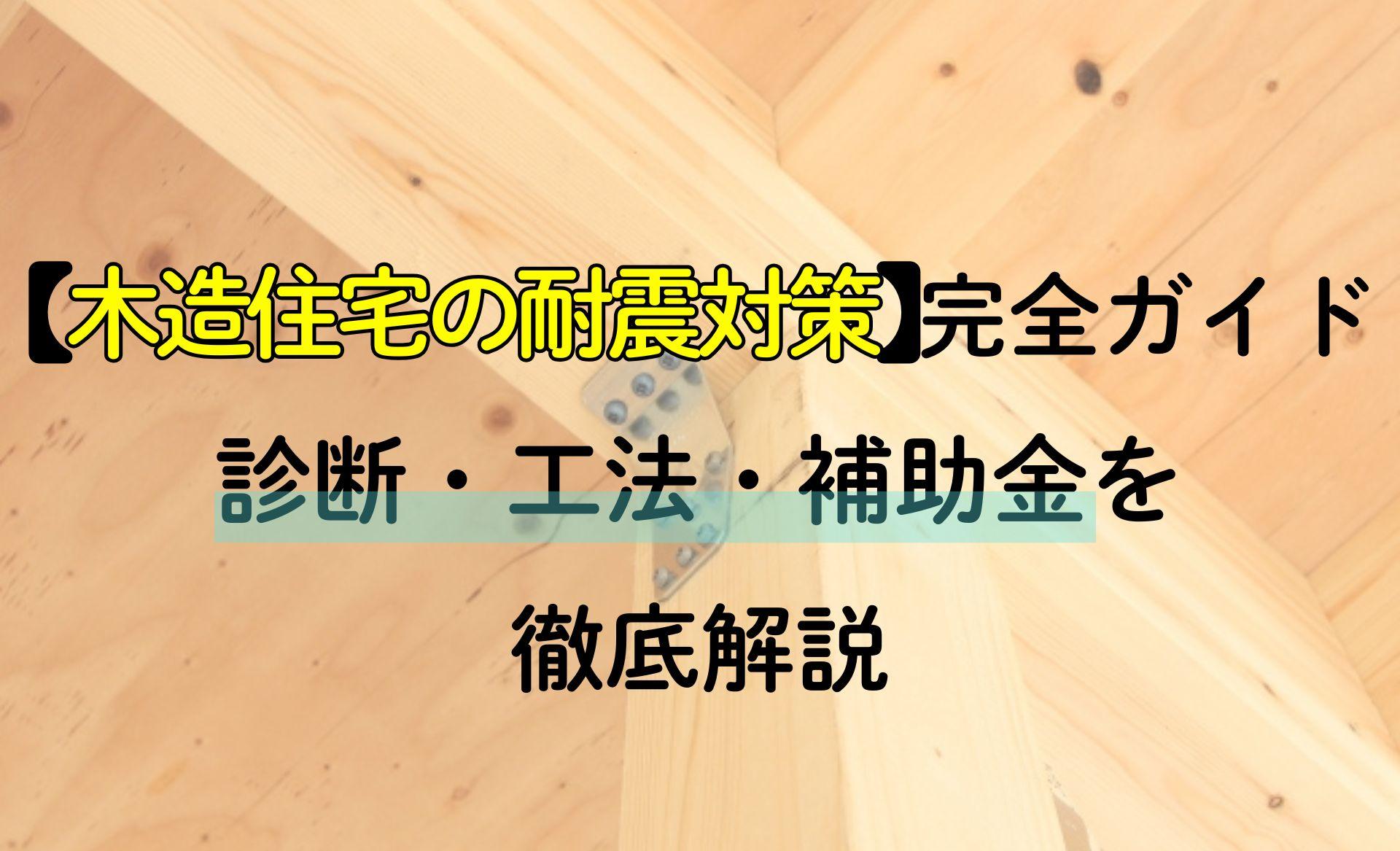
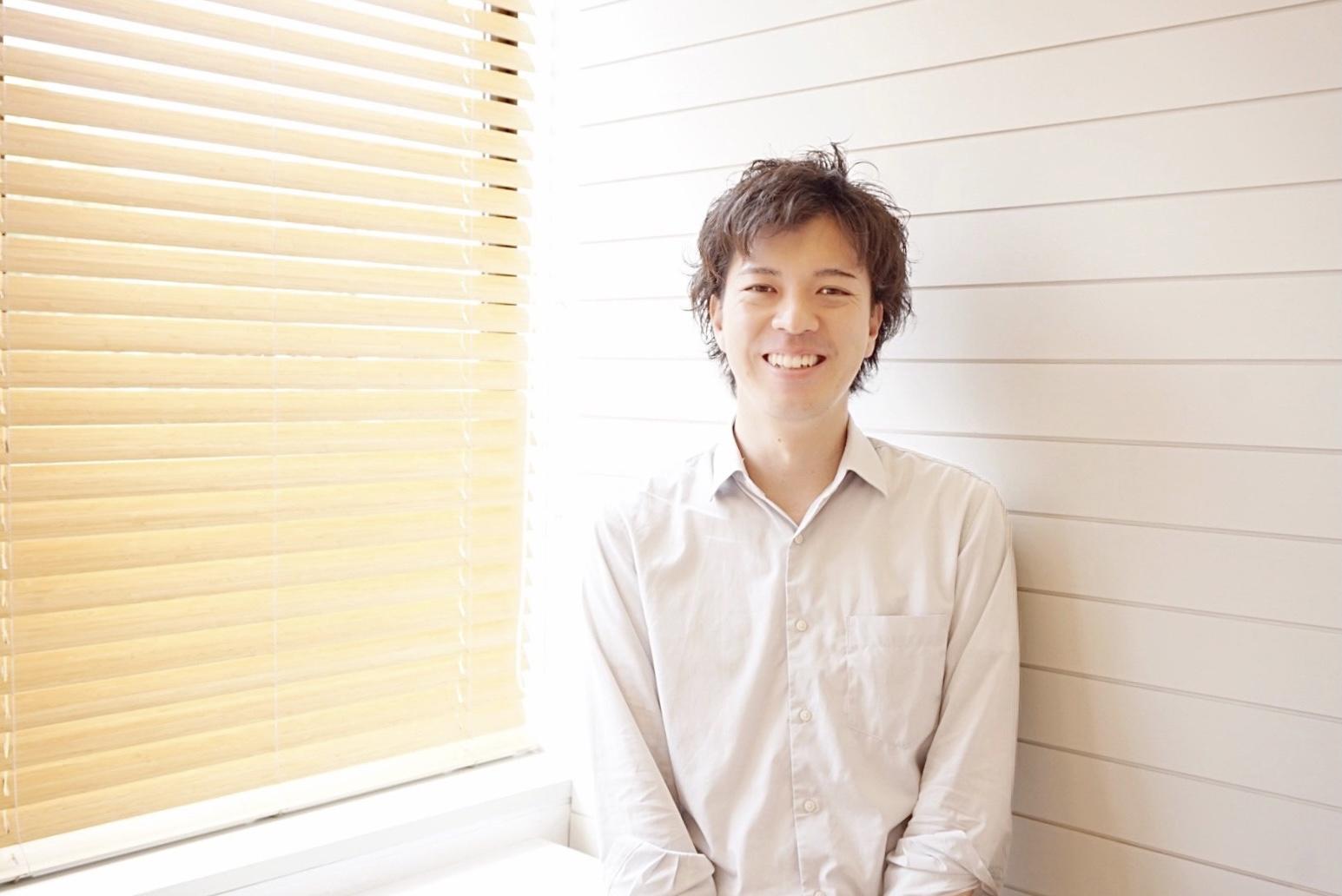
株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
地震大国の日本では、木造住宅の耐震性能が命を守る重要な要素となります。しかし、とくに築年数のたった木造住宅は、現代の耐震基準を満たしていない可能性が。
本記事では、木造住宅の耐震対策について、以下のポイントをわかりやすく解説します。
- 木造住宅の耐震基準と耐震等級
- 耐震診断の方法・流れ
- 効果的な耐震改修工法
- 費用負担を軽減できる補助金制度
家族が安心して暮らせる住まいづくりのために、正しい知識を身につけましょう。
木造住宅の耐震性

基本的に木造住宅は地震に強いとされます。木造住宅の耐震性の特徴や弱点を知りましょう。
| 特徴 | 弱点 | |
| 木造住宅 |
・木材の柔軟性により、地震の揺れを吸収しやすい |
・鉄骨造住宅よりも法定耐用年数が短い |
木造住宅の弱点は、計画的な点検と必要な補強工事を実施すれば改善できます。耐震診断を実施して木造住宅の状況を知り、必要に応じた対策をとりましょう。
木造住宅の耐震基準
耐震基準とは、建物が地震に耐えられるように定められた基準のことです。木造住宅も耐震基準が設けられています。
木造住宅の耐震基準は、1981年と2000年に大きく改正され、大きく3つの耐震基準にわかれます。耐震基準は住宅が備えるべき耐震性能の最低限のレベルを示すものです。
1995年におこった阪神・淡路大震災では、被災した木造住宅の98%は旧耐震基準で建てられていたことがわかっています。
また、2016年に発生した熊本地震では、旧耐震基準の木造住宅の倒壊率は28.2%なのに対し、新耐震基準の倒壊率が8.7%、2000年基準の倒壊率は2.2%です。
参照:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書
過去におこった地震のデータを比較すると、耐震基準の効果の違いがはっきりと現れています。
木造住宅の耐震等級
耐震等級とは、建物がどれだけ地震に強いかを判定するための評価基準です。2000年に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づいて定められています。
建物がどれだけ地震に耐えられるかを示す指標として、耐震等級1・耐震等級2・耐震等級3まで、3つの段階が設定されています。
| 等級 | 特徴 |
|
耐震等級1 |
・建築基準法で定められた最低限の耐震性能 |
|
耐震等級2 |
・耐震等級1の1.25倍の耐震性能がある |
|
耐震等級3 |
・耐震等級1の1.5倍の耐震性能 |
こんな木造住宅は要注意!
以下のような特徴が見られる木造住宅は、耐震診断や耐震改修を検討しましょう。
- 1981(昭和56)年5月31日以前に着工された家
- 大地震を経験している家
- 液状化など地盤が悪い地域に建つ家
- 基礎や外壁に大きなひびが入っている家
- シロアリが発生している家
- 1階に車庫があり、柱や壁が少ない家
- 1階の南側に大きな窓がある家
- 建物の四隅に壁がない家
- 瓦屋根(土葺き)や土壁で塗られた木造住宅
- 柱のサイズが12cm×12cm以下の家
日本建築防災協会の「誰でもできるわが家の耐震診断」を利用し、ご自宅は耐震診断や耐震診断が必要かどうかをチェックしましょう。
木造住宅を守る!耐震診断とは

耐震診断とは、地震に対する建物の強さを調べ、今の耐震性能を評価する検査のことです。
新耐震基準を満たしている木造住宅でも、経年劣化により耐震性が低下する可能性があります。定期的な点検と必要に応じた補強が推奨されているのです。
とくに、築30年以上の住宅は、耐震診断を受けることをおすすめします。耐震診断の流れや費用について知りましょう。
耐震診断の流れ
まずは木造住宅の耐震診断を受け、耐震性が十分でないと判断された場合は、補強工事の実施を検討しましょう。
耐震診断は一般診断法と精密診断法の2つがあります。
一般診断法:図面を確認し、目視で行う。壁などをはがすような検査はしない
精密診断法:必要に応じて壁などを剥がし、内部の構造までチェックする
通常実施される一般診断法の流れは、次のような手順で行われます。
1.予備調査:建物の基本情報やこれまでの改修記録など、調査に必要な書類やデータを集める
2.設計図の有無を確認
3.診断方法を決定する
4.現地調査:木造住宅に適した診断方法により耐震診断を行う
5.解析・診断:調査内容から耐震性能を計算し、診断する
6.評価:調査結果から総合的な耐震性能の診断し、評価をする
一般診断法の耐震診断を行う場合、必要な書類がそろっていれば1時間半〜2時間程度です。設計図などがない場合は、建物を測定・調査して収集するため、2〜2時間半ほどかかるでしょう。
耐震診断の一般的な費用
木造住宅の耐震診断にかかる費用は、建物の大きさや状態によって異なります。日本建築業連合会によると、耐震診断にかかる費用は一般的な木造住宅で『12〜25万円程度』ほどです。
また、耐震診断にかかる費用は、お住まいの地域や依頼する業者によって違います。富山県によると、富山県の一般的な耐震診断の費用は、5万円〜10万円ほどです。
まずは、耐震改修支援センターや地方公共団体の相談窓口に問い合わせましょう。地域の一般的な耐震診断の費用や、補助金情報を得られるでしょう。
耐震診断の補助制度
多くの自治体で、耐震診断の助成制度を設けています。それぞれの自治体が独自の支援制度を設けているため、お住まいの地域によって受けられる補助内容が変わるため注意しましょう。
助成金を利用するには、耐震診断を受ける前にお住まいの市区町村に問い合わせることをおすすめします。
富山県は、耐震診断費用の9割を補助。自己負担2,000円〜6,000円程度で耐震診断を受けられます。
- 木造一戸建、平屋建てか2階建ての建物
- 昭和56年5月31日以前に着工して建てられた
- 軸組工法によるもの(伝統工法によるものも含む)
- 令和6年1月1日の能登半島地震で被災した住宅
(準半壊以上・災証明を受けたもの、昭和56年6月1日以降に着工して建てられたものが対象)
参照:富山県庁ホームページ
木造住宅を耐震補強して命を守る

こ耐震診断によって建物の耐震性がわかったら、必要に応じて耐震補強工事を実施します。地震への抵抗力を高めるため、現在の建物に補強を加える工事を行いましょう。
木造住宅の耐震補強の方法
木造住宅の耐震性を高めるため、建物の状態に合わせて主に以下の補強方法を適切に組み合わせ工事を実施します。
- 壁を増やす
- 接合部を補強する
- 基礎を補強する
- 屋根を軽くする
壁を増やす
壁を増やしたり、バランスよく配置したりして、地震に強い建物にします。
例えば、柱だけでは地震の力に耐えきれませんが、筋交いを入れて耐力壁を追加することで、建物の強度を高められます。
また、壁や柱がかたよって配置されていると、地震の揺れでねじれが生じ、建物に大きな負担が。壁のないところに耐力壁を設置し、建物全体のバランスを改善させます。
接合部を補強する
地震の揺れによって柱などが外れると建物が倒壊する可能性があります。接合部を金物でしっかりと固定することが重要です。
地震時の揺れで柱が浮き上がるのを防ぐホールダウン金物や、柱と土台を固定するためのL字金物などを、建物の状況に応じて取り入れます。
基礎を補強する
基礎や土台がしっかりしていないと、建物が倒壊する危険性が高くなります。基礎を補強して地震に耐えられる建物にしましょう。
鉄筋が入っていない無筋コンクリート基礎には、樹脂を注入したり、新たに鉄筋コンクリート基礎を抱き合わせて補強します。
屋根を軽くする
屋根の重さは建物全体の耐震性能に影響します。建物の上部が重いと地震の揺れが増幅しやすいためです。
重たい葺土を使用して固定した日本瓦を、軽量瓦・化粧ストレート屋根・金属屋根(トタンやガルバリウム鋼板)などに改修して屋根を軽量化させます。
耐震補強工事の流れ
耐震診断の結果建物の耐震性が不十分と判断された場合に、耐震補強工事を行います。耐震診断後の耐震補強工事の流れを見ていきましょう。
1.耐震診断の結果を確認し、補強計画を作成
2.予算スケジュールなどを確認し、耐震補強プランを決定
3.工事を実施
4.工事が完了したら、完了検査を行う
耐震補強工事に補助金を活用するなら、申請後承認されてから、正式な契約を結び工事を実施しましょう。
工事が完了し費用の支払いを済ませたら、完了報告書を提出し耐震審査を受けたのちに補助金が支給されます。
木造住宅の耐震改修工事の一般的な費用
木造住宅の耐震補強の費用は、建物の状態や耐震診断結果によって変わります。
一般財団法人日本建築防災協会「耐震改修工事の目安」によると、一般的な木造住宅の耐震改修工事は100〜150万円未満の工事が最も多いです。全体の半数以上の工事が約140万円以下で行われています。
また、耐震補強工事は壁を解体する機会も多いです。劣化した部分のリフォームも一緒に行えば、工期短縮、コスト削減の両方のメリットが得られます。
さらに、国や地方自治体の助成制度を活用すれば費用を抑えられるでしょう。
耐震改修の補助金制度
耐震改修工事の助成制度は、耐震診断と同じようにそれぞれの自治体が独自の支援制度を設けています。工事費用の一部を補助しますが、お住まいの地域によって受けられる補助内容が異なるため注意しましょう。
富山県は、耐震改修の工事費5分の4を補助します。補助金の限度額は100万円です。対象となる住宅は、富山県庁ホームページをご覧ください。建物がある市町村窓口へ問い合わせましょう。
各自治体は、耐震対策用の補助金として使える金額を年度ごとに設定しています。補助金制度は年度によって内容が変更される可能性もあるため、必ず自治体に確認しましょう。
お住まいの耐震補強の補助金が知りたい方はこちらからご確認ください。
木造住宅の耐震についてよくある質問

木造住宅の耐震化について、よくある質問と回答をまとめました。
木造と鉄骨造どちらが地震に強いの?
木造と鉄骨造は、地震に対してそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらが強いかを単純に判断できません。
| 木造 | 鉄骨造 | |
| 地震に対する強さ |
地震の揺れを吸収しやすい |
地震の揺れに耐える強度が強い |
| 重量 | 軽い | 重い |
| コスト | 抑えられる | 高い |
| 耐久年数 |
60年程度 |
100年程度 |
建物の重さと高さが大きくなるほど、地震から受ける力も大きくなります。そのため、重量の軽い木造は、重い鉄骨造と比べて地震の影響を受けにくく、耐震面では有利です。
木造住宅は震度いくつまで耐えられるの?
木造住宅の耐震性の寿命は、建築時の品質・構造・メンテナンスによって大きく変わります。
国土交通省は、工学院大学の吉田教授・早稲田大学の小松教授らが行った建物の平均寿命に係る既往研究を公表しています。
調査を開始した1997年の木造住宅の平均寿命は約44年だったのに対し、2011年木造住宅の平均寿命は『65年』という結果になりました。
建築技術の進歩や、耐震補強への関心が向上し、定期的なメンテナンスの重要性が認識されたからだと推測できます。
こまめなメンテナンスや耐震補強を行えば、地震に負けない木造住宅になるでしょう。
木造住宅の耐震対策で安心して暮らせる家に

大切な家族を守るためには、まず我が家の耐震性を知ることが重要です。
木造住宅の耐震性を高めるには、まずお住まいの建物の耐震性を知りましょう。耐震診断を行えば、建物の地震に対する強さを知るきっかけになります。診断結果に基づいて適切な耐震補強工事を実施すれば、より地震に強い建物にすることができるのです。
耐震診断・耐震補強工事ともに、各自治体それぞれで助成制度が設けられています。少ない負担で耐震性を高められるため、積極的に活用し安心して暮らせる家を手に入れましょう。
私たちユニテは、多くの耐震改修工事を含むリノベーション実績があります。
補助金制度に詳しいスタッフが、お客様のご予算とライフスタイルに合わせたベストな提案をさせていたします。
大切なお住まいの安全性と快適性を高めるお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。