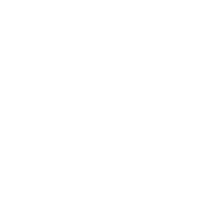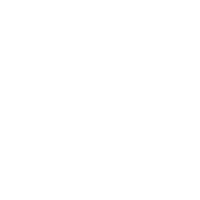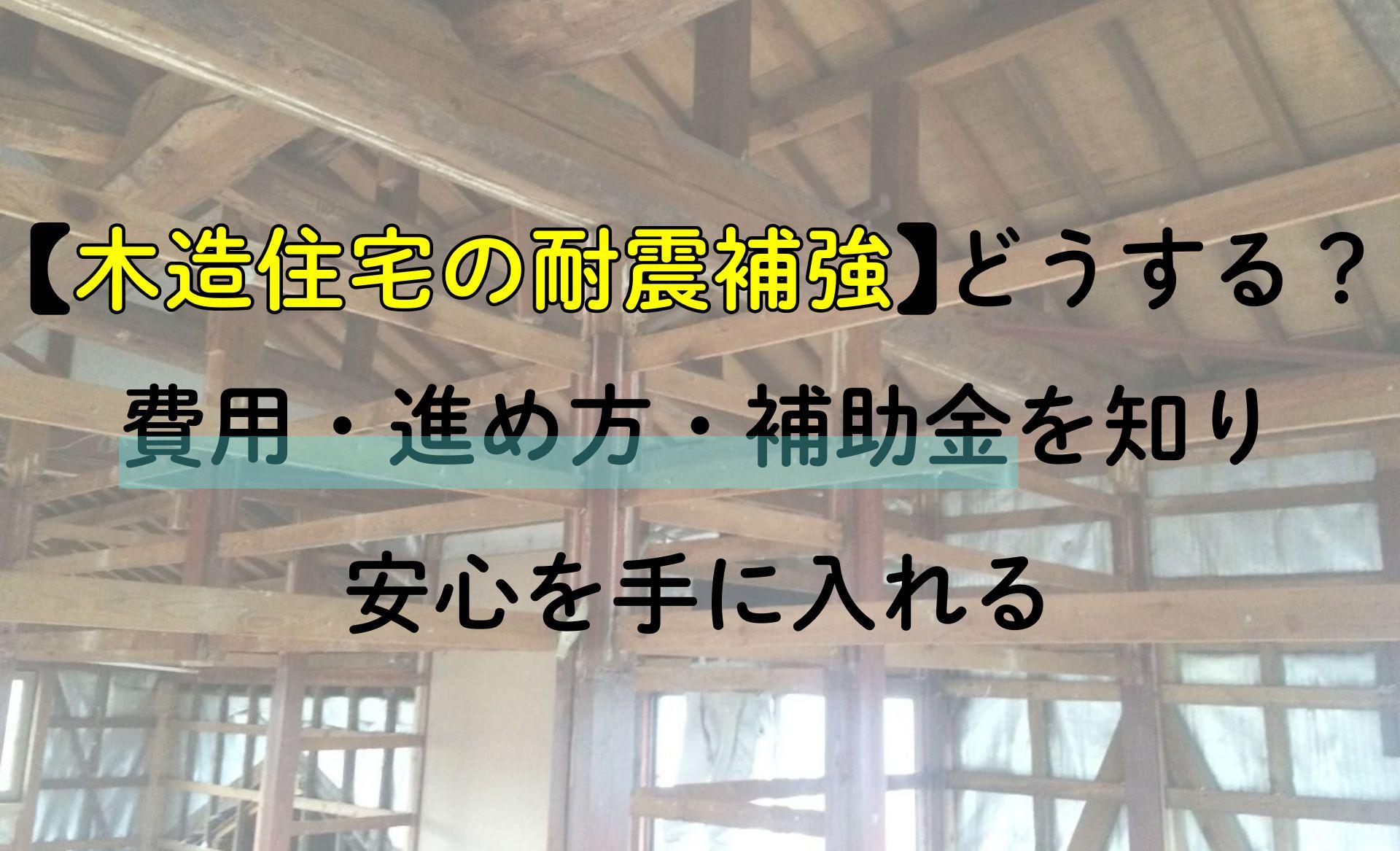
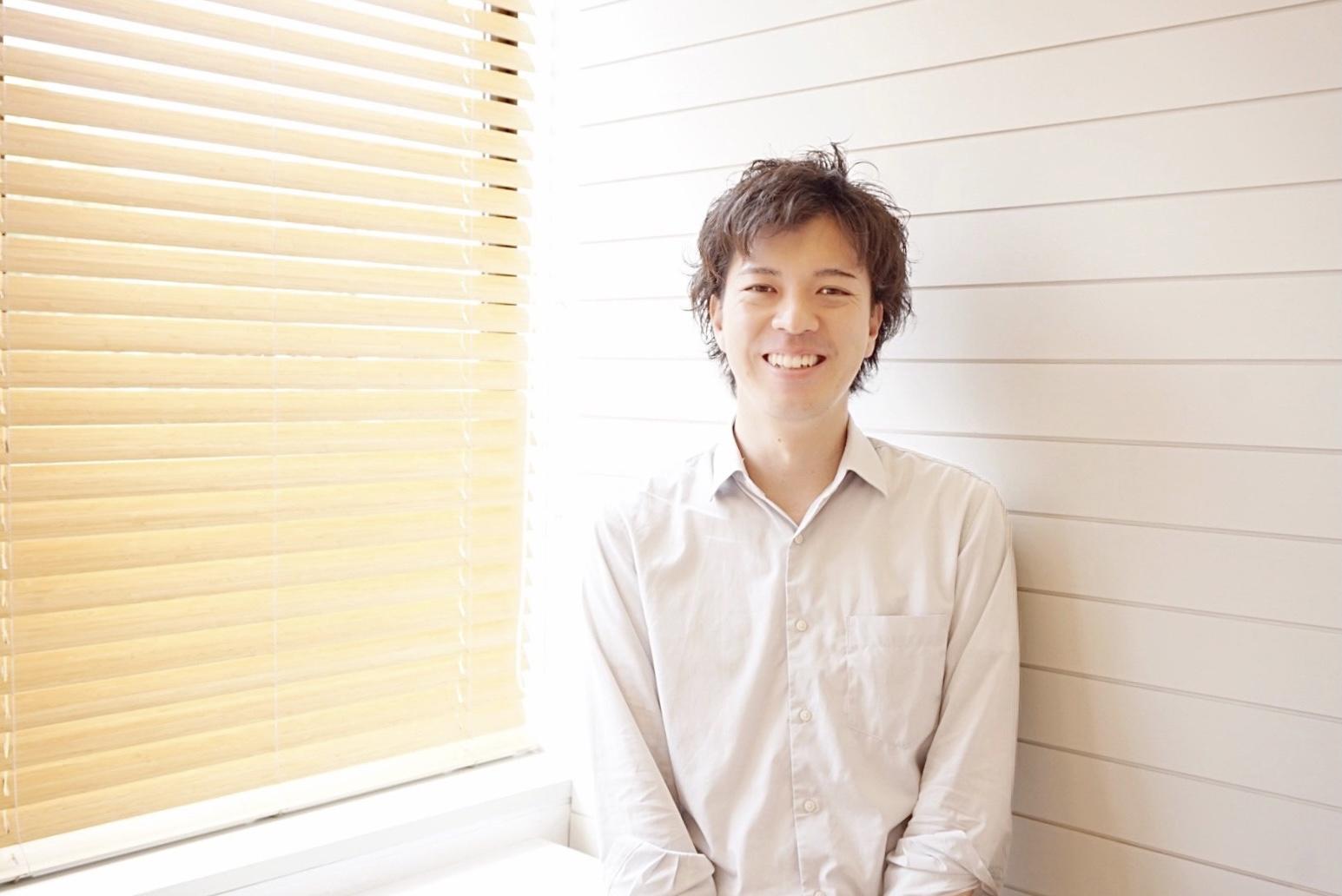
株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
お住まいの木造住宅の耐震性に不安を感じていませんか?耐震補強した方が良いと思っていても「費用が高そう」「どこに相談したらいいの?」と、踏み出せない方が多いでしょう。
この記事では、木造住宅の耐震補強について以下のポイントを紹介します。
- 具体的な補強方法と効果
- 工事にかかる費用の目安
- 工事の進め方とポイント
- 活用できる補助金制度
- 信頼できる事業者の選び方
家族の安全を守るために必要な耐震補強。正しい知識を身につけて、安心な暮らしへの第一歩を踏み出しましょう。
木造住宅の耐震補強が必要な理由

築年数が古い木造住宅は、地震の揺れに対して弱い構造になっています。柱や壁の強度不足、接合部の緩みなど、目には見えない弱点が隠れていることも。
耐震補強で木造住宅の強度を高めれば、家族の命と財産を守り、安心して住み続けられます。
木造住宅の特徴と弱点
基本的に木造住宅は地震に強いといわれています。木造住宅の特徴を見ていきましょう。
一方で、木造住宅は経年劣化により強度が低下するリスクがあります。
これらの木造住宅の特徴と弱点を理解した上で、定期的な点検を行うことが木造住宅の耐震性を高めます。
こんな木造住宅は要注意!

1981(昭和56)年5月31日より前に建てられた木造住宅は、耐震補強が必要です。1981年6月に建築基準法が改正され、耐震基準が強化される以前の建物だからです。
実際に、1995年阪神淡路大震災において、1981年以降に建てられた建物は被害が少なかったことが報告されています。
以下のような特徴が見られる木造住宅は、耐震補強が必要です。
- 大地震を経験している家
- 液状化など地盤が悪い地域に建つ家
- 基礎や外壁に大きなひびが入っている家
- シロアリが発生している家
- 1階に車庫があり、柱や壁が少ない家
- 1階の南側に大きな窓がある家
- 建物の四隅に壁がない家
- 瓦屋根(土葺き)や土壁で塗られた木造住宅
- 柱のサイズが12cm×12cm以下の家
ぜひ、日本建築防災協会の「誰でもできるわが家の耐震診断」を利用し、ご自宅の耐震補強が必要かどうかをチェックしましょう。
木造住宅を耐震補強するメリット

地震の強い家に建て替えるより、木造住宅の耐震補強を行う方が、短い工事期間で費用を抑えられます。
一般財団法人日本建築防災協会「おしえて!地震に強い住まいづくり」で紹介されている、昭和50年に建てられた30坪の木造住宅を例に挙げましょう。
家を解体し同じ場所に地震に強い家を建てると約2,850万円かかりますが、耐震補強は180万円で行えます。工事日数も約5分の1で済むのです。
また、家の外壁や基礎の耐震補強は家に住みながら進められる工事もあります。
生活や負担を最小限に抑えられる耐震補強で、住み慣れた家を安全にしましょう。
木造住宅を耐震補強する方法

木造住宅を耐震補強する主な方法は、以下の5つです。これらの方法を組み合わせることで、木造住宅の耐震性能を効果的に向上させます。
- 壁を補強する
- 接合部を補強する
- 建物の基礎を補強する
- 屋根を軽量化する
壁を補強する

木造住宅の壁を補強し、耐震性を高めます。壁の補強は耐震補強工事でメインとなることが多いです。壁を強くすることはもちろん、数を増やし、バランスよく配置します。
壁を補強する際によく用いられるのが「筋交い」です。筋交いとは、柱と柱の間に斜めに設置する部材のことをいいます。壁の中に隠れるように取り付けられます。
耐震補強で筋交いを行う場合は、土台や梁と接合させて固定するため、壁だけでなく床と天井の解体も必要です。
接合部を補強する

筋かいと柱・筋かいと土台・柱と土台・柱と梁柱といった接合部を補強し、強度を強めます。適切な金物やボルトを正しい位置に取り付けることが重要です。
古い木造住宅では、もとからある接合部が劣化しているケースも。必要に応じて、接合部を補修してから新たな補強を行うこともあります。
建物の基礎を補強する

建物の基礎が弱まってしまうと、建物全体の安全性が低下します。木造住宅の状態や地盤の特性に合わせて、杭打ち工法・地盤改良工法・ベタ基礎工法などから最適な補強方法を選びます。
今の基礎に新たな基礎を打ち増しし、補強する方法が一般的です。基礎に鉄筋が入っていない場合は鉄筋やプレート入りの基礎で補強したり、亀裂がある場合は樹脂や繊維を注入したりして補修・補強を行います。
屋根を軽量化する

屋根瓦の重さで建物への負担が増えると、耐震性が下がる原因に。建物への負担を減らすため、屋根を軽くして耐震性を向上させます。
重い屋根瓦を、金属屋根(ガルバリウム鋼板など)・軽量スレート・軽量瓦などに変更するのが一般的です。
屋根の軽量化を行う際は、建物の構造や地域の気候条件をしっかり確認し、適切な材料と工法を選択しましょう。
耐震診断・耐震補強の流れ

耐震診断から耐震補強の流れを紹介します。
1、耐震診断を依頼する:お住まいの市区町村の耐震診断・改修の相談窓口に連絡し、補助対象の木造住宅かどうかを確認する。
2、耐震診断を受ける:専門家が設計図書や増改築の有無などの情報を集める。さらに現地で建物の現況を調査する。耐震診断の所要時間は、設計図書などがあれば約1.5〜2時間程度。
3、診断結果を分析する:耐震診断の結果を基に、必要な補強箇所を特定し、プランを作成する。
4、見積もりの作成と調整:耐震補強の詳細な見積もりを作成。予算に応じて工事内容を調整する。
5、耐震改修工事を進める
6、完了検査を行い引き渡す:工事完了後、耐震性能が向上したことを確認する
耐震診断を依頼する場合、対象となる住宅は診断費用がかかりません。お住まいの木造住宅が補助対象であれば、自治体が木造住宅耐震診断士を手配してくれますよ。
補助対象外の場合は、一般財団法人日本建築防災協会「耐震診断・改修の窓口一覧」から依頼する建築団体を探しましょう。
木材住宅の耐震補強にかかる費用

木造住宅の耐震補強は、家の形・住宅・大きさ・補強方法によって費用が変わります。一般的な耐震補強の相場や、耐震補強方法別の目安となる費用を見ていきましょう。
一般的な耐震補強費用の相場
耐震補強の費用は、お住いの住宅の状態や耐震診断結果によって変わります。
財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震改修費用」についての調査によると、多くの方が100〜150万円で耐震改修を実施し、187万円以下で済んだケースが半数以上です
さらに、国や地方自治体の助成金を活用すれば費用を抑えられるでしょう。
耐震補強方法別の費用比較
耐震補修の費用は、木造住宅の状態・耐震診断結果・耐震補強の方法や範囲によって異なります。
財団法人日本建築協会が紹介している「部位ごとの工事費用の目安」を参考に、標準的な金額を見てみましょう。
| 部位 | 価格 |
| 外壁 |
13~15万円/幅910mm |
| 内壁 |
9~12万円/幅910mm |
| 基礎 |
4~5.5万円/メートル |
| 屋根 |
1.5~2万円/平方メートル |
木造住宅の外壁や内壁の耐震補強は、リフォームと一緒に行うと工事単価が下がる可能性があります。
「外壁のヒビが気になる」「クロスが剥がれているので張り直したい」とお考えの方は、この機会に耐震補強とリフォームを行ってはいかがでしょうか。
木造住宅を耐震補強するなら補助金を上手に使おう

耐震診断や耐震改修の補助金制度は、国が基本的な制度を作り、各自治体が運用しています。
多くの都道府県で何らかの耐震関連補助制度はありますが、市区町村によって、受けられる支援の金額や条件はさまざまです。同じ都道府県内でも、市区町村によって利用できる補助金額が異なることも。
補助金の申請の流れや注意点を見ていきましょう。
地方自治体の支援制度
木造住宅の耐震診断や耐震補強については、支援内容や補助金の金額は自治体によって異なり、対象となる建物の条件も自治体ごとに設定されています。
耐震補強の補助金や助成金を利用するには、工事を実施する前にお住まいの市区町村に問い合わせが必要です。
富山県の耐震診断・耐震改修に対する支援制度をご紹介します。
耐震改修:工事費の5分の4を補助(100万円まで)
補助金が利用できる住宅の条件
築年数:1981(昭和56)年5月31日より前に着工して建てられた住宅
建物の構造:木造2階建て・平屋建て
使われている工法:軸組工法
参照:富山県庁ホームページ
富山県は築年数が古く立派で広い住宅が多いため、耐震改修費用が高額になる可能性があります。そのため、富山県は必要な場所だけ直す部分改修や、何年かに分けて少しずつ補強する場合も助成の対象です。富山県は、予算に合わせて少しずつ耐震化を進められるようになっています。
お住まいの耐震補強の補助金が知りたい方はこちらからご確認ください。
補助金申請の流れと注意点

耐震診断で助成金を利用する一般的な流れを見ていきましょう。
1、住んでいる自治体の耐震診断助成制度を確認する:多くの自治体で無料または低価格での耐震診断を実施する
2、必要書類を確認する:申請書・住民票・建物の登記簿謄本・固定資産税納税通知書の写しなどが必要
3、助成金を申請する
4、自治体が申請内容を審査
5、耐震診断の実施:審査に通過すると、自治体が指定する診断員が現地調査を行う
6、診断結果が自治体と申請者に報告される
7、助成金の交付される
つぎは、耐震改修を行う際の流れを見ていきましょう。
1、耐震診断:耐震診断に対する補助金制度と同時に使うことも可能
2、耐震診断結果に基づいて耐震補強を検討する
3、耐震補強の設計・耐震補強の見積もりを作成する
4、補助金を申請
5、申請承認されてから、工事の正式な契約を結ぶ
6、耐震補強工事を実施する
7、工事完了報告し補助金が交付される
補助金を利用する際は以下のポイントに注意しましょう。
- 助成金の申請には期限がある
- 予算に限りがあるため、早めに申請する
- 耐震診断・耐震改修をする前に助成金の申請をする
業者を選ぶポイント

木造住宅の耐震補強を依頼するなら、以下のような業者なら安心してまかせられます。
- 自治体が公表する業者
- 耐震工事の実績がある業者
- 工事内容や費用について詳しく説明してくれる業者
- アフターフォローが充実している業者
- 地域の建築事情に精通している地元の業者
- 各種補助金制度に詳しく、申請のサポートをしてくれる業者
各自治体によって、木造住宅耐震改修事業者リストなどが公表されています。自治体の相談窓口などを利用しても良いですね。地域の事情に詳しい業者を見つけやすいです。
富山県の木造住宅耐震改修事業者リストはこちらこらご確認ください。
また、耐震診断や補強工事の経験が豊富な業者に依頼しましょう。耐震補強は資格よりも経験が重要です。耐震診断と補強工事の両方に豊富な経験を持つ専門家を選ぶと良いでしょう。
ユニテは数多くのリノベーション実績があるため、耐震改修も数多く手がけてきました。補助金制度に精通したプロが、予算や暮らし方にあわせて提案します。
ユニテなら、住み慣れた家を安全・快適にするお手伝いをさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
木造住宅を耐震補強して家族の安全を守ろう

耐震補強で木造住宅の強度を高めることは、家族の命と財産を守ります。長く安心して住み続けられるように、耐震診断・耐震改修を検討しましょう。
- 大地震を経験している家
- 液状化など地盤が悪い地域に建つ家
- 基礎や外壁に大きなひびが入っている家
- シロアリが発生している家
- 1階に車庫があり、柱や壁が少ない家
- 1階の南側に大きな窓がある家
- 建物の四隅に壁がない家
- 瓦屋根(土葺き)や土壁で塗られた木造住宅
- 柱のサイズが12cm×12cm以下の家
多くの自治体で耐震診断や耐震改修の補助金制度があります。耐震補強の補助金や助成金を利用し、費用を抑えながら安心を手に入れましょう。